突然ですが、プラントエンジニアの業務は結構わかりにくいものです。各種サイトなどでいろいろ書かれていますが一般的・共通的な要素を集めていくうちに、抽象的な内容になってしまいます。身近な業務ではないので、もともとイメージがしにくいものなので、理解もしにくいでしょう。
そこで本記事では、私の担当業務を実体験に基づいて書いてみようと思います。プラントエンジニアに興味がある人に少しでも役立てばうれしいです。
この記事は、オーナーズエンジニアシリーズの一部です。
プロジェクト予算における労務費の考え方:オーナーズエンジニア視点から
オーナーズエンジニアとして働く前に知っておくべきリスクと対策
「実は知らないことだらけ」オーナーズエンジニアの設計業務の実態とは? ―丸投げ・不安・誤解…増改築プロジェクトの裏側
オーナーズエンジニア必見!プラント建設で費用を抑える検討手法まとめ
オーナーズエンジニアの設備設計は将来性があるか?
オーナーズエンジニアの仕事はゼネコンと関わる前後でどう変わる?
工事会社とオーナーズエンジニア、良い関係を保つためのポイント
オーナーズエンジニア必見!化学プラント予算管理の実践ガイド
保全こそが化学プラントのオーナーズエンジニアで生き残る
立会検査を最速で終わらせるコツ|オーナーズエンジニア向け
現地工事コストを抑えるためにオーナーズエンジニアができること
オーナーエンジニアが現場で実践すべき配管工事の品質管理手法
特定業務
プラントエンジニアの業務を特定業務と日常業務の2つに分けます。先に特定業務から解説します。こちらの内容の方が、プラントエンジニア的な内容です。
詳細設計
設備の詳細設計をするフェーズです。いかにもエンジニアの設計という業務です。成果物は設計書という書類になります。
設計書には以下のような内容が含まれます。
・設備の主要な仕様
・仕様を決定するに至った理由
・付帯設備、安全設備などの考え方
設計書では物理的な計算式をいっぱい使うものと想像するかもしれません。実際にはExcelで計算できる四則計算や微積分程度。計算ソフトを回すことはありません。
これらの計算以上に大事なのは、設備を選定するに至った経緯。書類としてまとまって記録されていなければ、問題が起きたときの対策を取りにくくなります。40年以上使い続ける設備である以上、同じ人がずっと担当するわけにもいかず、導入当初にしか設定できない考え方を書くことが設計書の意義です。
設備購入
設備の設計書を書くと、設備を購入します。設計者としては設備を購入するための仕様を決めることが大事で、逆にそのために設計書を書くと言っても良いでしょう。
設備の購入は仕様書という形になります。仕様書はどんな設備でも当てはまる契約的な条項の部分と、対象とする設備の仕様をまとめたデータシートの部分からなります。
理想は、仕様書に記載すべき内容と設計書で決定した内容が100%一致していること。設計書には考え方もプラスされており、仕様書は考え方だけを取り除いた形にすることが望ましいです。
とはいえ、実態はそうもいきません。設計書は設計書、仕様書は仕様書で様式が異なっていたり、過去に作ったものと同じ形にしないと行けなかったりもするかもしれません(本当はここをテコ入れすることがとても大事)。
仕様書はエンジニアリング業務を進める上で絶対に必要です。逆に設計書は無くても進んでしまうもので、設計書を作成する人が少なくなっているのが現状ですね。
技術査定
仕様書を作成して調達部に依頼を出せば、ベンダーに見積依頼が届きます。ベンダーが見積をするうえで技術的な打ち合わせをしたり、作成された見積の技術的な査定をします。
技術的な打ち合わせは、令和の現代でも電話を使う会社がとにかく多い印象です。メールを出して質問しても、1週間オーダーでの時差が発生するのがこの業界の特徴(私の今の業務だと社内外問わず1日で何かしら返事しないと遅いという印象ですが)。電話だと、ベンダー担当者が捕まらなかったり、エンジニア側も会議で不在だったりと、とにかく非効率さを感じる業務です(本当はここもテコ入れしないと、製造業の衰退の一因になると思います)。
査定はあくまでも技術的な部分に限定するのが難しい所。数量や仕様についてはその妥当性を考えて、単価など値段に関する部分は調達部に委ねるという役割分担が大事です。例えば、配管を製作するのに20日かかるという見積が出されて、この内容なら15日でできるはずだと査定するイメージ。15日でできるかどうかは、調達部とベンダーとの折衝で確定されます(結局はベンダーの主張する20日で納めることがほとんどのはず)。
手を抜こうと思えば、予算をそれなりに確保しておき、予算内であれば無条件に問題なしと査定してしまいます。予算を確保することが極めて大事になります。
略フロー作成
設備の仕様が決まったら略フローを作成します。仕様書や技術査定と並行して進められます。
本来なら設計書を書く段階で略フローも作成しないといけません。例えば配管口径やバルブ・ヘッダーの置き方、流量など計装関係の情報など、設計書では残すべきだからです。そうしないと設備のノズル情報など決められないはず。
多くの設備購入実績がある現代では、設備の仕様は既存と同じと割り切ってしまってそこから略フローを作成する方が多いです。老朽更新であれば略フローそのものが既存と同じとすることも可能です。
こうすることで確かに手を抜けますが、技術力を身に付けるためには全く役に立たないことは理解しておきましょう。既存を少しでも改善するという姿勢で設備の仕様を見ていくことは、理想的なプラント像を自身の中に構築していく上でも大事です。プラント建設などエンジニアの仕事の幅を広げることになるでしょう。
略フローができあがると、P&IDの作成をします。ここは私の場合、外部会社に委託しています。
図面チェック
P&ID・配管図・機器図などのCADを使った業務は、私の場合、外部に委託しています。これらの成果物をチェックするのは、エンジニアの業務です。いわゆる赤ペン先生です。チェックは、設計書・略フロー・既存のP&IDなどを頼りにします。
P&IDはページ数も多くはないので、1度はしっかりチェックします。1プラントで50枚くらいが建設段階で発生しますが、ここで特殊業務と位置つけている範囲では10枚にも満たない分量です。その大半が既存のP&IDの多少の修正のみ。ここをしっかりチェックするためには、化学工学的な知識がどうしても必要になります。手を抜こうと思えば、他部門にチェックを依頼してその集約だけをしても良いでしょう。繰り返しますが、技術力を身に付けることはできません。完成系が1度提出されチェックしたら、チェックバックを再確認する程度。業務時間としては数時間~1日程度の話です。
配管図は枚数そのものも問題ですが、1枚1枚の情報量が多いのでチェックが大変です。基本的にP&ID通りになっているかをチェックするのが最優先で、その後に現場の状況と見比べて操作性・投資・工事作業性などを総合的にチェックします。これもP&IDと同じで集約係になりきることは不可能ではありません。繰り返し・・・。チェックスキームはP&IDと同じですが、時間が1週間程度は掛かるでしょう。大きな工事だと、50%チェック・90%チェックなど段階的にチェックすることも大事です。
機器図は、ベンダーから五月雨式に提出されます。組立図が最初に提出されここをチェックした後に、部品図が提出されます。組立図のチェックがとにかく重要です。機械関係だけでチェックできるものでもないので、関係者に見てもらう必要があります。これも集約係に徹することができて(以下略)。
申請資料作成
設備やP&IDなどの工事に必要な資料ができあがると、官庁申請の資料を作成します。基本的にはすでに出来上がった資料の組み合わせなので、単なる作業となります。
申請をしっかりしないと工事はできないので、スケジュール管理の方が大事ですね。
資料引き渡し
これまで作成した資料を次の部門に引き渡します。工事・保全・計装・電気など複数の部門に跨ります。どの資料をいつまでに渡すかは、会社で業務標準として定めるべきものです。
必要に応じて説明会を開きますが、大抵の場合は資料を一方的に提出して終わりというのが、私のところの実態です。ですので、後で問題になったり不満がでたりします。
日常業務
日常業務について解説します。特定業務は仕事が発生したときに限定されますが、日常業務はいつでも起こりえる業務です。
FS見積
設備投資の見積をします。基本的には依頼部門からの要請に応えて実施するので特定業務扱いでも良いですが、エンジニアとしては日々理想的な設備構成を作り上げるための努力をするべきなので、日常業務と位置付けています。
依頼部門からの要請にこたえているだけでは受け身の業務となってしまい、依頼部門の都合に振り回されてしまいます。いつ依頼が来てもすぐに回答できるような、攻めの姿勢を取っておくと仕事をコントロールしやすくなり、社内での評判は上がるでしょう。
設備の単価情報や、工事の単価情報など、特定業務を行っている中で蓄積された情報をデータベース化していつでも取り出せるようにするのが大事です。多くのエンジニアが配置されている職場だと、足並みをそろえるのが大変となり、重要性はますます上がります(ですが一匹狼の体制でやり過ごそうとする会社の方が多いと信じています)。
予算管理
予算管理は予算を把握することを意味します。特定業務と位置付けても良いのですが、修繕費など毎年確実に割り当てられる予算もあるため、日常業務に位置付けます。
予算と使用した額をまとめて、今後の使用予定額と予想残額を把握し、関係者で共有するために使います。
理想的には1カ月に1回や大きな金が動いたときに把握するべきもので、プロジェクトマネジメントの練習として日常的に実施するものです。緩い環境だと、工事が終わった時には予算が余って問題ないので、道中の予算は全く管理しなくても進められるかもしれません(こういう人が多いのは弊社だけかも・・・)。
基準制改訂
エンジニアリングで使用する各種基準の制改訂をします。特定業務で直面した課題を基準に反映させるのは当然として、制定された基準の定期見直しも重要な業務です。とはいえ、改訂は基本的には部署名の変更など、小さなものに限定されるのが実態でしょう。
ただし、何も改訂しなくても監査の対象ではなくやり過ごせてしまうことも少なくありません。特定の基準だけが制改訂をしっかりすることになるでしょう。それに甘えてしまうと、使えなくなる基準が量産され、体系が崩壊していきます。
参考
関連記事
最後に
プラントエンジニアの業務は特定業務と日常業務に分けられます。特定業務では、詳細設計・設備購入・技術査定・略フロー作成・P&IDチェック・申請資料作成・資料引き渡しといったプロジェクトごとの仕事が中心です。一方、日常業務では、FS見積・予算管理・基準制改訂など、常に発生する管理や準備業務が中心です。特定業務で技術力を身につけ、日常業務で業務全体のコントロール力を養うことが、優れたプラントエンジニアになるポイントです。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)X(旧Twitter)のDMでも可能です。
- 設備設計で悩んでいる
- トラブル原因の考え方が分からない
- 若手の教育方法に困っている
など、幅広くお受けしています。
*いただいたコメント全て拝見し、数日中に真剣に回答させていただきます。
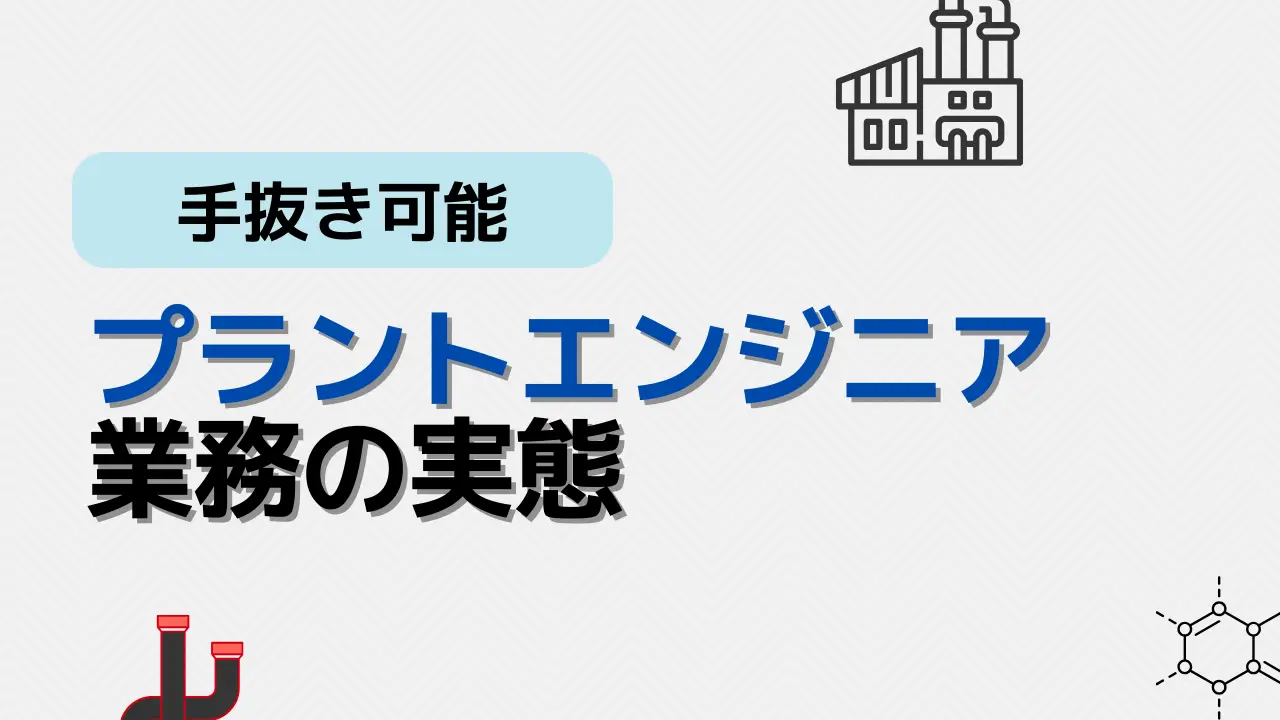

コメント