化学工場で働く機械・電気系エンジニアにとって、「化学工学」の知識はどこまで必要なのでしょうか?大学で機械や電気を学んできた技術者にとって、化学の話はややハードルが高く感じられることもあります。
本記事では、化学プラントの現場で求められる機電系エンジニアの役割と、化学工学の知識がどこまで必要かについて、現場経験を交えて紹介します。
化学工場の機電系エンジニアは、化学工学の知識が必要と言われています。機械系の学部でも化学工学と関連する分野の勉強はします。流動や伝熱です。
機械系の出身者にとって、化学工学は難しいものと捉えられて、流動や伝熱ですら勉強しない人が増えています。では、これらの知識がないエンジニアが、化学プラントでNGとなるのか?というとそうでもありません。
勉強した方が良いけども、しなくても何とかなってしまうという感じですね。
この記事は、機電系エンジニア性質シリーズの一部です。
【妄想】AIで化学工場の機電系エンジニアリングがこう変わって欲しい
化学工場×データサイエンス:機電系エンジニアが直面する“現場とのギャップ”とは?
化学プラントの機電系エンジニアはどう評価されている?現場・本社・製造のリアルな視線
プラント建設が減る中で、機電系エンジニアに求められる力とは
2024年版ものづくり白書を読む:プラント機電系エンジニアの視点から
化学プラントの機電系エンジニアが陥る“予算感覚のバグ”:コスト意識の再構築が必要な理由
競争相手が少ない化学プラント機電系エンジニア
マンツーマン指導が減少する化学プラントの機電系エンジニア教育課題
専門性が高すぎる?化学会社の機電系エンジニアのジョブローテーションと職場環境の実態
設計と保全の違いと連携の重要性──化学プラントの機電系エンジニア視点
機電系エンジニアの業務実態:化学工場での典型的な1日の流れ
機電系エンジニアの内面にあるこだわりと外から見た印象の違い
視野の狭さを克服する!機電系エンジニアが知るべき標準化・パターン化のポイント
機電系エンジニアの狭い範囲で時代に残されないためにできること
転職で化学プラントに来た機電系エンジニアのキャリアルート3パターン
技術力が徐々に低下している|化学プラントの機電系エンジニア
働かないおじさんの典型3パターン|化学プラントの機電系エンジニア
視野が狭い化学プラントの機電系エンジニアが気を付けたいこと
なぜ機電系エンジニアは受け身になるのか?──若手・中堅・マネージャー全員に共通する“意識の低下”
機電系エンジニアが“抱え込み”やすい本当の理由──思考のクセと成長機会の損失
院卒・大卒・高卒まで幅広く機電系学生を歓迎する化学プラントの実情
図面と数値だけじゃ足りない!言語化ができる機電系エンジニアになる方法
化学プラントの職種別「1日の流れ」:機電系エンジニア・保全・製造部のリアルな時間感覚
機電系エンジニアの事務仕事実態:パソコン苦手がもたらす現場の課題
機電系エンジニアが化学プラントで直面する「分からない」11の壁とその乗り越え方
言語化で差をつける化学プラント機電系エンジニアの仕事術:設備情報・使い方・工事・運転を徹底解説
使えればいい
機電系エンジニアが仕事をする対象は設備です。
健全な設備を現場に導入する
これが最大使命と言って良いでしょう。
配管が流れればそれでいい、というのと同じである程度使えれば基本的にはOKです。
少しくらいの問題があることは、多々あります。
基本設計で設定した能力に対してプラント運転に影響を与えない範囲の差であれば、問題ありません。
個人のスキルとして、自分が設計した能力通りの結果が現場で得られることは、重要なことでやりがいを感じる部分です。
しかし、この達成感を皆が皆感じることはなく、達成できる人が少ない、そもそも入社する人も少ない、という状況では高望みと言えるでしょう。
成果に対する費用対効果が低い
機電系エンジニアが化学工学を使って得られる成果は、設計した仕様と実運転の能力との差の大小の部分です。
この大小の差は、エンジニアとしては大きく感じる人も居ますが、工場全体を俯瞰したときにはそこまででもありません。
例えば、100L/minの流量を流すポンプを設計しようとして、90L/minしか現場で流れなかった時に、化学工学の知識を駆使します。
ポンプの性能が予定通りで流量が出ないとなったら、圧力損失を疑います。
液物性、配管口径、圧力、調整弁などの圧力損失部、劣化状況、ポンプ電流・・・
流動の分野だけを見ても、いろいろな要素を考えないといけませんね。
これらをトータルで見れる人が激減しています。
- プロセス物性は知っているけど、ポンプのことは知らない
- ポンプの機械的なことは知っているけど、電気的なことは知らない
- ポンプの電気的なことは知っているけど、他は知らない
細分化されていったとしても、その人たちが力を合わせればそれなりの答えが見えてきます。
取りまとめをする調整役は大変でしょうが、全員が調整役をする必要はありません。
仮に化学工学の知識があったとして、90L/minの流量を100L/minに上げる手段を何の投資もなく実現することは難しい可能性が高いです。
100L/minがどうしても必要というのであれば、別の機械に少し大型のポンプに交換してしまえば、問題は解決してしまいます。
問題が起きたときに化学工学の知識を使って、特定の人が頑張って何とかしようとしても結果は得られず、お金で解決せざるを得ないと割り切ったら以降の検討は止める。
その間の生産機会の損失は、計画に盛り込んでおく。
こういう判断をしていけば、機電系エンジニアが化学工学の知識を持つ必要は薄くなります。
成長に対する費用対効果が低い
機電系エンジニアが化学工学を学ぶと言っても、使いこなせるレベルに到達するには時間が掛かります。
教科書などの自主勉強で基本知識は習得できても、実務に対する適用をする機会が多くはないからです。
使えれば良いという設備の世界において、機電系エンジニアが現場の検証をするチャンスは1年に数回歩かないかでしょう。
現場の声を聴き、改善案を考え、トライアルして結果をもらう。
このPDCAサイクルを回せることはほぼありません。
どこかのタイミングでストップします。特にトライアル後の結果フィードバックの部分は、1年先の話になったりして忘れ去られます。
そうすると、せっかく学んだ知識を活かす機会が少なくなり、機電系エンジニアに聞いても意味がないと判断されて、ますます活かす機会が少なくなります。
プロセスエンジニアや製造現場に居ないと、成長機会が少なくなりますね。
本当に重要なものはメーカーを呼ぶ
設備に関して本当に問題があって、何とか解決しないと行けなければ、機電系エンジニアに頼るのではなくメーカーに頼ることになります。
設備故障時の修理が典型例です。
故障はしていないけど、運転能力が出ていないという場合、化学工学の知識を持った機電系エンジニアが最初は対応します。
それでもダメならメーカーを呼びます。
この瞬間に、化学工学の知識が機電系エンジニアにとって必要か、少し疑問になります。
しかし安心してください。
メーカーも似たような状況の可能性が高いです。
メーカーに聞けば解決できるという期待が以前はありましたが、今ではその期待感は凄く少なくなっています。
結局は解決できなかったという場合が多いです。
メーカーの技術者はその設備に関しては、機械的にも電気的にも化学工学的にも一定の知識があるはずです。
その人でも無理であれば、広く浅く知識が求められるユーザー側では太刀打ちできないでしょう。
化学工学の知識を持った機電系エンジニアが、メーカーに質問しても

分かりません。
と冷たく回答されることの方が多いです。
この「分かりません」と丸投げ放棄される光景は、製造が機電系エンジニアに対して日常的に感じていることでしょう。
参考
関連記事
最後に
機電系エンジニアにとって、化学工学の知識は「必須」ではありませんが、「持っておくと有利」な知識です。特に、設備選定やトラブル対応、化学系との連携場面では、その理解がスムーズな業務遂行に役立ちます。
ただし、全てを理解する必要はなく、「必要なときに調べて対応できる」姿勢こそが最も重要です。
化学工学に苦手意識を持たず、機電系ならではの視点で貢献していきましょう。
化学工学の知識は機電系エンジニアに必要と言われますが、実はあまり必要なかったりします。本当に最低限の部分だけ知識として持っていればよくて、後は周りの人と協議調整さえできれば済んでしまいます。
勉強して知識や経験を高めていくことは素晴らしいことですが、それができなくても機電系エンジニアとして活躍できるようにしていきたいです。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
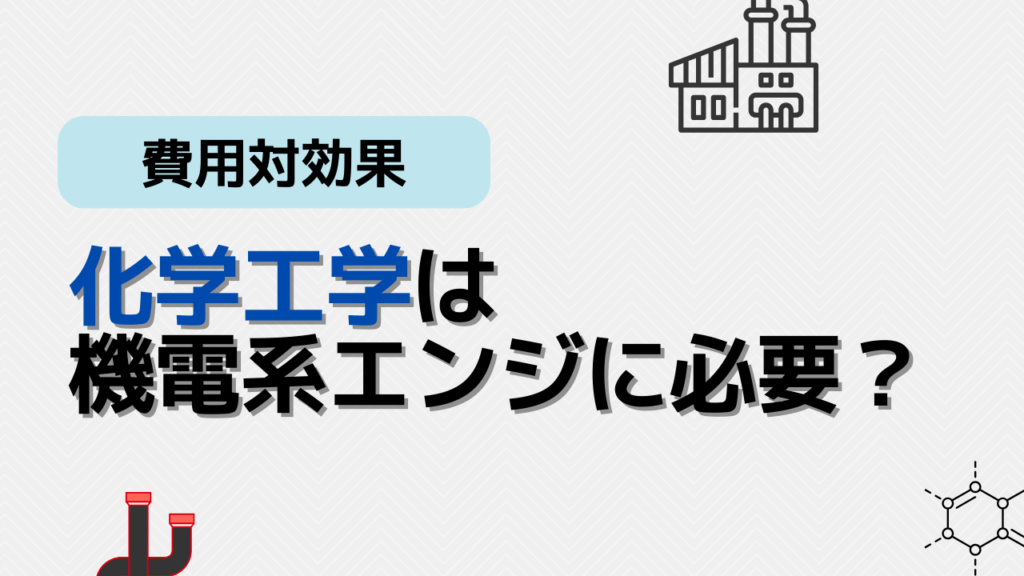

コメント