化学プラントの機電系エンジニアは、高額な設備投資を扱う専門職です。設計から施工、発注まで幅広い業務に関わる中で、企業から与えられる「予算」の管理は大きな責務の一つです。
しかし、日々このサイクルを繰り返す中で、**予算に対する感覚が“バグる”**エンジニアも少なくありません。
「予算は与えられたら使い切るもの」「削減努力はある一定までで十分」──このような考えにとらわれた結果、社内でも浮いた存在になったり、無意識のうちにコストセンター化してしまうことも。
本記事では、そんな「予算感覚のバグ」に陥りやすいエンジニアの特徴や背景、そしてそこから抜け出すための視点を掘り下げます。
与えられた予算を使い切る
予算は与えられたら使うもの。
この考え方は決して間違ってはいません。ここには理由があります。
予算化を行うためには、機電系エンジニア目線ではかなり叩かれているように見えます。
- 予算着工までにとにかく削減案を求められる
- プラントの長期安定化のための投資ができない
- そもそも予算申請会議に参加できない
こういう環境に居ると、与えられた数字になるように予算案を練ることが最大の使命となってしまいます。
設備内容や配管ルートなどを考えるにも限界があり、一定の削減効果まで出し切ってしまうと、それ以上は考えられなくなります。しかし、外部からはそれがデフォルトだと認識されてしまいます。
デフォルト状態が徐々に削減方向に向かい、これ以上はどうしようもなくなる。
こうして思考が硬直化していしまいます。
実はほかにできることがあったとしても、思いつかなかったり相談しなかったりして、一定の額以上の努力をしようとしなくなります。
予算を越えなければそれ以上の努力しない
もらった予算は自分たちの管理範囲で、周りから束縛されたくないという想いを持ってしまいます。
これが、予算を余らせるという努力をさせなくなってしまいます。
もらった予算は手放さない
予算化を叩かれば叩かれるほど、もらった予算は手放さないという思考になります。
例えば、1,000万円の予算が降りた場合、1,000万円を越えないように努力します。
結果的に980万円くらいで工事が終わりそうであれば、それで十分だろうと思ってしまいます。
ところが設計段階でしっかり考えれば900万円になる可能性が見えていました。
それでも980万円で終わるなら予算内だから十分だろう、と900万円の可能性を潰してしまいます。
これがコスト意識として明確に現れます。
工場全体を見れる人は実はいない
予算とその運用方法は会社によって違いますが、余った金額は別の投資にある程度自由に割り当てができる場合、予算を余らせることは大きな意味があります。
予算化の段階で、プラント全体で必要な投資を俯瞰して優先順位を決めるということはできていないでしょう。
ここだけは何とかしないとまずい。
これくらいの緊急度が高い部分にだけ着目してしまいます。
その周りには小さな金額でも効果のある投資がいっぱいあったとしても、目を向けません。
一度もらった予算で余った部分は、そういう小金で出来る対応に投資できる可能性があります。
その重要性は工場全体では把握しにくく、機電系エンジニアの方が知っている部分があります。
そこに投資したら機電系エンジニア自身が楽になるかも知れないのに、放棄。
結果的に周りの部署からは、何も努力しようとしない、と思われてしまいます。
見積を甘めに、実務は思考停止
物価の高騰化のために、予算を余らせようとしても足りないという事情の方が強く出てしまいます。
この状況が続くと、見積を甘めにしようという思考が出てしまいます。
とにかくお金を確保したうえで、実行段階で努力して金額を削減したい。
この思いであれば、反対する人はいません。
しかし実際には、甘めの見積で予算化してもお金が足りない、という結果になりがち。
- 甘めの見積をしたときの前提条件を1つでも説明できない
- 予算が足りなくなった理由を1つでも説明できない
- 高騰した費用の内訳を1つでも説明できない
こんな感じで、予算管理に対する責任を1つずつ放棄していき、コストセンターとなっていきます。
実行段階で努力しようとせず、時間がないから見積段階の仕様で発注という感じになっていきます。
時間が無いというのは色々な理由があり、設計者の技能不足・製造課などとの調整部職・無駄な時間の使い方・・・などです。
エンジニアにとってこういうマネジメント力はとても大事です。
小さなプロジェクトほど注意
予算に対する意識は大きな建設プロジェクトよりは、小さなプロジェクトの方が遥かに大事です。
大きなプロジェクトだとアサインされる人も多く、予算管理を専門で実施する人も居ます。都度報告も求められるでしょう。
しかし、小さなプロジェクトでは担当者任せ。
コスト意識のないエンジニアが、もらった予算を使い切り、工場全体で必要な投資が十分にカバーできない。
長期間予算が割り当てらない部分がどんどん目立っていき、予算が膨れ上がってしまう。
こういう結果になっていきます。
コスト意識を持たないと、プラントの長期運営・保全に大きな影響が出てしまいます。機電系エンジニアにとってコスト意識は重要です。
参考
関連記事
最後に
化学プラントの機電系エンジニアが扱う予算は、単なる“使うためのお金”ではなく、企業全体の設備戦略を支える重要な資源です。
・使い切ることに固執して削減の余地を見逃す
・甘い見積りで根拠を欠いた予算化をする
・再投資の可能性を考えず、自部署の都合だけで運用する
こうした行動は、最終的に信頼の損失と“コストセンター化”という悪循環を引き起こします。
今こそ、エンジニアとしての予算意識を見直し、「本当に必要な設備投資とは何か」を問い直す時です。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
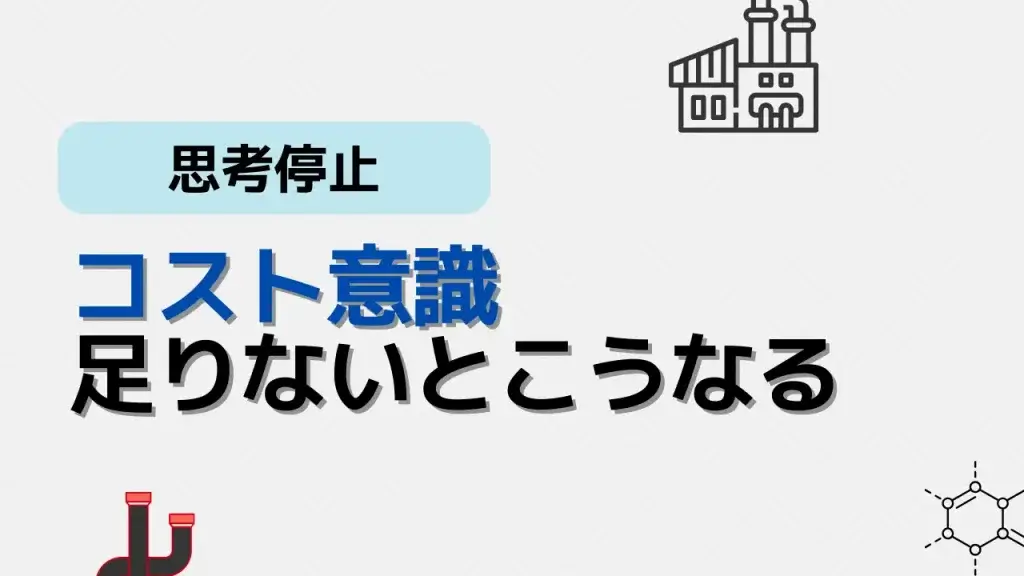

コメント