化学プラントのエンジニアなら設備投資に対して敏感であるべきです。工事コストについては年々上がり続け話題になっているでしょう。
設備そのものよりも工事コストの方が高いくらいです。
ラング係数も上昇し続けています。
ここで工事コストの中身や背景を少し掘り下げておいた方が、エンジニアリングにいい結果を及ぼします、

単価高騰は日々チェックしよう!!
この記事は、オーナーズエンジニアシリーズの一部です。
プロジェクト予算における労務費の考え方:オーナーズエンジニア視点から
オーナーズエンジニアとして働く前に知っておくべきリスクと対策
「実は知らないことだらけ」オーナーズエンジニアの設計業務の実態とは? ―丸投げ・不安・誤解…増改築プロジェクトの裏側
オーナーズエンジニア必見!プラント建設で費用を抑える検討手法まとめ
オーナーズエンジニアの設備設計は将来性があるか?
オーナーズエンジニアの仕事はゼネコンと関わる前後でどう変わる?
工事会社とオーナーズエンジニア、良い関係を保つためのポイント
オーナーズエンジニア必見!化学プラント予算管理の実践ガイド
保全こそが化学プラントのオーナーズエンジニアで生き残る
立会検査を最速で終わらせるコツ|オーナーズエンジニア向け
化学プラントのオーナーズエンジニア業務の実態例
オーナーエンジニアが現場で実践すべき配管工事の品質管理手法
工事コストの内訳
工事コストは労務費+資材費で大きく分割することができます。
公共工事設計単価
化学プラントの工事単価を設計するうえで以下の資料が基礎資料となります。
国土交通省の「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」
毎年3月に公開されています。
建設業を中心としたデータですが、化学プラントの建設工事にも類推できる資料です。
平均労務単価
まずは全体像を見てみましょう。
平均労務単価の情報が最も分かりやすい。
簡潔に言うと、1997年から2012年までは労務単価が減少し、2013年以降は増加し続けている。
公共工事の減少や東日本大震災の特需などが背景にありますが、少子高齢化や3K作業という要因もあります。
世間一般の感覚からするとごく当たり前の展開ですが、社内の環境に染まっているとこの辺の感覚が全くないまま長年時が過ぎ去ります。
労務単価は過去30年全く変わっていない!考える価値などない!
なんて豪語する人もいるくらいです。世間知らずもここまで来ると病的です。
職種ごと単価
職種ごと単価は興味がある分野だけチェックすれば良いでしょう。
機械屋なら配管工よりも溶接工が高いという当たり前の情報がデータとして見れます。
電気計装屋なら配線工の単価が分かります。
宿主ごとの違いを見比べると、技術的な難易度や有資格者の人数など推測することが可能です。
こういう情報は、社内の非エンジニアリング部門へのアピールとしては最適な情報です。
エンジニアリングの人は、日常的に施工会社とやり取りしているので知っていて当然という世界。
金額原単位
資材の単価は金額原単位という表現をしています。
化学屋にとっては分かりやすい表現ですが、機械屋にとっては違和感があるでしょうか。
- 資材単価 : 単位重量当たりの金額
- 金額原単位 : 単位金額で製造できる重量
重量と金額が逆数になっています。
原単位は製造原価の分野で使いますね。
金額原単位は建設資材に対して表現されています。
セメント・コンクリート・石材・鋼材などです。
鋼材が化学プラントでは関連性があるでしょう。
現在は4つの材料いずれも金額が高騰しています。区別する必要はないでしょう。
これも労務費と同じく人手不足が理由の1つです。分かりやすいです。
原料単価や輸送費などを理由にしても良いですが、人手不足の方が社内的にはアピールしやすいです。
資材費は目立たない
さて、この資材費ですが高騰しても化学プラントではあまり目立ちません。
というのも、工事費という意味では資材費よりも労務費の方が割合が高いからです。
工事費=労務費+資材費と考えた時に、
労務費 : 資材費 = 4 : 1くらいが、化学プラントでは一般的でしょう。
ペトロケミカルとファインケミカルとで多少の差はあり、ペトロの方が資材費が高いイメージです。
いずれにしろ、労務費の方がファクターが強いために資材費が少し上がったところで目立ちません。
設計上の注意点
高騰する工事コストを抑えるためにユーザーができることを見ていきましょう。
まずは設計段階から。
レイアウト
レイアウトとは設備の配置をイメージしてください。
レイアウトを運転員の作業性として捉えている人もいます。
私も昔はそうでした。
運転員が楽になるように、レイアウトを考えなさい。
そう指導されました。
これも正しいのですが、その側面だけでなくて工事コストにも大きく影響するという事を理解しておく方が良いでしょう。
配管長さ
レイアウトは配管長さに直結します。
合理的に考えたレイアウトとは、配管の長さも最適化されています。
配管長さはそのまま工事金額に直結します。
配管工事は普通、配管長さ × 単価で決まるはずです。
この配管長さを削減するために、設計者はレイアウトを試行錯誤しなければいけません。
超重要です。
配管材質
材質は、配管工事である 配管長さ × 単価の単価に効きます。
こちらは逆に変更できる可能性があまり高くありません。
特に、鉄やステンレスなどの汎用材質では、検討をしてもメリットはでません。
材質に付いて考えるとすれば、耐食性の高い材質についてでしょう。
耐食性の高い材質として何を選ぶかということは、色々な人が考えるため、単に機械設計屋が指定できる要素はあまりありません。
バッチ系ならPTFEライニングやFRPなどに限定されると思います。
配管口径
配管口径は配管工事である配管長さ × 単価の単価に効きます。
これは機械設計屋が努力できる部分です。
配管中の圧力損失を考慮して最適な光景を選べるのは、機械設計屋だけです。
特に、ユーティリティ配管は大口径のために努力代が大きいです。
特殊な加工品
特殊な加工品とは下記のようなイメージです。
- 手仕込み作業がある箇所の、作業架台や安全対策
- 手仕込み作業がある箇所の、作業環境を整える衛生対策
- 製品切替作業がある箇所の、配管レイアウト
これも機械屋が知恵を絞れる箇所です。
これらの要素は、設計段階でどこまで作りこめるか?という世界になります。
- 実運転を知らず図面しか知らないエンジニア
- 実運転は知っているが図面は知らない運転員
交わることはありません。
一度作った後で、運転員から駄目と言われて作り直すことも。
作った後で判断せざるを得ないので、二重投資になります。
二重投資を削減するために作業内容を徹底的に吟味して、一発で作り上げると製作コストは最小化できますが、バランス感覚が大事。
二重投資を避けるために費やした設計時間がコストを圧迫する要因になるからです。
エンジニアは長年設計品質に拘り過ぎていて期限を切るという発想が低い傾向にあるので、コスト感覚を持つのは難しいかも知れませんね。
工事上の注意点
設計段階と同じく工事段階でできることを見ていきましょう。
工事準備期間を長く
発注から工事期間まで時間が取れれば取れるほど安くなります。
工事準備期間と呼びます。
これは露骨に影響します。
設計期間を長く取ると工事準備期間が短くなり、工事コストが上がります。
なぜかというと、良質な作業員を確保するために多くの資金を準備しなければいけないから。
コンビナート地域など作業員が多く確保できそうなら気にしなくてもいかも知れませんが、地方の製造会社なら敏感に反応する部分です。
設計者も十分に理解しておきたいところですね。
施工期間を長く
施工期間を長くするほど、工事コストは下がります。
工事準備期間と同じく作業員の確保の問題。
でもこれはエンジニアだけが決めれるものではありません。
生産計画の都合があるからです。
生産計画がシビアなので、工事はこの期間でやって欲しい。
こんな問い合わせはよくあります。
でもエンジニアはここで諦めてはいけません。
短い期間で施工はできるがコストは上がります。
ここを明確に主張しましょう。
何も言わずに受け入れてしまうと、何でもできると思い込まれますよ。
一括発注
発注を一括でできる方が当然安いです。
ネゴが効く可能性があるからです。
でもこれを過信してはいけません。
分割発注をしてでも主要部分だけを先に発注して工事準備期間を確保する方が安くなる場合もあります。
発注のネゴと工事準備期間が工事コストに影響がでているという関係性はエンジニアなら理解しておきましょう。
参考
最後に
化学プラントの工事コストと削減する工夫について解説しました。
労務費と資材費に分けて考え、設計段階では物量が影響し工事段階では発注時期と発注回数が影響します。
労務費と資材費ともに上がっています。特に労務費は上がり続けています。
肉体労働への敬遠の影響が特に強いです。
基本原則を抑えたうえで、バランスを持った業務をしていきましょう。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
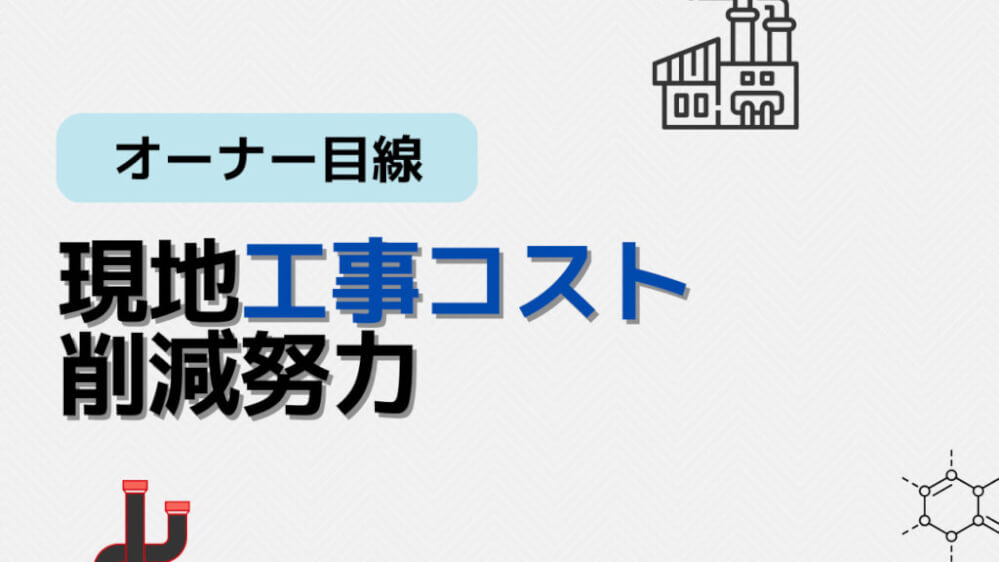

コメント
お世話になります、いつも拝見させていただいております。
労務費(エンジニアリングフィー)は、オーナーズエンジの場合はあまり関係ないと思いますが、どの項目にどれくらい見込まれますか?
(社内事業部をまたいで仕事をする場合、人件費をどの製造部門から捻出するかで話題になることがありました)
機械工事であれば、(購入品+工事費)×20~30%=労務費 として換算することが多いと思いますが、いかがでしょうか?
知見ございましたら、ご教示いただけると幸いです。
労務費割合については、割合で出すほどの実績データを私は持っていません。
エンジニアリングフィーとしては各業種の合計値×20~30%は妥当かやや低いくらいの数字だと思います。
プラントエンジ会社に委託する場合はフィーとして外だししますが、内部でエンジニアリングをする場合、
費用を予算に盛り込むのは難しいと思います。関係なくはないのですが、ブラックボックス化されている印象です。
労務費は(プロジェクトの期間×人数)で効いてきますが、人数はプロジェクト規模に線形比例するわけでなく、階段上に影響が出るはずです。
10億円~15億円が10人でも、15億円で15人に急に上がるなどのイメージです。
(購入費+工事費)は、金属系の多い連続プラントとグラスライニングが多いバッチプラントでは差が出てくるので、データの蓄積が必要となります。
事業部間を跨ぐという件ですが、会社としてのエンジニアの人数と投資総額が毎年ほぼ一律であるなら、その中のパイをどの事業部に振り分けるかという話で
考えると良いように思います。上記の通り業界によって(購入費+工事費)は変わってくるので、事業部間で不公平が出る原因ともなります。
各投資案件にたいして個別に必要な工数を積み上げて、工数総額から按分することも考えられなくはないですが、作業が煩雑になるはずです。
それなら、もっと分かりやすい総額ベースで捻出を考えるくらいではないでしょうか?