近年、化学プラントの機電系エンジニアにおけるマンツーマン指導の機会が著しく減少しています。従来は製造課など現場での直接指導が成長の重要な柱でしたが、社内の年齢構成の偏りや新卒採用の減少、従業員の意識変化により、この貴重な教育機会が減っています。
本記事では、なぜマンツーマン指導が減少しているのか、その背景と課題を掘り下げ、今後のエンジニア教育における問題点を考察します。
この記事は、機電系エンジニア性質シリーズの一部です。
【妄想】AIで化学工場の機電系エンジニアリングがこう変わって欲しい
化学工場×データサイエンス:機電系エンジニアが直面する“現場とのギャップ”とは?
化学プラントの機電系エンジニアはどう評価されている?現場・本社・製造のリアルな視線
プラント建設が減る中で、機電系エンジニアに求められる力とは
2024年版ものづくり白書を読む:プラント機電系エンジニアの視点から
化学プラントの機電系エンジニアが陥る“予算感覚のバグ”:コスト意識の再構築が必要な理由
競争相手が少ない化学プラント機電系エンジニア
機電系エンジニアの内面にあるこだわりと外から見た印象の違い
専門性が高すぎる?化学会社の機電系エンジニアのジョブローテーションと職場環境の実態
設計と保全の違いと連携の重要性──化学プラントの機電系エンジニア視点
機電系エンジニアの業務実態:化学工場での典型的な1日の流れ
「化学工学の知識、機電系エンジニアに本当に必要?」—現場での実情を探る
視野の狭さを克服する!機電系エンジニアが知るべき標準化・パターン化のポイント
機電系エンジニアの狭い範囲で時代に残されないためにできること
転職で化学プラントに来た機電系エンジニアのキャリアルート3パターン
技術力が徐々に低下している|化学プラントの機電系エンジニア
働かないおじさんの典型3パターン|化学プラントの機電系エンジニア
視野が狭い化学プラントの機電系エンジニアが気を付けたいこと
なぜ機電系エンジニアは受け身になるのか?──若手・中堅・マネージャー全員に共通する“意識の低下”
機電系エンジニアが“抱え込み”やすい本当の理由──思考のクセと成長機会の損失
院卒・大卒・高卒まで幅広く機電系学生を歓迎する化学プラントの実情
図面と数値だけじゃ足りない!言語化ができる機電系エンジニアになる方法
化学プラントの職種別「1日の流れ」:機電系エンジニア・保全・製造部のリアルな時間感覚
機電系エンジニアの事務仕事実態:パソコン苦手がもたらす現場の課題
機電系エンジニアが化学プラントで直面する「分からない」11の壁とその乗り越え方
言語化で差をつける化学プラント機電系エンジニアの仕事術:設備情報・使い方・工事・運転を徹底解説
年齢構成がいびつ
教えることができない職場環境の1つに、年齢構成がいびつであることが挙げられます。
レベル差がそこそこ
誰かに教える・教わるというのは、レベル差がそれなりという条件が付きます。
経験・知識に差がありすぎると、専門家でない限り教えるときに相当の課題を抱えます。
教える側が相当の調整をしないといけないからですね。
それができる人も居れば、できない人も居る。
その前提を置くと、レベル差がそこそこの関係であることはとても大事です。(会社で新卒が求められる理由の1つですね)
少子高齢化
年齢構成がいびつになる理由の1つは、少子高齢化です。
若手とベテラン層の人数構成が均一でない職場は多いでしょう。
本来は教える側に立つべきベテランや中堅の層の一定数が、若手に教える機会がなく年を経過してしまいます。
新卒が少なく転職が多い
一部のエンジニアリングは不人気のため、新卒希望者が少なく転職者が多くなります。
新卒者に対して教えるというのと、転職者に対して教えるというのでは、教える側の成長という意味では大きく違います。
新卒者に対しては、説明している本人が分からないところがありながら説明して、分からない部分があれば一緒に考えるという寄り添った教育ができます。
しかし、転職者は知らないことがあって教わったとしても、バックグラウンドから補正して理解できてしまいます。
教育する側が悩む機会が少なくなってしまいます。
新卒から転職を主体にした採用に切り替えていかざるを得ない機電系エンジニアリングでは、その場しのぎをせざるを得ない状況です。
従業員の意識
教える機会が少ない職場では、従業員の意識の問題があります。
聞くことが怖い
聞くことが怖いと考える人が増えていると言われます。
昔からそうです。
それでも聞くか、聞かないかの違いが、今と昔ではあります。
聞かないでもなんとかなってしまうと考えてしまうのか、責任感の問題なのか、とにかく分からないことを聞かない職場があることは確かです。
調べればすべてが分かる
調べればすべてが分かる、という思い込みを持っている人が多いです。
何もマニュアルがない、もしくは陳腐化している組織は問題ですが、マニュアルがあっても見ない人が増えています。
どこに何があるか分からない→だから調べない
という不思議。
ここに資料があるからと説明しても、短い時間で忘れてしまったりします。
調べたことが全てと考えて、実務に対して汎用的に成立すると思い込んだりします。
エンジニアリングの仕事って無機質に当てはめるだけの仕事ではない、という事実に目を背けて・・・。
教育資料の拡充に頼る
マンツーマンで教えることが、時間的にも精神的にも難しくなっている現状、教育資料の拡充が叫ばれています。
マニュアル作成のソフトっていっぱい出ていますよね。
これで最低限の部分を習得してもらおうとする教育をする側と、これですべてが解決すると思っている教育を受ける側との高い壁ができあがっていきます。
教育を受ける側から見ると、「会社が教育資料を作るのは当然だ」と思うかも知れません。
でも、甘えていると危険なことになりかねませんよ。
その資料が誰に対するものなのか、教育する側はしっかり考えています。
サイロ思考の加速
教える機会が少なく、成長がしにくくなると、その組織は守備範囲を狭くしていきます。
他部門と調整する接点部分を、他部署に依頼していきます。
教える機会がなく、教えるべき人が少なく、資料を拡充していけばいくほど、「これくらいの仕事でいい」と自分の仕事を勝手に再定義します。
こういうサイロ思考は、目の前で困っている人が即時解決するには効果があります。
しかし長期的には不利になります。
仕事の本質を見て、不要な物は切り捨てる、本来の仕事に特化する、仕事の付加価値を作っていく、というアプローチができなくなっていくでしょう。
私の職場で将来起こりえる確率が高いことだと思っています。
参考
関連記事
最後に
マンツーマン指導の減少は化学プラントの機電系エンジニア教育に深刻な影響を与えています。年齢構成の偏りや採用の変化、従業員の意識といった複数の要因が絡み合い、組織の技術力維持と成長を難しくしています。教育資料の整備だけに頼るのではなく、組織全体で教える文化を再構築することが急務です。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
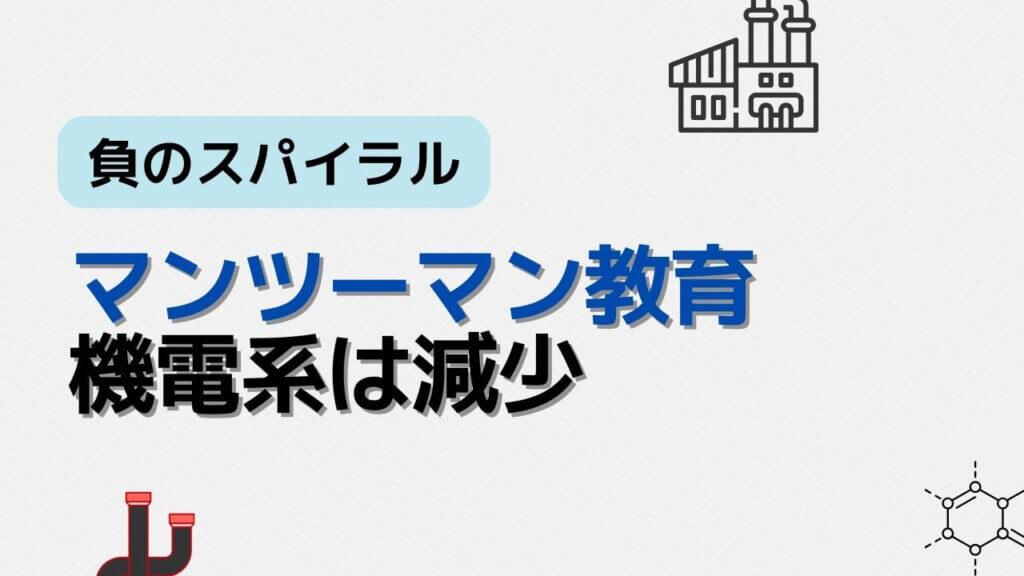

コメント