化学設備業界では、かつてのような熟練技術者による安定した設計・製造体制が崩れつつあります。とくに中小の化学設備メーカーにおける人材不足と、OJT(On the Job Training)頼みの技術継承の限界が顕著に現れており、図面の品質低下や、設計ミスによる納期遅延、トラブルの多発など深刻な問題が日常的に発生しています。
この記事では、現場のリアルな声を通じて、化学設備メーカーの技術力が低下する背景とその影響を掘り下げます。
年々変わっていく環境変化に対して、2021年当時どんな環境であるかの記録として残したいと思いっています。昔から似たような傾向はあったのでしょうが、言語化されず伝承もされていないですからね。
この記事は、設備メーカーシリーズの一部です。
GLメーカーってこんな感じ?私の正直なイメージ
化学プラントで感じる“面倒なメーカー対応”の実態とは
エンジニアと設備メーカーがお互いに歩み寄ると効率化が進みます
フッ素樹脂ライニング製マグネットポンプのメーカー比較:設計と保全で選ぶ最適解とは?
新規設備メーカー採用のポイント|製缶機器を中心とした技術確認の進め方
設備トラブルの原因対策についてメーカーと打ち合わせするときの落としどころ
化学プラントにも起こりうる“対応の遅い設備メーカー”の3大問題とは?
製缶(タンク・熱交換器)のメーカー見積に対するユーザー査定
小さな設備メーカーは製図ができない
機電系エンジニア目線で設備メーカーの技術力を測るとき、製図能力が最も分かりやすい形で現れます。
人がいない
設備メーカーの製図能力は、人手不足の影響を非常に強く受けています。もっと簡単に言うとCADオペレータがいません。
昔は5人くらいいたけど、今は1人いるかいないか。
こんな話は、どこの中小メーカーからも聞きます。
そもそも5人で製図を回そうとしていたこと自体が無理がありそうなのに、1人いるかいないかの世界って希少価値すぎます。それでも図面を書かないといけないのが設備メーカーの痛いところ。標準的な仕様はなく受注生産でカスタム設計をせざるを得ないですから。
人がいないなら外部に委託します。ここで問題が。
外部の人は社内の設備に詳しいとは限らないです。
例えば製缶メーカーが製図をできる人を探そうとしても、マッチする人がいなくて組立系の製図ができる人に依頼する場合もあるでしょう。
製缶の製図ができるとしても、ユーザーとの取り決めで暗黙の内に決まっている内容を理解していない場合もあります。これが図面のやり取りのロスが起こります。
設備に詳しくない
人がいないということと、ほぼ同義ですが社内の製図者が自社の製造設備のことを知らないという実態があります。これは特に中小の製缶メーカーで露骨にみられます。
先の例では、5人いた製図者が1人になって、何とか1人雇って2人になった。この2人目が技術を持っている可能性です。
まずありえません。
特に中小企業の製図者として募集があったとしても、給料が少ないはず。それなら大手企業で募集を掛けている所なんて山のようにあります。中小企業が人を育てる場合、OJTしかないでしょう。現場を見て盗むという世界が未だにあるはずです。
机上で図面を作っても現場ではNGが出てしまいます。
メーカーの図面作成者が対応できないから、ユーザーにメーカー現場から直接確認依頼が来るという謎なケースも出てきています。
窓口である営業の価値が全否定されていますね。こんな環境で一人前に現場も製図もできるようになるには、5年10年と膨大な時間がかかります。その人が5年も残るのか?昔ながらの変わらない現場の要求にこたえようとする若い人がどれだけいるのでしょうか?嫌になって辞める人が続出して、長続きしません。
製図のルールを雑に扱う
製図はJISでちゃんとルールが決まっています。最初に図面の勉強をする時は、このルールの多さや自由度の低さに戸惑うことでしょう。
みんなそうです。
でもそれを社内でちゃんとチェックしてユーザーに提出するからこそ、ユーザー目線では一定の品質の図面を毎回見ることができます。それが機能しなくなって「ルールとはちょっと違う雑な図面」を見た時、ユーザーは不安に思います。
- 寸法が引き出し線と重なって見えにくい
- 無意味に過剰なハッチングを掛ける
- 寸法補助線の引き出し元が分かりにくい
- 組立図と部品図の整合性が取れていない
- BOMの数量が明らかにおかしい
- フォントサイズが小さくて見えない
典型的に発見するのは4と5です。
客先照会用の図面と自社制作用の図面を兼ねるときに、図面の整合性が整っていない状態で提出するがゆえに出てくる問題です。ユーザーとしては、メーカーの責任で見るべき範囲だと突っぱねることも可能です。
でも結果的に時間がかかります。意匠図としての承認をした後、いざ作り始めたら問題が出ます。
慌てたメーカーは図面の修正をしてユーザーに確認依頼をして、即日の承認を求めようとバタバタします。ユーザーはそれに対応していたらメーカーに振り回される形になります。
1社だけを対応しているならいいのですが、ユーザーとしてはそういう案件を10~20くらい並行処理します。その1社だけに振り回されるわけではありません。だからこそ、図面はしっかり見ておかざるを得ません。
設備メーカーは技術開発ができない
設備メーカーで新技術を開発することは、ほぼ望めないでしょう。これはメーカーの営業担当の来訪機会の減少という形でよく現れます。メーカーのHPを良くチェックしても、昔と変わってないことに気が付くでしょう。
展示会に行っても分かります。アピールするときはできるだけ広く大きく見せようとしますが、実態は非常に怪しいです。
ハステロイ・チタン・タンタル何でも制作できます!ってアピールしておいて、いざチタンをお願いしようとしたら、納期が異常に掛かったり単価が異常に高かったり。それを知っているメーカーはそもそも見積を辞退しようとすらします。
そういう時にアピール内容と違いますよねって言ったら、必ずこう言います。
「すみません」
業界・人を見抜く力がエンジニアには求められます。
報告書作成は後回し
メーカーでも製作とメンテナンスで対応が少し違います。製作は図面の問題としてよく見えますが、メンテナンスは修理したら終わりという風潮がとても強いです。報告書・見解書を求めようものなら絶望的。ユーザー目線では、メンテナンスが終わった後の速報として書類を求めたいところです。
これについては当日の議事録のコピーが限界です。綺麗にパソコンで清書しようものなら。。。
入力だけでも時間がかかり、上司の承認に時間がかかり、その間に他の緊急メンテナンスに対応しないといけない。そうして忘れ去られます。ユーザーもここは考え直さないといけません。
報告書を作るという作業はメーカーとしてはとても高度なスキルが要求されるものだ、と。
見方を変えましょう。報告書を作る依頼をしても、ユーザーはその仕事の進捗管理ができるでしょうか。1週間前に報告書を依頼して、1週間経ったことに気を配る余裕があるでしょうか。
他の仕事で忙殺されているはずです。
もしくはタスク管理をしっかり行っていないはず。
自身でタスク管理すらできていないのに、相手も同じようにタスク管理ができていると思うのはちょっと違うでしょう。
メーカーに丸投げ依頼しているから、責任はメーカーにあるはずだ。
という思考だけでは現実は付いてきません。
メーカーの対応が遅れて、痛い目を見るのはユーザーです。
品質
メーカーはすべてが品質がなし崩し的な印象を覚えます。製造業なら4M(man・machine・material・method)という単語を耳にしたこともあるでしょう。大手会社ならこの変更管理の重要性を理解して実践もしています。
ところが、中小企業のユーザーになると意識は途端に薄くなります。設備メーカーならほぼ意識はないと言って良いでしょう。
man
設備メーカー目線でmanというと、新工場などが話題になります。manとは人のこと。4Mは製造品質を担保するための4つの要素で、人が品質を決める要素となります。
具体的には、サービスの品質を作りこむ技能があることを認定する制度を取っているでしょう。製造なら技能認定試験や抜き取り検査でチェック可能です。設計は日常業務で問題を起こしているかどうかで定性的に判定するでしょう。
1つの事業所で長年行っている業務なら、人の入れ替わりのたびに認定をして一定の品質を保とうとします。ところが新工場ができた場合は、その条件が途端に怪しくなります。特に海外工場を建設した場合や海外に製作を委託した場合。
品質管理部門の担当者が海外の実力チェックと保証をするために駆け回ることになります。ユーザーもそれくらいは想像が付きます。
ところが、これを営業が理解してないケースが多いです。メーカー営業がユーザーに対して「○○製品は海外で作ることになりました!よろしく!」というような言い方で決定事項だけを後出しで説明する場合を見かけます。
それが品質を担保できているかどうか、という説明があってしかるべき。でも営業にそのことを説明しても、「何言っているのだろう?」って顔をする人が本当に居ます。若手・ベテラン関係なくです。
製造業の営業であることを認識していないのか、そんなことに気を回せないのか・・・。品質保証の人と話すと通じるので、営業の技術力低下という方が正しい気がします。
machine
machineは製作設備と製作物の両方が考えられます。でもここはあまりターゲットになりません。設備は旧型を使い倒し、製作物は新技術が開発されないから。
method
methodもあまりターゲットになりません。新技術の開発に繋がらないからですね。
material
materialは製作物の材質そのものなのであまり話題には上がらないでしょう。金属系は特に変われないです。
SUS304やSUS316LのNi含量が年々下がって許容値限界になっているのはミルシートを見ると分かります。高分子材料の材質の添加剤が実は変わっていたというケースが厄介で、メーカーでもトレースできていない例が見られます。
将来
化学工場向けの設備メーカーの展望は明るくないどころかとても暗いと思っています。
安さを求めて汎用的な設備は、中小の製缶会社に依頼することが多いでしょうが、そのうち会社が少なくなっていきます。
会社を立ち上げた社長が60歳どころか70歳を越えて、趣味の世界で何とかやりくりしていて、跡継ぎを探しても集まらない。
こうやって店を畳むことに。
50歳や60歳前半で跡継ぎをしっかり考えれば良かったのに、もう少し頑張れる・・・と先延ばしにした結果、跡継ぎを育てられなかった。
こういう企業さんをよく見かけます。
そうなると、大手会社との吸収合併が進むでしょう。
多種多様な設備仕様に対して設計製作が満足にできるほどの人材を確保できないでしょうから、大手会社での設計の統一化は進みます。
汎用的なタンクですら、ユーザーのこだわりを反映できないメーカー標準での購買が進んでいくと思います。
参考
最後に
化学設備メーカーにおける人材不足とOJT任せの技術継承は、製図品質の低下、技術開発力の停滞、そして報告体制の乱れなど、あらゆる面で業界の信頼性を揺るがしています。とくに中小メーカーでは、現場の努力だけでは限界があり、ユーザー・メーカー双方の視点から抜本的な改善が求められます。技術の空洞化が進む今こそ、次世代へ向けた仕組みづくりと意識改革が必要です。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
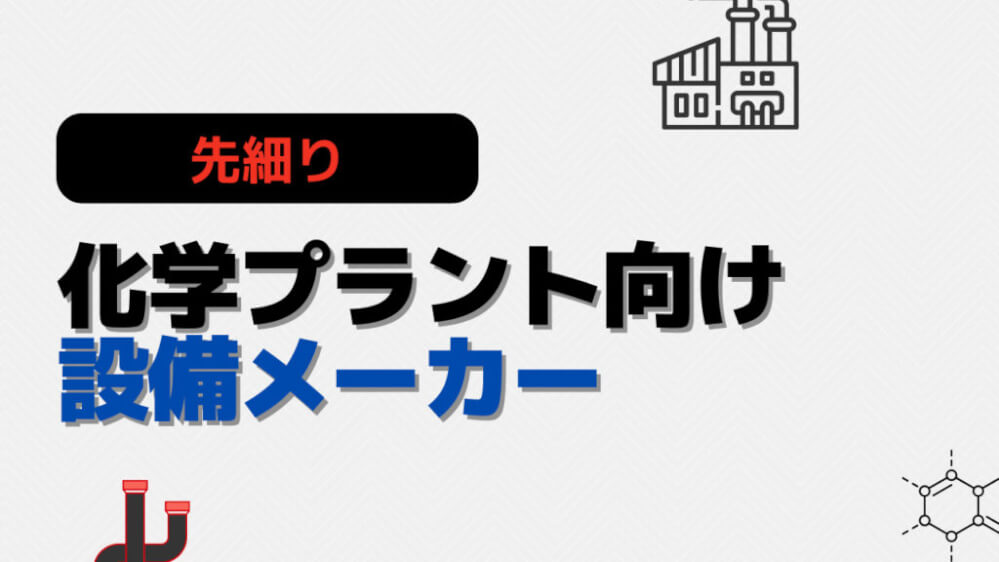

コメント