プラントエンジニアの中核を担う「機械」「電気」「計装」「土建」の4職種。しかし、多くの現場ではこれらの職種が足並みを揃えて協力することが難しく、連携不足によるさまざまな問題が発生しています。
なぜこの4職種はバラバラになりがちなのか、その背景と現状を整理し、組織を強化するために必要なポイントを探ってみましょう。
調整業務の大切さを理解して評価してくれる人が居ないと、組織がまとまりません。会社で給料もらっているから…というのは実は通用しません。学校の部活やサークルの方が、よっぽど一致団結しています。
プラントエンジニアの4大職種(機械・電気・計装・土建)
まず今回取り上げる4職種の特徴を紹介します。
機械・電気・計装・土建の4職種が、それぞれ別の部署として独立して仕事しています。
例えば電気と計装を合わせて電計というよう場合には、少し事情が異なるでしょう。
大きな組織だと設計と保全の機能を分けますが、小さいと設計と保全は同じ部署に統合されています。
設計と保全については部署が同じであろうが別であろうが、情報溶融は活発にはされていないでしょう。
机の配置はJTCによくある島型で、各職種で同じフロアに居ても島は当然違うという状況。
窓際には管理職がいて、プレイングマネージャーが多いような環境。
オーナーエンジニアが前提
こういう状況を想定しています。
強烈なマネジメント不足
4職種の足並みが揃わない理由の1つは、マネジメント不足です。
まとめ役の部長や相当する課長がしっかりしていないと、バラバラに動き始めます。
というのも、課長レベルでは自分の組織を何とかしようという部下のマネジメントに力を置きがちだからです。
昨今は特にその割合が強いです。
ところが、課長としては会社や工場レベルなどの広い視点を持ちながら、課の運営もしないといけません。
- 会社のことを考えずに、部下だけを見ていたら仕事が進まない
- 部下のことを考えずに、会社のことを考えると部下が持たない
極端な例ですが、どちらかのパターンが多いです。
特に1で放置している場合の方が圧倒機に多いと、私の身の回りでは感じています。
部長の場合は、会社からは強いプレッシャーを受けていても、部下には伝えないというケースが多いように見えています。
言葉通りのサンドバック状態ですが、課長側としては運営方針を認識する機会が少なく自分で何とかしようとしてしまいます。
役割がはっきりし過ぎている
4職種がそれなりに機能して、一定の期間を経過すると、自分の役割を固定化しようとします。

機械はここまでが機械、後は他の職種で良く分からない!
この思考が強くなってくると、以下の単語が飛び交うようになります。
機械屋・電気屋・計装屋・土建屋
仕事の内容が変わらず、区分がはっきりしていて、そこだけに注力できる環境ならこれでも良いでしょう。
ただし、プラントの多くの設備でこの区分を明確にしている人はおそらく居ないでしょう。
私は電気と計装の区分が良く悩みます。
電圧の違い(使用電力の違い)である程度は判断できますが、どっちも電気を使っているから良く分からないと混乱している人もいます。
成長速度が遅い
昨今のエンジニアは成長速度が遅いと思います。
この遅さが足並みをバラバラにさせる要因になります。
成長速度が遅い → 自職種の理解で精いっぱい → 他職種の仕事を知ろうとしない → 成長が一定でストップ
負のサイクルを繰り返している感じ。
速度が遅いという言い方をしていますが、成長を望んでいない・昇進を望んでいないという表現でも近いと思います。
仲良くなる機会が少ない
職種間で仲良くなる機会が少なくなっています。
仕事上の接点部分での話し合いをする人もいますが、その量は確実に減っています。
コミュニケーションはメールが多くて、雑談の機会が減っています。
さらにプライベートでの接点も減っていて、個々人の好みや癖を知る機会も減っています。
この状態で足並みが揃う方が変ですね。
足並みが揃わないことで起こること
4大職種の足並みが揃わない条件は結構はっきりしています。
その結果、どういうことが起こるでしょうか?
誰かがカバーしている
足並みが揃わない状態であっても、目的の成果を上げるためには誰かがカバーしています。
どの職種がカバーしているかは会社によって違うでしょう。
化学プラントのエンジニアリングの場合、守備範囲の一番大きい機械がカバーしてそうなイメージです。
いつまで持つかという話になりますが、危ないとなった時には結局は応援などでカバーできなくなっています。
ツケはマネージャー層が負うことになりますね。
会議時間が増える
足並みを揃えるためには、会議は重要です。
特に対面での会議。
A職種の人は自分の殻に籠っていて、B職種の人がA職種のことも気にかけるような発言をしたら、A職種の人は何かしら考えるはずです。
こういうリアルタイムの反応があるのが会議の場。
オンラインではその辺はちょっと弱いですね。
会議の個数が増えるので、残業時間は増えていく方向でしょう。
妥協が増える
足並みが揃わないと、依頼部門である製造部門は妥協をしていきます。
オーナーエンジニアだからといって、何でも依頼を聞いてくれるわけでない。
多少のことなら昨今の流れで仕方ないと思いますが、行き過ぎると結構な問題に繋がります。
関連記事
さらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
最後に
プラントエンジニアの機械・電気・計装・土建の4職種が足並みを揃えられない背景には、強力なマネジメント不足、役割固定化、成長の鈍化、コミュニケーション不足という構造的な問題があります。このままでは業務効率低下や残業増加、品質低下などのリスクが高まります。
組織としてこれらの課題を認識し、職種間の対話促進や調整役の強化などの施策が求められています。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
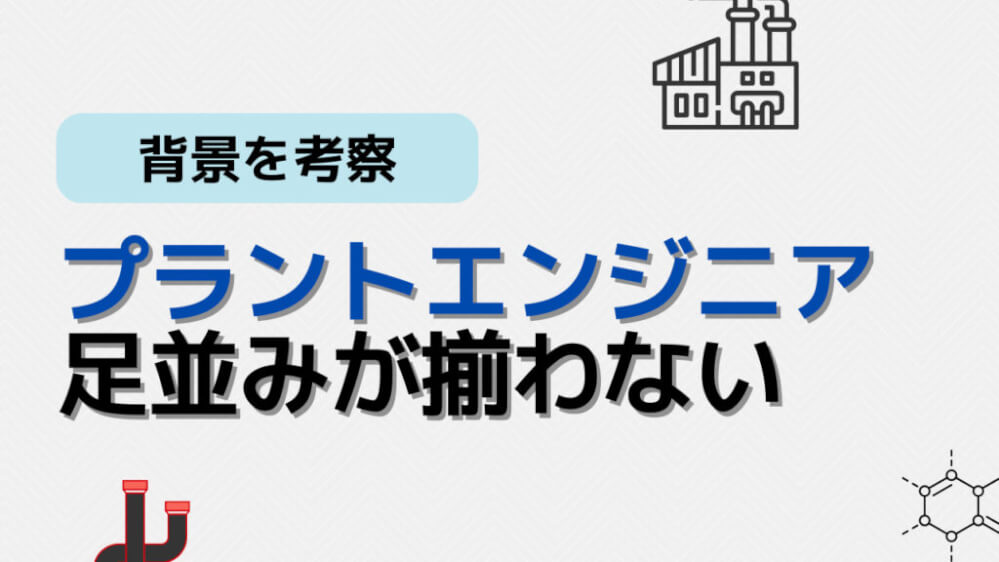
コメント