保全業務において「計画」はすべての出発点です。特にプラント設備の保全では、最初に立てる計画の質がその後の点検・修理・管理すべてに影響を与えます。PDCAサイクルの「P(計画)」が曖昧であれば、その後の「D(実行)」「C(評価)」「A(改善)」も意味をなしません。
本記事では、設備保全の計画立案において何から始め、どこまで見積もるべきかを、実務経験に基づいたステップで解説します。初心者でも実践できるよう、情報の精度と工数のバランスを意識した内容にまとめています。
この手順通りにしっかり保全計画ができていれば、論理的になるでしょう。反対をするのはとても難しくなるはずです。(これに反対意見を出しても、結果はあまり良いとは思えません)
難しさは量と精度にあります。
この記事は、保全計画シリーズの一部です。
【設備保全入門】MTBF・MTTR・稼働率とは?意味・計算式・使い方を解説!
プラント設備の保全計画を見直す障害となる思考
Excelで設備保全初心者を卒業!一人前になるためのステップ
プラント設備保全の長期計画の基本的な考え方
RCM(Reliability centered maintenance)の化学プラントでの考え方
建設中に決まるメンテナンス性!設計で差が出るプラントの寿命
機器をすべてリストアップ
保全計画の最初のステップは、とにかく機器を全部リストアップすることです。
現場で配置図やP&IDを見ながら照合して、基本資料を100%に仕上げます。
設備という点ではそんなに多くないので、1人のエンジニアが担当するレベルでは、半日程度で情報が収集できるでしょう。
その代わり少し体力勝負になります。
ここを雑に扱ってしまうと、以降のすべてが狂います。
現物と基礎資料の照合が大事
このデータをエクセルなどで台帳化しましょう。
配置図やP&IDから転記が必要になるので、ここでも抜けがあると以降のすべてが狂います。
基礎資料と台帳の照合が大事
通常修理に必要なデータの収集
無事に設備をリストアップ出来たら、以下の2つの情報を整理しましょう。
通常の修理に必要な金額
金額とは修理に掛かる費用のことです。
こういう情報の合計値を、ある程度丸めて算出します。
部品費用5万円+修理工数10万円+移動費7万円 = 22万円 → 30万円
なぜ丸めるかというと、個々の設備に細かく設定する意味がないからです。
例えば、ポンプAで22万円で、ポンプBで25万円だとしましょう。
ポンプAとポンプBの違いは設備の種類・設置位置などいくつかの要素があります。
これを全部パターン化して金額を振り分けると、ポンプ1つでも10パターンくらいできるでしょう。
担当する設備はポンプ以外にも、複数の種類があるはずです。
これを緻密に仕訳けていたら、情報収集だけでも時間がいくらあっても足りません。
許容される範囲で丸めましょう。
設備点数にもよりますがこれを妥協しないなら、上手く保全できません。
通常の修理に必要な日数
修理に掛かる日数を整理します。
これも金額と同じである程度妥協しましょう。
これくらいのオーダーで考えましょう。
数日を2日・3日・4日と細かく分けていたら、キリがありません。
1日以内で終わりそうなら1日、1日を越えそうなら数日、数日だと不安なら1週間・・・
というように余裕をある程度見ましょう。
価格高騰と同じで、部品の長納期化やSVの多忙化など、日数ベースでも予測しにくい事項があります。
ここを細かく見積もるのは、費用対効果が悪いです。
修理しないときのリスク
修理を前提とした保全のデータを作り上げていくと、予算を管理する部門からこういう質問が来ます。

そんな高い金出せるわけないでしょょ
こういう時には、修理しないリスクを整理しておきましょう。
応急修理に必要な金額
応急修理に必要な金額を見積もりましょう。
夜間や休日なら手当として設定しますが、日常でも多少の上乗せをしておいた方が無難です。
故障が起こる頻度
修理しないで放置していると、いつかは壊れます。
どれくらいの頻度で壊れるかの見積をしますが、オーダーは以下のような感じで良いでしょう。
これは保全を経験している人なら、体感的に理解しています。
多少の誤差があっても許容されるはずなので、頻度を数字で見えるようにしましょう。
応急修理に必要な日数
修理に掛かる日数を見積もります。
通常修理に必要な日数より、余裕を持ちましょう。
作業員が手配できるか、部品が手に入るか、という部分でリスクがあるからです。
この日数は生産日数の縮小に直結します。
「通常修理費 < 応急修理費」が当然
通常修理の費用より応急修理の費用の方が高いはずです。
体感的に分かっていても、数値で示している人はあまり居ないでしょう。
ある程度丸めた数字で考えないと、パターンが多すぎて整理が難しいでしょう。
上記の金額・日程・頻度などの情報を提示すれば、トータルで考えない会社は無いと信じています。
気合で何とかするものだ!という思考停止をしている会社は、ちょっと危ないと思います。
予備機の情報
応急修理費を削減するために、予備機を準備しておくことが考えられます。
金額
予備機を準備するにはお金が発生します。
故障の頻度や掛かるコストを考えたときに、予備機を準備する方が良いというパターンは十分に考えられます。
| 対応 | 金額 | 頻度 |
| 補修 | 50万 | 1年に1回 |
| 交換 | 100万 | BM |
例えば、補修を1年に1回、50万円で毎年続けている設備があるとしましょう。
そういうものだと思考停止してずっと続けられてしまいがち。
ところが部品交換は1回100万円で済むとしましょう。
設備の様子を見ながら壊れるまで補修を続け、壊れてから部品を交換するというBM的な対応をしていると、補修に掛かる費用がトータルで不利になってしまうかも知れません。
部品の補修と交換のどちらがいいかは、運転状況・設備の調達難易度・補修の対応難易度などいくつかの要素をトータルで考えまますが、基本は金額と頻度です。
ここで大きな方向性を先に決めてから、詳細を詰めましょう。
日数
据付予備ならほぼノーリスクですが、格納予備になると応急補修と同じ考え方が必要になります。
格納予備のメリットは、長納期部品のリスク回避です。
生産機会を損失する可能性がゼロではないので、1日や数日など数値で出せるようにしましょう。
参考
関連記事
最後に
保全計画は、現場を支える最も根幹となる業務です。以下のポイントを押さえることで、精度の高い、説得力ある計画を立案できます:
- 設備情報の網羅的なリストアップ
- 修理に関する金額・日数の適切な見積もり
- 修理を怠った場合のリスクと影響の見える化
- 予備機の有無とその妥当性評価
数字で示せる計画は、現場の理解と協力を得やすく、計画全体の実行性と説得力を高めます。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
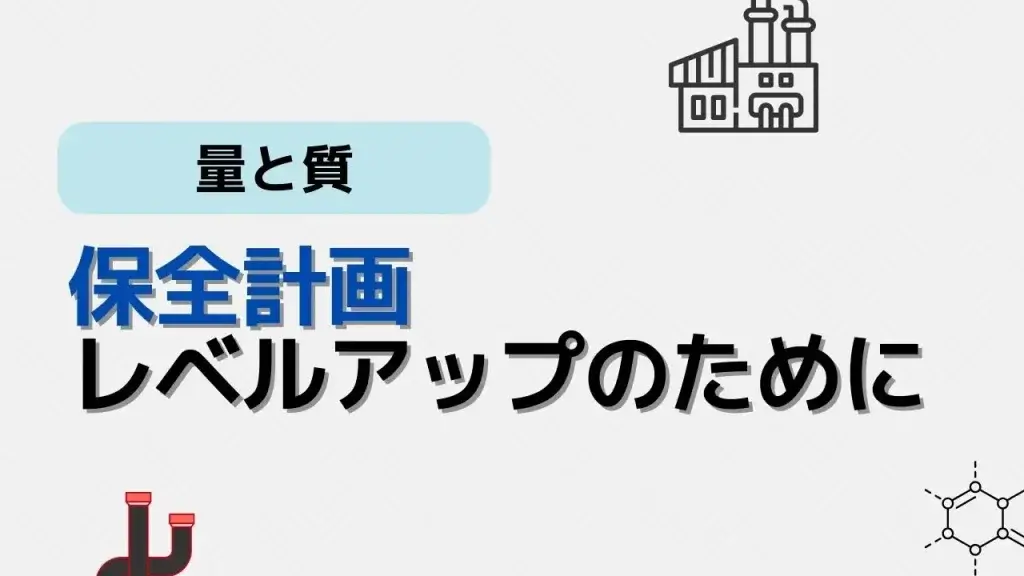

コメント