 電気設計
電気設計 UPSが化学プラントの電気関係でよく使われる理由
整流装置・インバータ・蓄電池からなるシステムで原理的には割と単純です。
 電気設計
電気設計 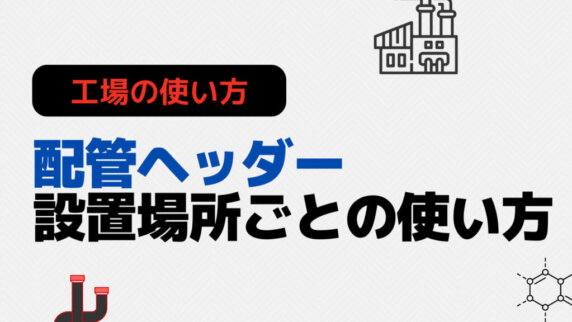 配管
配管 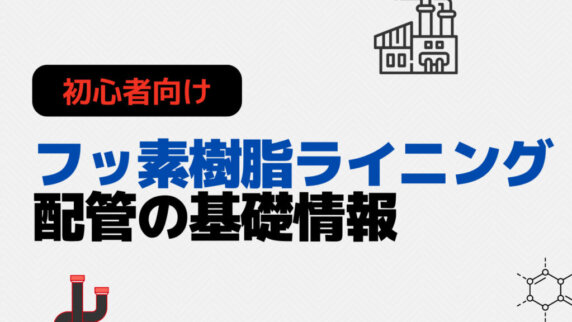 配管
配管  配管
配管 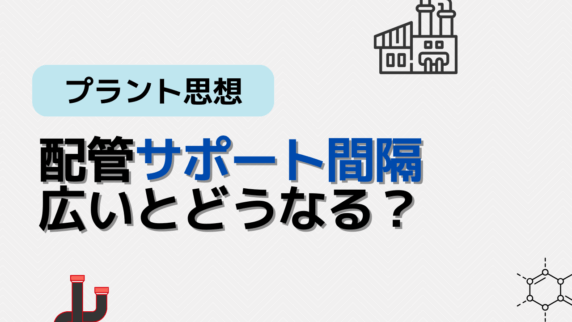 配管
配管 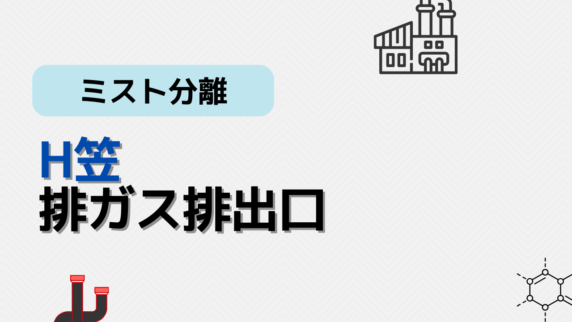 配管
配管 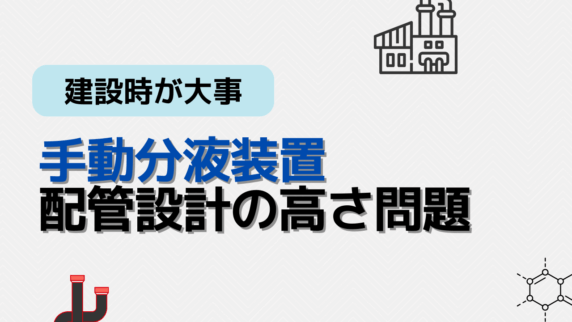 配管
配管 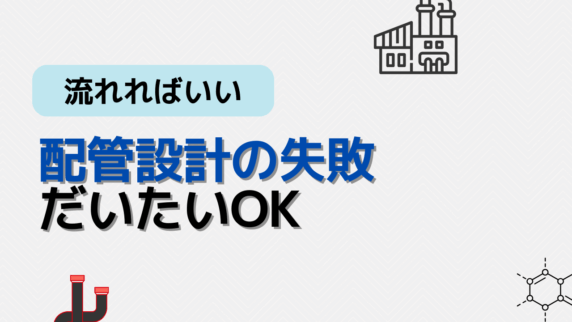 配管
配管 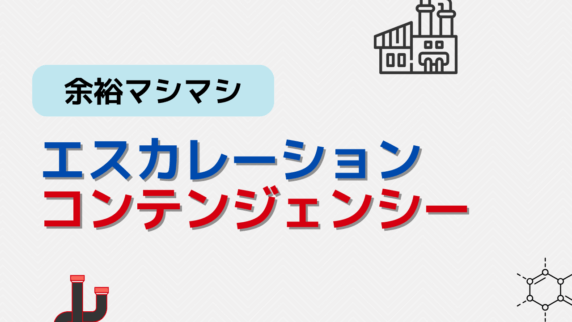 プロジェクト
プロジェクト  プロジェクト
プロジェクト