化学プラントの設備はここ20年でほとんど変わっていないと言われます。私自身も入社以来、新技術の導入は限られており、防爆規制がその大きな壁となっています。しかし一方で、事務作業や設計、教育の現場ではITやDXの浸透により大きな変化がありました。
この記事では、化学プラントの設備から設計、教育に至るまで、この20年間で何が変わり、何が変わっていないのかを振り返ります。

事業環境
化学業界としては、20年で結構な変化がありました。
- 石油化学業界の縮小
- 電子機器需要の増加
- 半導体需要の増加
- 医薬需要の増加
プラントエンジニアレベルでも、特定の業界に長いこと関わっているとある程度の変化は見えてくるでしょう。
一般的に知られている情報でも上の変化が認められます。
特に半導体や医薬はこれからますます伸びるでしょう。
期待したいですね。
意志決定の遅延
エンジニア目線では投資判断の遅さにとても不満を持っています。
これは20年で半年~1年くらい遅くなった印象を持っています。
昔なら投資判断が速くて着工から工事まで2年掛けていたものが、今では投資判断が遅いために1年半や1年に短縮せざるを得ないという格好です。
高ランクのプロジェクトよりも、低ランクのプロジェクトほどしわ寄せが行っています。
コストアップ
20年でプラントに関わるコストは明らかに上がっています。
工事上のコストは労務費や資材費という背景から避けられません。
同じプラントを使い続けると、メンテナンスコストも増えます。
原料も当然コストアップ。
競争力を持たせるためには人を減らすしか手がないという状態。
コスト面だけでなく安全やミス防止の面からも自動化は進めざるを得ないでしょう。
プラント設備
化学プラントは20年で思ったほど変化がありません。
新たな設備を導入することが難しいからです。
ほぼ全ては防爆の規制によるもの。
設備的に変化があったものをリストアップしましょう。
キーワードは防爆・自動・静電気くらいでしょう。
世間的にはITなど技術開発が進んでいますが、化学プラントでは岩盤規制が非常に硬く導入がとても遅れています。
それでも少しずつでも導入をしようという動きが出ています。
リストの内容は、私が何とか思いついたものであってこれ以上思い出そうとしてもなかなか難しいです。
数多くの装置を導入しているプラントでありながら、20年でたった10個以下程度の技術しか導入されていない。
これが化学プラントが変わっていないと言われる所以でしょう。
規制に嫌気が指して生産中止品が出てくるのも納得します。
事務作業
事務作業もこの20年で大きく変わりました。
パソコンが1人1台
20年前というとパソコンが1人1台ですらなかった時代です。
当時でも大学の研究室では1人1台が基本でしたが、会社では数台しか置いていなかったところもあるでしょう。
弊社も当時の座席配置を見てみてもそれが伺えます。
ノートパソコンですらなかったでしょうね・・・。
そう考えると大きな進歩
OHPの廃止
20年前というと発表はOHPを使っていたでしょう。
トランスペアレンシーの世界です。死語ですね。
PowerPointって素晴らしい発明だったわけですね。
プロジェクターが導入され、パソコンと有線で繋ぐということが基本となりました。
今でも絶滅はしていませんが、結構減っていますね。
wifiの導入
社内のLANが構築されて、wifiも飛ばすようになってきたと思います。
これは大きな革命。
- パソコンを会議室に持ち込むことが可能
- プロジェクターへの接続が無線で可能
無駄な会議でも出席しないといけないが、その間に内職ができるようになったことは大きいでしょう。
テレワーク
テレワーク化も20年でちょっとずつですが進んています。
技術系や工場系はまだまだ難しいですが、本社など事務系はかなりテレワークができるようになりました。
20年前では考えられなかったこと。
働き方改革やコロナなどもあって、とても大事な発想です。
設計
プラント設計関係で変化したことをまとめました。
製図テーブルが無くなった
設計事務所には昔は大型の製図テーブルがありました。
ドラフターという方が分かりやすいでしょう。
私が入社したときにも、事務所に数台設置されていました。
昔は個人ごとに設置されていたのでしょう。
この20年で、紙の図面を使用する機会が激減したために、製図テーブルも撤去されました。
後半は単なる物置台くらいにしか使われていませんでした…
時代の移り変わりを感じますね。。
図面テンプレートが無くなった
図面テンプレートとは〇・△・□などを手書きするためのひな形です。
これも入社当時は配布されていましたが、私は数回しか使ったことがありません。
というのも、手書きで正式図を書く機会がなくなったからです。
- 正式図作成前の概念図であれば手書きでOK
- 正式図はCADで書けばOK
この考え方が普及したからです。
紙でデータを保管するデメリットから、紙で資料を発行する必要性がなくなってきたのですね。
今でも、A1やもっと大きなサイズの紙の図面は残っていますが、
1年に1回使えば良いくらい。
10年間以上見向きもされない図面も山のようにあります。
三角スケールが無くなった
三角スケールというと、三角定規と勘違いされる方もいるでしょう。
断面形状が三角形で、6種類の縮尺が付いている定規です。
これも使う機会は減りました。
紙の図面の縮尺を、定規で読み取るという方法を取る機会が減ったからです。
過去の図面は電子データ化されたからですね。
CADで計測する方が、よっぽと早く確実です。
私も、三角スケールは保有していますが、ノートパソコンを傾ける道具としてしか使っていません。
キーボードが机と少し角度が付いている方が、入力しやすいですからね ^ ^
どうでもいいことですが、コンベックススケールは現役で使用しますね。設計者にとって現場の必須アイテム
図面の電子化が増えた
図面の電子化は設計でも大きな変化ではないでしょうか。
昔は図面のやり取りは「郵送」が基本でした。
紙の図面に朱記をしてやりとりをし、不明点は電話で確認する。
非効率でしょう。
今ではPDF化してメールでやり取りが簡単にできます。
それでも2020年ごろまでは紙の図面にこだわるメーカーもいましたが、ほぼ絶滅してきましたね。
図面システムという名の管理システムを導入してる会社も多いでしょう。
Excel計算ソフトが増えた
この20年くらいで、設計計算ソフトが増えました。
ソフトと言ってもすごく単純なものです。
- 化学工学で使う四則計算を自動計算する
- 多くのデータを使った計算をリスト化して統合する
- グラフから読み取るデータを近似式を使って自動計算する(圧力容器の構造計算など)
昔はExcelなんて無かったので、紙の設計書に文献の計算式を各スタイルが多いです。
学校の勉強や試験そのものです。
今ではExcelを使わない計算なんて考えられないレベルですね。
手書き図面が作れない
電子化が進んだ弊害として、今のオーナーエンジニアは手書きの図面を作ることが極端に苦手です。
Excelで作ろうものなら、かなり怪しい図面ばかり。
オートシェイプの基本サイズから線種・線の太さ・色など全く変えずに外形図を書くだけ。
図面ではなくてイメージ図。
製図のルールを学校で習わなかったのかと疑問になるレベル。
細かさという意味で大事な部分ですが、それがすっぽり抜け落ちてしまっています。
保全
保全もこの20年で大きく変わりました。
保全データの蓄積
保全上は電子データの積み上げを行っているでしょう。
電子データで管理するようになって、過去の履歴を追いかけたり複数の設備の情報を比較したりと便利になりました。
データ保全が進みました。
一匹狼で独自の思想だけで行う保全は、これからますます減っていくでしょう。
保全方式の確立
この20年で保全方式を確立していった会社も増えたのではないでしょうか?
弊部ではTBM・CBM・BMという表現を20年前は、日常業務ではほとんど使っていませんでした。
ある機器が故障した時に、「機器名称」とセットで「製作年」や「保全方式」はあってしかるべきもの。
これが20年前は普通に「機器名称」だけでした。
保全方式を定めていても、保全計画と予算取りのためだけに使われていたということでうs。
在庫管理
設備が故障したときのことを考えて在庫をどうしようか意識する機会もこの20年で増えました。
- 在庫はチームで管理するもの
- 安定操業のための在庫管理が大事
- 在庫保管場所が少なくなっている
一匹狼の保全はやはり好ましいものではありません。
個人の力は限定的です。
情報の分断は好ましくありません。
設備の技術開発はこれ以上望めません。
ということはチームでの管理を目指すしか手がありません。
本体予備も予備部品も適切な管理をすることが、今後の重要なスキルの1つになっていくでしょう。
教育
教育もいつの間にか大きく変わっています。
2000年代の教育
私が新入社員のころの教育を振り返りましょう。
- 上司の机の前で報連相
- 基本的に放置
- 口頭での説明のみ
- 部下から報告するもの
2000年代の教育って基本は放置でした。
良く言うと「部下の自主性を重んじる」、悪く言うと「忙しくて面倒が見られない」。
これで良かったわけです。
右も左も分からない新入社員は、上司に聞く時間が取れずネットの情報も不足していたので、いろいろ考えながら情報収集や設計をしていました。
- 文献を読み漁る
- 周囲の人にヒアリングをする
- とにかく現場に通う
今の若手はこの辺の手段を考えることが全くなく、いきなりネットで検索。
検索でヒットしなければ他を探そうとしない。
これくらいで終わってしまいます。
機械エンジニアに指導するときも、絶対に口頭だけの説明でした。
これは言語化能力を高める上で役に立つことは確かです。
でも入社したばかりで、知識がない時に口頭ってかなりきついです。
上司は黙って部下の報告を待っていればOKでした。
それでも普通に進みました。
2020年代の教育
2000年代の教育は、教育とはいいがたいモノでした。
さて、時代は変わって2020年代はどうでしょうか。
- 会議室で報連相
- 上司から進捗を聞きに行く
- 上司が絵を書いて説明
部下の報連相を机の前で聞くことは基本的にしません。
説教などが入る要素があるため、会議室など周りの人が聞かない場所を作り出さないといけません。
これだけでも面倒な作業。
部下から定期報告なんて上がってこないのが普通です。
上司が部下に情報を聞き出しにいかないといけません。
手遅れになっても部下は責任を取ろうと焦りもしません。
報告を聞こうとしなかった上司が悪いというスタンスです。
2020年現在の20代に特徴的ですが、30代でも結構います。
口頭だけの説明で理解できる人も減ったので、絵を書いて説明しないといけません。
部下が自分の理解度を示すために絵を書いてくれればいいのに、それは絶対にしません。
書くのは上司側。
手を動かさず、情報を検索し受け取って、横流し。
これでスキルなんて身に付くのかな?と疑問はあります。
最後に
化学プラントの設備は20年でほとんど変わっていませんが、防爆規制という壁の中で少しずつ自動化や安全技術が導入されています。事務作業や設計、保全、教育の分野ではITやDXの進展に伴い大きな変革がありました。
これらの変化を理解し、今後のプラント運営や技術継承に活かすことが重要です。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
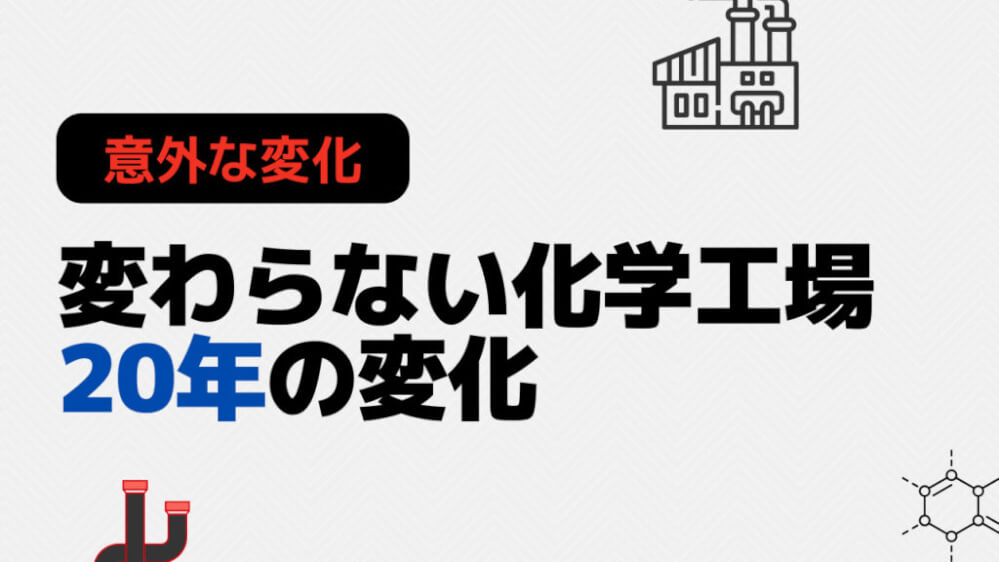

コメント