設備保全の長期計画について解説します。
プラント建設をした瞬間から、プラント廃棄の時までずっと保全は続きます。保全を最初にしっかり計画することは、工場運営にとって非常に大事。
計画をしっかり立てて、予定通りに予算化ができて交換ができるプラントは超理想的です。実際には定期検査をしてそろそろ寿命かな?って思ってから予算化をしようとして、予算が降りずにジリ貧になることが多いでしょう。
設備の長期計画を練るには、設備に関するあらゆる知識が求められます。その考え方の基本的な部分を紹介します。
この記事は、保全計画シリーズの一部です。
プラント設備の保全計画を見直す障害となる思考
Excelで設備保全初心者を卒業!一人前になるためのステップ
【設備保全入門】MTBF・MTTR・稼働率とは?意味・計算式・使い方を解説!
RCM(Reliability centered maintenance)の化学プラントでの考え方
保全エンジニア必見|計画立案で失敗しないための基本フロー
建設中に決まるメンテナンス性!設計で差が出るプラントの寿命
点検内容の決定
本記事では渦巻ポンプの保全を考えます。まずは、渦巻ポンプで点検すべきことをリストアップしましょう。ヒントは動く部分です。
- メカニカルシール
- モーター
- ベアリング
- インペラ
インペラを点検部品に設定しない場合は、もちろんあります。例えば清浄な水なら、インペラが摩耗したり腐食したりする可能性は、極めて低いですから。
今回はインペラも、点検内容に含めておきましょう。
点検周期の設定
これらの部品の点検周期を決めます。点検周期と言いつつ、実際にはほぼ交換周期に相当します。というのも、例えばメカニカルシールやベアリングは点検のために分解したら、再利用できないからです。
| 部品 | 点検周期 | 交換周期 |
| メカニカルシール | 4年 | 4年 |
| モーター | 4年 | 4年 |
| ベアリング | 4年 | 4年 |
| インペラ | 4年 | 10年 |
簡単に、4年に1回はポンプの分解をして点検をするというプランにします。交換部品もインペラを除いてすべて4年。4年に1回の分解で、自ずとインペラもチェックしていることになります。インペラだけは、分解してもただ清掃するだけで、設置20年後でやっと交換するという考えにします。
費用の算出
それぞれの保全に掛かる費用を見積もります。おおよその金額で以下のような感じに決めていきます。
| 部品 | 費用 | 交換周期 | 条件 |
| メカニカルシール | 20万年 | 4年 | A |
| モーター | 20万円 | 4年 | A |
| ベアリング | 10万円 | 4年 | A |
| インペラ | 30万円 | 10年 | B |
ここまでは単に積み上げるだけ。保全計画が複雑になるのは、この辺りからです。
本来なら、4年で分解交換するというなら、TBMが4年の機器という設定になります。インペラを交換しない計画であれば、まさに成立します。この場合は、TBMが4年で1回あたり50万円の保全費用が必要、という計画が立てられます。これがパターンAの保全としましょう。
一方で、インペラを交換するのはTBMが10年で1回あたり30万円の保全費用が必要、という計画になります。これをパターンBの保全としましょう。
2パターンある瞬間に保全計画がややこしくなります。そこで、保全の計画の場合は、星取表という形でリスト化していきます。
例えば以下のような感じです。
| 年度 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 費用 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 条件 | – | – | – | A | – | – | – | A | – | B | – | A | – | – |
22年度にポンプを設置して、4年目の26年度にパターンAの保全をします。8年目の30年度も同じです。10年目の32年度にはパターンBの保全が入ってきます。
具体的な実施時期の決定
1つの設備に対して計画を立てたら終了、というわけにはいきません。膨大な数の設備に対して、同じような計画を立てることになります。
例えば渦巻ポンプだけで年間500万円しか保全に割り当てができない、と仮定しましょう。上記の保全計画を単純に積み上げていくと、もしかしたら以下のような感じになるかもしれません。
| 年度 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 費用 | 500 | 450 | 550 | 500 | 400 | 600 | 500 | 500 | 500 | 530 | 450 | 580 | 500 | 600 |
24年度や25年度を見てみると、それぞれ500万円とは異なる費用です。平均するとどちらも500万円ですね。こういう場合は、25年度の計画の一部を前に倒して実施します。同じように27年度と28年度も変えます。
全体の保全計画ができるだけ平均化されるように、保全する設備の優先順位を少し操作します。これで基本的な計画が完成します。
延命処置
保全計画を立てたら、そのまま長期間無機質に計画に従って実行すればいいかというと、そうもいきません。上の保全計画の例でも34年度くらいから、平均500万円を上回る予想が実は立っています。
| 年度 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 費用 | 500 | 450 | 550 | 500 | 400 | 600 | 500 | 500 | 500 | 530 | 450 | 580 | 500 | 600 |
費用の高騰はいくつかの理由が考えられます。
- 材料や工数が高騰している
- 設備が劣化して点検周期を短くしないといけない
設備の後期には保全費用を増やさないといけません。人間と全く同じこと。
しかし、設置年度とTBMの年数だけで立てた計画では、この辺りが完全にスルーされます。後期の保全計画と更新タイミングを適切に設定できる人は、保全の超エリートだと私は思います。それくらい、実施している人は少ないです。
そもそも人間と違って、設備は数が少ないので各段階での保全費用のデータ蓄積が難しいですからね。設備の数量と金額の大小によって、難易度は大きく異なります。バッチ系化学プラントのように、設備の数が多い場合は特に難しいでしょう。
参考
関連記事
さらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
最後に
プラント設備保全の長期計画の立て方を解説しました。
点検部品のリスト化と費用の積み上げ・周期の設定は基礎中の基礎。
その年に割り当てられる予算に対して、実施する設備のピックアップをして計画確定。
後期の設備に対するフォローまでできると、保全の超エリートです。
化学プラントの保全などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
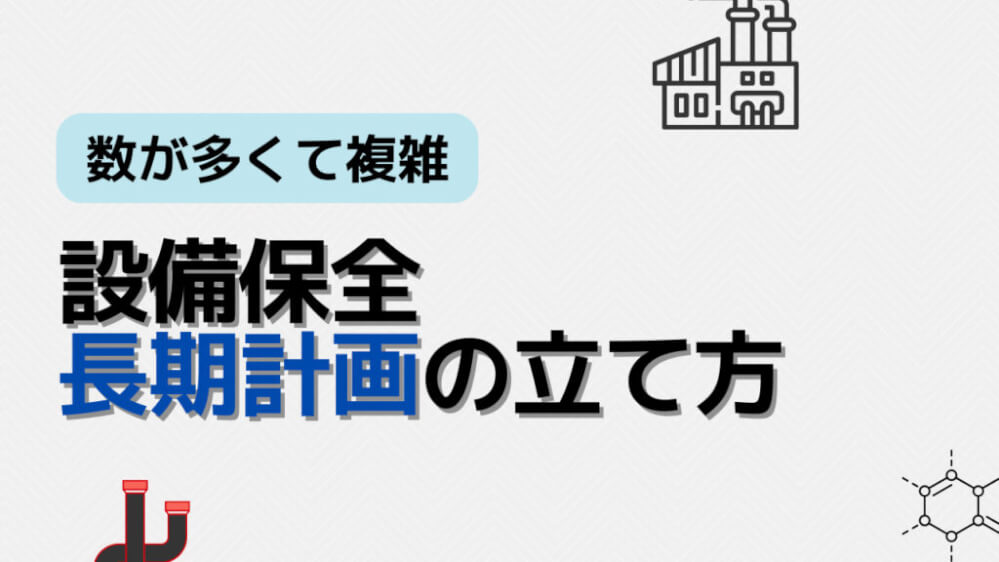

コメント