エネルギー管理士(熱分野)について、化学プラントの機械系エンジニアが受験する前に準備しておくことをまとめます。
エネルギー管理士の試験は、化学プラントのエンジニア的にはかなり高レベルの資格です。
入社してすぐに受験するのはハードルが高いです。
試験科目と実務との関係を主に解説して、先に受験しておく方が良い資格も解説します。
慌てずにしっかり対策しましょう。
試験科目と実務の関係
エネルギー管理士の熱分野の試験科目について解説します。
エネルギー総合管理及び法規
エネルギー総合管理及び法規は、いわゆる法律とか概論の部分です。
資格試験では法律は避けて通れません。
ほぼ暗記になるので、一夜漬けは止めておいた方が良いでしょう。
毎日少しずつ触れて、記憶に定着させましょう。
概論はしっかり理解したいです。
資格試験で学んだ内容のほとんどは実務では使いません。
設備管理系の資格でよくある計算問題とか設備の構造とかは、実務で担当しない確率の方が高いでしょう。
最終的に使う可能性があるのは概論的な部分。
ここを暗記に頼らずに理解できていると強いです。後々まで使えるでしょう。
- 法律は日々触れて記憶に定着
- 概論は試験が終わっても使える可能性がある
熱と流体の流れの基礎
熱と流体の流れの基礎は、機械系大学でいう熱力学や流体力学の分野です。
実務というよりは大学で学ぶ内容に近いです。
大学卒業してから実務でも触れていないと、忘れてしまいそうですね。
燃料と燃焼
燃料と燃焼は燃料の特徴や燃焼計算などです。
これはボイラー技士の試験内容と、とても良く似ています。
熱利用設備及びその管理
熱利用設備及びその管理は設備に関する試験項目です。
実務で担当するかどうかは、経験年数に依存します。
入社3年目くらいを想定して、実務で経験する科目かどうか解説しましょう。
- 計測及び制御
- ボイラ、蒸気輸送・貯蔵装置、蒸気原動機・内燃機関・ガスタービン
- 熱交換器・熱回収装置
- 冷凍・空調調和設備
- 工業炉、熱設備材料
- 蒸留・蒸発・濃縮装置、乾燥装置、乾留・ガス化装置
計測及び制御とボイラ、蒸気輸送・貯蔵装置、蒸気原動機・内燃機関・ガスタービンは必須科目ですが、熱交換器・熱回収装置と冷凍・空調調和設備と工業炉、熱設備材料と蒸留・蒸発・濃縮装置、乾燥装置、乾留・ガス化装置は選択科目です(4科目中2科目)
計装及び制御は、いわゆる計装制御の分野。
化学プラントでも登場する温度計や流量計など、一般的な計装に関する知識です。
計装は設備系ならどこでも似たような物を使うので、他の資格でも登場するでしょう。
電気も計装も設備が変わっても使いやすいという意味で、機械よりも汎用性があります。
ボイラ、蒸気輸送・貯蔵装置、蒸気原動機・内燃機関・ガスタービンは、エネルギー管理士ならではの設備でしょう。
化学プラントではボイラー以外は担当するチャンスは少ないかもしれませんね。
熱交換器・熱回収装置は、熱交換器そのものですね。
化学プラントでも非常によく見かけます。
経験が浅いエンジニアも担当することは多いです。
熱交換器の設計をしていくうちに次第にマスターしているでしょう。
合わせて熱計算も習得できるでしょう。
冷凍・空調調和設備は、冷凍機やエアコンとして化学プラントで登場します。
冷凍機やエアコンの設計はレアなので、数年レベルでは担当しないこともあり得ます。
実務で担当した経験があるならチャンスの科目です。
工業炉、熱設備材料は化学プラントではあまり多くはありません。
環境処理系の設備で使うことがあるでしょうが、担当するかどうかは運の要素が入るでしょう。
蒸留・蒸発・濃縮装置、乾燥装置、乾留・ガス化装置は、蒸留や乾燥装置として化学プラントで登場します。
蒸留や蒸発は、反応器レベルでも実施できますので、担当する人もいるでしょう。
乾燥機は冷凍機やエアコンと同じで、実務で担当するかどうかは運に依ります。
先に準備しておくこと
エネルギー管理士を取得する前に、準備しておくことをまとめます。
先に取得する資格
エネルギー管理士の熱分野を取得する前に、ボイラー技士2級を取得しておきましょう。
ボイラーという機械そのものが試験範囲になっており、燃焼計算も重なっています。
制御回りも重なる部分があります。
先にボイラー技士の勉強をすることで、エネルギー管理士として勉強する部分を少しでも減らすことが可能です。
ボイラー技士2級を取得しておく。
実務で経験しておくこと
資格ではないですが、実務で経験しておいた方が良いこともまとめましょう。
熱交換器の設計はほぼ必須です。
ここで熱計算をしていると、資格の勉強範囲を絞ることができます。
冷凍機・エアコンや蒸留・乾燥は経験するかどうか運に左右されるので、どれか1つは経験していると勉強しやすいと思います。
- 熱交換器の設計は経験しておく
- 冷凍機・エアコンもしくは蒸留・乾燥は1度は経験したい
遅すぎてもダメ
エネルギー管理士の資格は、学校卒業後に時間を空けすぎていると大変です。
入社して3年くらいまでに取得しておくのが理想だと思っています。
熱力学や流体力学などは、実務というよりも学校の勉強に近い問いが出てきます。
大学でこれらの科目をしっかり勉強していれば、卒業後5年10年経っても忘れないでしょう。
そうでなければ、いざ勉強しようとしたときに忘れていることを思い出す必要があります。
これって結構な抵抗感です。
私も今更、エネルギー管理士の試験を受けるのは抵抗感があります。(熱でも電気でも)
参考
関連記事
最後に
化学プラントの機械系エンジニアがエネルギー管理士の熱分野の資格を受験する前に知っておきたいことをまとめました。
入社3年目くらいまでに取るのが理想。熱や流体の計算は忘れます。
ボイラー技士2級は取っておくと楽になります。
実務では熱交換器の設計は経験しておきましょう。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
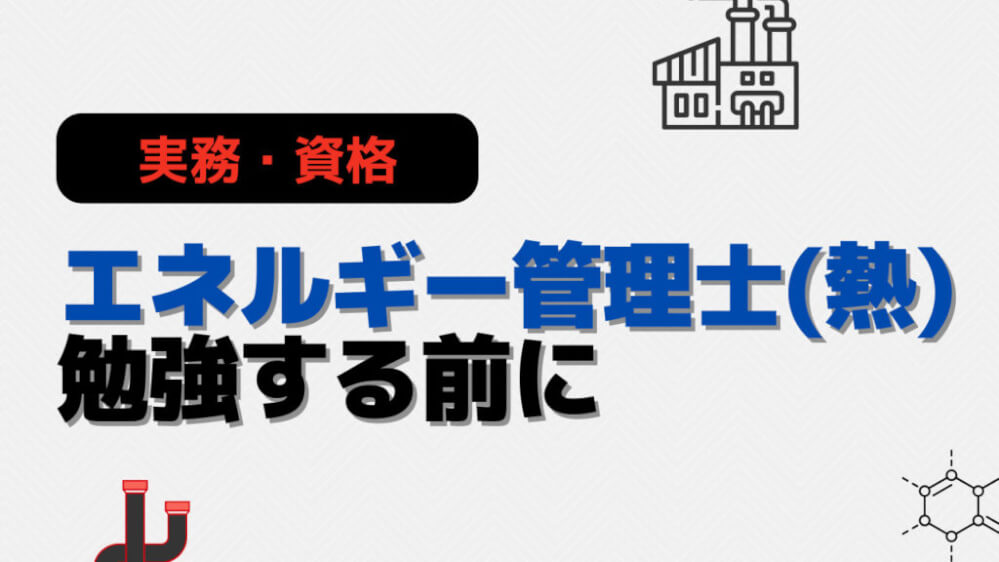

コメント
高卒の初学者です。宜しくお願い致します。今年初めて、エネルギー管理士熱分野を受験しました。4科目不合格でした。3年前の過去問が特に役に立つようです。リフレッシュ休暇を使い切り、受験に臨み図書館に通いましたが、想像以上に苦しい戦いでした。合格は遥かに遠く及びませんでした。素直にDVD教材を買った方が良いのでしょうか? (11/11(土)に2級ボイラー技士、その後eco検定を受験する予定です。)冷凍機械3種、危険物乙4も、今後勉強しようと思っています。流体力学、熱力学は未経験です。取得済み資格は、電気工事士1,2種、電子機器組立1級、運転免許証など。
コメントありがとうございます。キャリア的にかなり難易度が高いものに、いきなりチャレンジされたと思います。受けるとしても電気分野の方がよかったのでは?と思います(電気分野は詳しくなくて申し訳ありませんが)。仕事しながらだと、流体力学や熱力学の知識がある状態でも、数カ月のレベルで勉強時間が必要になるので、どこでも見れる書籍の方が結局は無難だと思います。こちらに参考資料がまとまっています。https://www.sat-co.info/blog/energy190007/。エネルギー管理士試験 徹底研究とエネルギー管理士 試験講座シリーズを私は使いました。分かりにくい部分があれば、質問いただければ答えられる範囲でこたえたいと思います。
がんばってください。