黒字リストラが話題になっている昨今、私が居る会社でもそういう噂が聞こえてきたりします。実行する前に社内ではいろいろ動きがあって最終的にリストラという流れになる(リストラの話が急にあってそれまで何もなかった、というわけではない)という立場から、会社の中でどういうことが起きるのかを私の例として考えます。
化学会社の話ではありますが、なるべく一般化しようと思います。
この記事は、業界再編シリーズの一部です。
三菱ケミカルの希望退職に対して思うこと
住友化学も人員削減へ:三菱ケミカルに続く構造改革の波
プラントオペレーターが余る時代が来る?― 現場の人員過多とその影響を考える
化学プラントの設計職場で起こる窓際族問題を考える
オーナーズエンジニアの設備設計は将来性があるか?
石油化学だけの話と思っていない?化学業界を覆うコモディティ化の本質
化学プラントでアウトソーシングされる部門とは?その理由と人材の特徴を解説
化学工場の付加価値はどこにある?──各部署が抱える現実と構造的な価値低下を考える
業績好調でも危ない会社のサイン:黒字リストラの裏側にある構造的課題
稼働の減少
最初に考えることは稼働です。製造業である以上、物を作って初めて成立します。リストラが起きる前には稼働の減少が先に起きているはずです。
工場の稼働は小さい工場なら割と多くの人が全体像を把握できますが、大きな工場であれば部分的な情報しか分からず全体像が掴みにくいです。それでも、従業員の「稼働が空いてきた」という体感的な情報が十分に参考になります。稼働の増減は年ごとに差はあるものの、減少が継続的に起こる場合、会社は何かしらの対策を考えます。
いきなりリストラという話にはならなくても、稼働減少が続けば会社は表に出ない範囲で粛々と検討を進めます。現場レベルでは情報が回ってこずに、まだ大丈夫だろうと思っていると裏では話が進んでしまいます。
とにかく、稼働の減少は黄色信号として認識して、会社での行動や態度を考えるタイミングです。意外とこれまでと同じ行動をとる人が多いからこそ注意したいです。
設備投資の減少
稼働の減少を補うためには、新製品の導入や合理化などの努力を工場では進めます。
新製品の導入
新製品の導入は工場でもビックイベントで、稼働が減っていることを認識していれば大きな期待を持つことでしょう。これは開発タイミングなど自身ではコントロールできない話なので、新製品の導入の話がオープンにならない時点で黄色信号であると考えられます。稼働の減少が継続していても、新製品の導入の話が積極的にあれば、大きな問題にはならないので新製品の導入の方が大事と考える場合もあります(どちらが大事という話はここではしません)。
合理化
新背品の導入がなくても、工場としては合理化を進めていきます。これは競争力を上げるために粛々と進められるでしょう。ところが、1つの生産品目で合理化を続けるのは限界があります。
・少しの投資で、大きな効果が創出される
・大きな効果が期待できても、大きな投資が必要
・投資が必要だが、効果があまりない
こんな感じで重要度や緊急度で仕分けして、取り組んでいきます。リストラを起こす前には、合理化に寄与する投資の大小をチェックしてみると良いでしょう。運転や企画に関わる人以外でも「それってどれくらいの効果があるのですか?」と聞いてみると良いです。定性的な理解はできます。
設備更新のみ
設備投資が減少していくと、新製品の導入や合理化は行われません。大半が設備更新になります。これは、「本当なら投資自体をしたくないけど、続けるためには止む無く更新しないといけない」という消極的な投資になります。
この状態が続けば、利益が出るか怪しいプラントのために設備投資をいつまで続けるか、という検討が進みます。一度建ててしまうと停止が難しい化学プラントだからこそ、設備更新だけが続いていくプラントは黄色信号でしょう。
会社によってはそもそも投資が積極的でないという場合もあります。この辺は、中長期的な差をチェックして何となく知るのが実際でしょう。
人の異動
稼働が減って、設備投資も減っていくと、人の異動の話が出てきます。
工場内間接部門
製造業では工場に人が多いので、まずはこの人にどういう仕事をしてもらおうかという発想で動きます。まずは工場内の間接部門に人が異動していきます。固定費としては変化がないけども、1つの製造部門に紐付く人を減らせば、工場目線では生産品目に対する固定費が減っているように見えます(=本社固定費に押し付けているとも言えます)。
これは工場内で人を動かすのと、工場外に人を動かすのでは、難しさが変わるからです。工場内で人の再配分ができる範囲なら、赤色信号の一歩手前という感じでしょう。
間接部門に異動した人が、急に仕事ができるわけではありません。年齢がある程度たっていれば教育効果もあまり期待できません。チームの頭数は増えても質は上がらない。それでもリストラに踏み切らないだけ何とか繋がっているという感じです。
異動は社員ならチェックが可能なはずなので、間接部門への異動などいつもとは違う流れがそれなりに続くようであれば動いている1つの証拠になります。異動通知のチェックはこの意味で大事ですね。
工場外異動
工場内での異動が難しい場合に、別の工場への引っ越しを伴う異動が考えられます。これは、他の工場で人が足りないという前提が付きます。
ここで多くの人は考えるでしょう。引っ越しが嫌で今いる場所から移りたくないかどうかを。引っ越しが嫌ですと主張すれば、選択肢は急に少なくなります。
全社集約
工場に居る人が過剰になれば、全社など集約させます。これは製造オペレータに限りません。工場に在籍するのは、その工場で学ぶことが多いからというのが会社が考えること。学ぶことが少ない工場なら、近くに住む必要はなくスポットで出張すれば良い話。
各工場に機能を持たせると人が必要になり、伝言ゲームも発生します。これを1つの場所に集約できればコストダウンは確実。都会志向の人が多いという点も後押しの材料になります。
機電系エンジニアも保全は工場に紐付きますが、設計は例外ではなく全社集約という可能性が十分にあります。
子会社
子会社への出向転籍は分かりやすい流れでしょう。定期的に実施している会社ならともかく、役職定年など一定の人だけが当てはまるのが普通。
これが、若い人も含めて起こるのであれば、リストラの一歩手前。会社を辞めるか子会社に移るかという2択を迫られているはずです。
管理職の動きは読みにくい
リストラが起こる前に管理職の動きをチェックしようという話がありますが、これは現実には難しいと思います。
・課長クラスだと日常の会議が多くて、多少会議が増えたところで気が付かれにくい。
・面談で露骨に希望部署の話をしている段階では、すでに取り返しがつかないポイントに到達。
・マニュアル整備などを進めているうちは、まだ救いがある
あえてチェックすると言えば、役員や部長クラスの人が、本社などへの出張の機会が増えたかどうかでしょう。シビアな話を工場ですると噂が広がるかも知れないので、気を使います。かといって、本社出張を意図的に増やしても気が付かれます。定期的な出張がある役員・部長が、そのタイミングで裏で話をするというのが現実的でしょう。この辺りは結構徹底されると思います。
工場だと夜に合宿など、工場とは別の場所で議論したりもするようです。
参考
最後に
リストラは表に出る直前までは伏せられているように見えますが、内部では必ず
- 噂
- 組織整理
- 業務の軽量化
といった前兆が積み重なっています。
「急に決まったように見えるけれど、実際には長い準備期間がある」
というのが現場で見た事実です。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)X(旧Twitter)のDMでも可能です。
- 設備設計で悩んでいる
- トラブル原因の考え方が分からない
- 若手の教育方法に困っている
など、幅広くお受けしています。
*いただいたコメント全て拝見し、数日中に真剣に回答させていただきます。
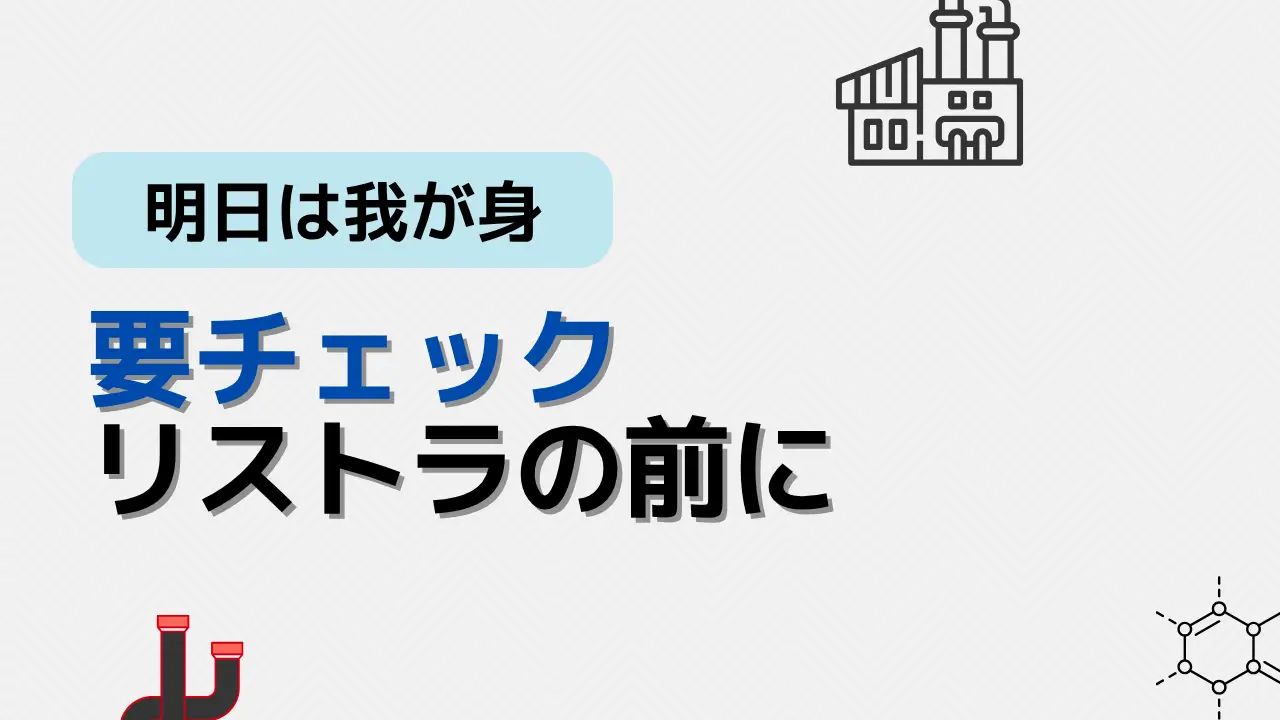
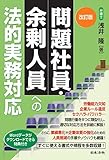
コメント