化学プラントのエンジニアには、プロセス系・機電系を問わず非常に幅広い知識が求められます。特に機械系エンジニアは、日々の業務をこなす中で「機械の知識、どこまで学べばいいの?」という悩みに直面しがちです。
機器の種類が多すぎて混乱したり、何から学べばよいか分からなかったり、知識量の多さに圧倒されてやる気がなくなってしまうこともあります。
そこで今回は、化学プラントにおける機械系エンジニアが、どこまでの知識を目指すべきか、どう学び、どう活用していくべきかについて、現場目線で解説します。
専門家ではない
化学プラントの機械系エンジニアは、機械に関するエキスパートではありません。
自分たちで機械を作るわけでなければ、補修も専門的なものならメーカーに依頼します。
3D-CADで設計試作をして量産化するわけでもありません。
世の中にある多くの機械設備を組み合わせてプラントを作り上げ・維持していくことが仕事です。
機械設備の良否を判定して、そのプラントの運転に最も適したものを選ぶためには、機械の知識が無くてはいけません。
機械の専門家ほどの知識は無くても、素人ではいけない。
この立ち位置をしっかり理解しておくと、気が楽になるでしょう。
機械系エンジニアの習得する知識例
化学プラントの機械系エンジニアが知っておきたい知識のレベルを、個々の項目にわけてざっくりまとめました。
| Lv.1(初心者) | Lv.2(製造) | Lv.3(目指すレベル) | Lv.4(専門家) | |
| ポンプ | 水を送る機械 | プラントで最も壊れやすい設備 | 型番や種類がいっぱいあると認識 | プロセスに応じて使い分けができる |
| ベアリング | なんか軸に付いている物 | 定期的な交換が必要 | 型番や種類がいっぱいあると認識 | 型式や種類の特徴を大体知っている |
| 減速機 | 速度を落とす | オイルが入っている | 型式や種類がいっぱいあると認識 | 型式や種類の特徴を大体知っている |
| 潤滑油 | オイル | 漏れてくるもの | 粘度や種類がいっぱいあると認識 | 型式や種類による特徴差を大体知っている |
| 溶接 | 金属と金属を繋げる方法 | 火を使って危ない | 方法・向き・欠陥など区分がいっぱいあると認識 | 方法・向き・欠陥の特徴を大体知っている |
| 材質 | 鉄とか樹脂とかある | ステンレスの種類をいくつか知っている | 鉄・ステンレス・樹脂の特徴を大体知っている | 各材質の使い分けができる |
| 配管 | 水道・ガスなどのアレ | 材質・フランジなどいろいろある | フィッティングの種類がいっぱいあることを認識 | フィッティング・フランジなど使い分ける |
| 保温 | 家にあるグラスウール | 保温・保冷で使い分けをしている | 保温・保冷の種類がいっぱいあると認識 | 保温・保冷の特徴を大体知っている |
| 足場 | 工事の周りにあるもの | 必要でもあり邪魔でもある | 工法がいっぱいあると認識 | 現場に応じた工法を選択できる |
表中のLv3くらいが機械研エンジニアの目標としています。
かんたんにいうと、「○○はいっぱいの種類がある」ということ。
この事実をしっかり認めることができれば、後は実務で触れていくうちに数個の種類の議論が多いことに気が付くでしょう。
その数個の性能比較を定性的・定量的に理解できていれば、合格です。
他の項目の学習に入って良いでしょう。
例えば材質なら、SS400・SUS304・SUS316Lくらいが最初の学習ポイントでしょう。
ハステロイ・グラスライニング・フッ素樹脂ライニングくらいまで目を向けたら、材質はとりあえずOKだと考えています。
この後にSGP・STPGなど鉄配管の種類を掘り下げても良いですが、個人的には後回しでも良いと思っています。
1つの分野で多くの種類全てをカバーするための学習時間を取るのは、非常にもったいないです。
使いもしない知識を持っていてもあまり意味はありませんからね。
専門家と議論して確立
理解した数個の知識を、専門家と議論しましょう。
社内にそういう相談できる人が居れば、積極的に活用すると良いです。
いない場合は、メーカーなど専門家に聞きましょう。
機械系エンジニアが知識として習得する範囲内で課題となっているものは、自分より詳しい人が外部にいるはずです。
例えば設備を購入する時に仕様の比較をしたいなら、メーカーに聞くという感じです。
実務に直結します。
メーカーはユーザーの使用条件の裏の部分が分からないものの、一般的な知識は持っています。
一般論としての話は相談に乗ってくれますので、自分が習得した知識の理解が間違っていないかをチェックする目的では有効に働くでしょう。
勘違いして「メーカーが言うからこの設備はこれが最適」とメーカーに判断を委ねないようにしましょう。
知識を総動員して判断するのは、ユーザーである化学プラントの機械系エンジニアです。
素人に説明して自信を付ける
自分で知識を習得し、専門家にも意見を聞いた内容を、素人である製造・企画などの部署に説明しましょう。
技術的な知識レベル差があるので、細かな説明は求められません。
たいていの場合は、取りえる選択肢の中でどれが最も最適かを考えることになるでしょう。
その判断材料としての説明を求められます。
繰り返していけば、どんな説明が求められるか理解できます。
自信もついてくるでしょう。
素人に対する説明が上手くなって信頼が得られると、機械系エンジニアから製造・企画などの別部署への異動の可能性が増えてきます。
キャリアとしても知識としても、ステップアップしやすくなるでしょう。
参考
関連記事
最後に
化学プラントの機械系エンジニアは、「全部を理解する」ことよりも、「どこに種類が多いかを認識し、代表的な選択肢を理解する」ことが重要です。
専門家のような知識は不要でも、運用判断ができる最低限の理解は必須。
学んだ知識を、実務で使いながら、専門家に確認し、素人に説明できるようになれば、確かなスキルとして自分の中に定着します。
知識の広さよりも、実用性と判断力がカギです。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
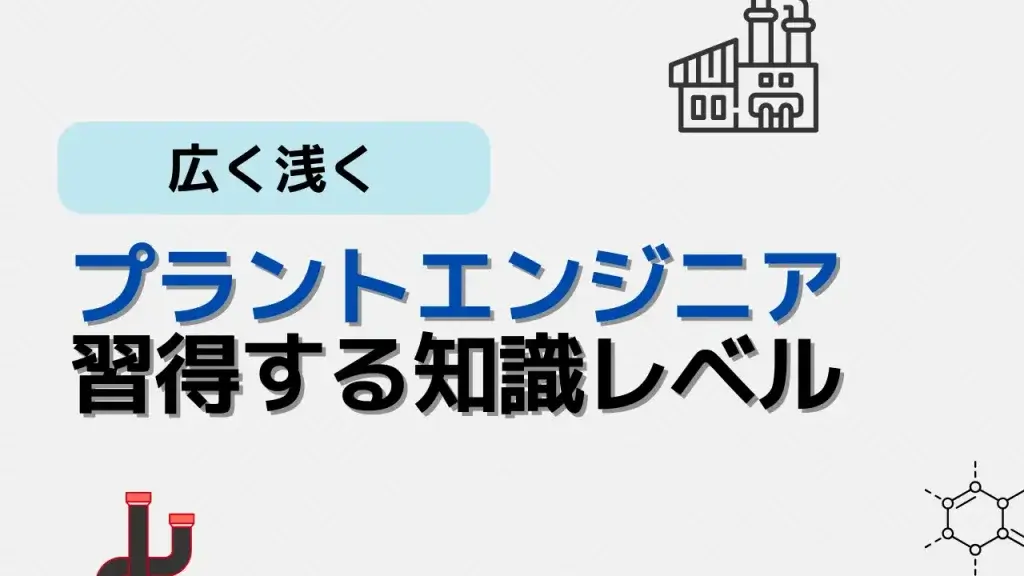

コメント