化学プラントの建設プロジェクトが終わり、いよいよ商業運転が始まる。しかし、その直後から現場では様々なトラブルや課題が次々と表面化します。多くの場合、その原因はゼネコンへの丸投げに起因し、設計思想の欠如や不十分な情報引き継ぎが影響しています。運転やメンテナンスに関わっている人がかなりの苦労をしています。
本記事では、化学プラント運転開始後に起こる問題の実態と背景を解説し、なぜこうした課題が起こるのかを掘り下げます。
不具合が放置される
現地工事をしていく中で、不具合は必ず発生します。
どれだけ努力して設計段階でフォローしても、ゼロにはなりません。
修正が簡単なものや、大きな問題ではない不具合なら、工事中に手直しすることは止めておいた方がいいでしょう。昔は、工事完成までに手直し必須という風潮でした。
手直しに掛かる労力がとても大きくマンパワーが追い付かないので、手直しの要否を取捨選択します。
取捨選択の段階で、オーナーとゼネコンとで衝突が発生。

面倒なので、何とか運転開始できればいいや
こんな感じで、オーナー側はいろいろなことを諦めていきます。
この流れが強くなってくると運転上の明らかな問題ですら、「面倒だから放置」されます。
ゼネコンだからしっかりしているだろう。
こう期待していたら、いつの間にか撤収されて問題が残り続けます。
設計思想が残らない
ゼネコンによるプロジェクトを進めていると、設計思想が残りません。
設計図書であるP&IDや機器図などの情報は、成果物として当然残します。
残らないのは設計書。
その仕様をなぜ選んだのか、そのシステムをなぜ選んだのか、残らないことの方が多いです。
基本設計に相当する部分ですが、EPCを一括でゼネコンに依頼したときに、設計書としてのEを作るのはとてもハードルが高いです。
社内で設計書を書こうにも、関係部署内でのチェックで設計書は赤ペンだらけに。
これを社外の人が書こうものなら、赤ペンだけでは済まない世界になるでしょう。
最低限の仕様部分は書くことができても、その思想までを理解するには、必要な言語化量が計り知れないものになります。
その情報をちゃんと理解して実行に移すのに、1年ではとても足りません。
プロジェクト工事を慌てて実施して、最後はかなり悲壮感が漂っている中で、設計思想を残そうという気にはならないでしょう。
メンテナンスに引継されない
建設が終わったら、メンテナンスに引き継ぐのが設計者の役目です。
これが上手くできているケースを見たことがありません。
社内プロジェクトでも、エンジニアリングとメンテナンスでの情報引継は難しいもの。
何をどう伝えて良いのか、分からない人の方が多いです。
エンジニアリングとメンテナンスの両方の仕事をしていないと、実感がないですから。
引継と言っても、設計図書の引き渡し程度でしょう。

図面はいっぱいあるから、後はよろしく

いっぱいあるのに、何の解説もなしに丸投げ?
実態は、資料の押し付けです。
設計書として文章が残っているわけでなく、図面から読み取って解釈しないといけません。
読み解くには膨大な時間が必要。
情報が渡されている段階では、プラントはすでに運転しようとしていて、読む時間すらありません。
さらに、例えば使用環境や腐食性の情報など、設備のメンテナンスに関わる情報は書かれていません。
この瞬間に、情報の引継は途絶えます。
エンジニアリングに目を当てると、ゼネコンに設計建設を丸投げして、得られた成果をメンテナンスに丸投げする、という結果として考えることができるでしょう。
建設プロジェクトにおいて、オーナーズエンジニアは調整業務に徹することになりますが、そのためにはちゃんとした知識と行動力が必要ですね。
無ければ・・・。・・・。
参考
関連記事
関連情報
プロジェクトの予算管理
プロジェクト経験者の誤解
難易度ランク
マネジメントの重要ポイント
プロジェクトマネジメントで大事なこと
マネジメントの思想
失敗から学ぶ
最後に
ゼネコン丸投げによる化学プラント建設プロジェクト終了後の運転開始時には、不具合放置、設計思想の継承不足、そして情報引き継ぎの欠如という重大な問題が待ち受けています。これらの課題は現場の効率と安全を著しく低下させ、長期的な運用コスト増加にもつながります。
問題解決には設計者とメンテナンス担当者間の密な連携と、オーナーズエンジニアの専門的介入が不可欠です。今後のプロジェクト運営には、この点を強く意識した改善が求められます。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
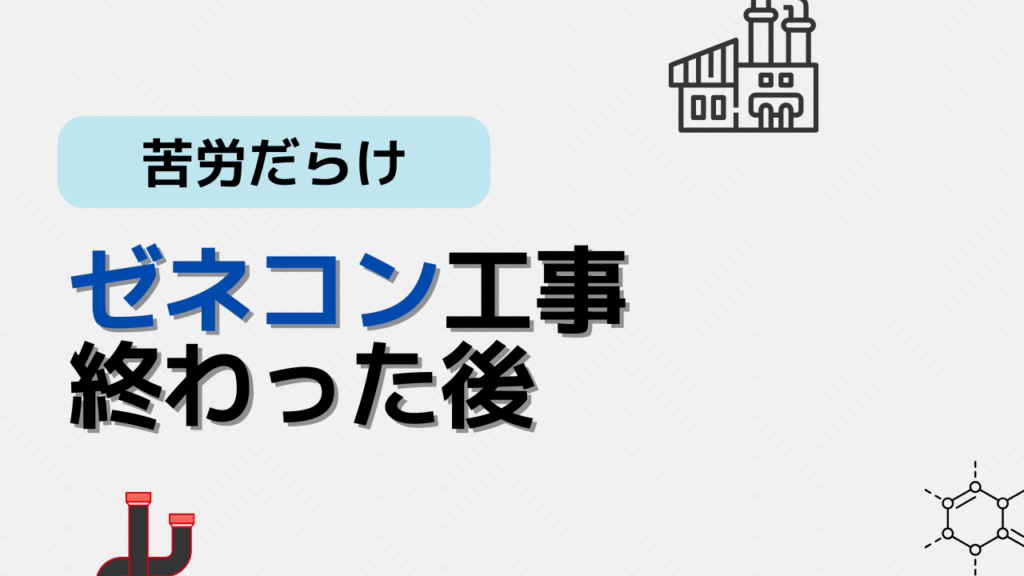

コメント