化学プラントに入社した新入社員にとって、現場実習(工場実習)は初めて現場に触れる貴重な経験です。しかし「何を学ぶべきか」「どのように現場を見ればよいのか」が分からず、戸惑う方も多いでしょう。
本記事では、現場実習の目的や具体的な学び方、注意点までを詳しく解説します。これを読めば、現場実習を最大限に活かす方法がわかります。
現場実習の目的
現場実習の目的はごくシンプルです。製造業の中心である工場の実態を知ること。これだけのはずです。
でもこの表現の表面的な部分だけを見て実習に臨んでいたら、時間を無駄にしかねません。製造部のオペレータと同じ目線で物事を見る機会はそんなに多くはありません。例えば以下のようなことを学ぶと良いと思います。
- 交代勤務の精神的、体力的苦痛
- 工場の運転方法や設備(の基本的な考え方)
- オペレータの運転に対する考え方
- オペレータが持っている知識
- 人間関係に対する考え方
- 組織に対する不満
例えば、機電系エンジニアなら設備の使い方や構造を知るように、指導を受けて現場実習に臨むでしょう。でも、そんなことはどうでもいいです。後でいくらでも学習できます。
本当に学習したいことは「オペレータの考え方」そのもの。彼らと同じ行動をとり同じ目線で同じものを見ることで、考え方を習得しようとすることが最も大事です。
レポートのような表面に発信されるものでなくても構いません。自信の内面にちゃんとインプットして、工場の文化を習得することが後の本来業務に活きます。そのために現場実習があるといっても過言ではないでしょう。
というのも、現場実習が終わったらオペレータと同じ目線で仕事をすることはなくなります。立場が変わるから微妙な壁ができてしまい、考え方を知る機会は確実になくなります。
現場実習の時期
現場実習の時期は、会社によってまちまちでしょう。
5月~6月
一般には5月から開始します。これは4月に入社して配属先の導入教育が終わった段階が、大腿5月だからです。GWより先にすると、5月病と重なってしまうリスクもあります。
終わりは会社や工場によって様々です。半年~1年くらい実習をする場合もあるでしょう。
現場実習は工場配属者だけでなく本社勤務者も行います。ここでは日数を削減して例えば1週間~2週間程度で終了する場合もあります。やった感を出すって感じですね。
現場実習の内容
現場実習の内容は基本的には見学のはずです。
見学
現場実習での見学は、オペレータの後を追いかけるという形になります。
- オペレータが計器室にいれば計器室にいる。
- オペレータがプラントに行こうとすればついていく。
- 食事も一緒に取る
- 雑談をする
こんな感じです。
オペレータと同じように現場を操作するということは、基本的にはさせません。操作をさせている会社はかなりマズイと思います。というのも、現場の危険性・安全対策・報連相・責任など製造操作に関する十分な知識がない中で作業をしてしまって何かあったら大ごとになるからです。
製造部からしても余計な手間にしかならない現場実習。とにかく後ろをついてきて、怪我をせずに帰ってもらうことを第一優先にしています。下手をしたら計器室内でじっとしてなさい、というプラントもあります。
昨今では階段や床の突起物に躓いただけでも問題になりますからね・・・。見学といってもおそらくはオペレータが何をしているか学ぶことはできないはずです。というのも生産方法や運転操作を知らない中で、オペレータの作業だけを見ても理解できるはずがないからです。
そもそも専門用語すら良く分からないまま終わるでしょう。分からないことを聞こうと思っても、オペレータに余裕がなくて聞けないという場面も多いはずです。
見学内容は連続とバッチでかなり変わります。連続は本当の意味で見学だけ。メイン業務がパトロールとなりがちだからです。なお、バッチ系なら手動操作が意外と多いので、プラント内を動き回ることもあります。
私が現場実習をしたときは完全手動操作だったので、交代勤務でも昼夜問わずにプラントを動き回った記憶があります。仕込み作業の準備程度なら手伝います。分液作業など待ち時間が掛かる場合には、結構な雑談をしたりします。この雑談こそが現場実習で最も大事にしたいことですね。
テーマ設定
何かしらテーマを与えられるでしょうが、操作をすることはないでしょう。生産技術・化学工学系の新入社員ならプロセス合理化の検討をテーマに挙げて、空いた時間に検討するというミッションを与えられるでしょう。
機電系の設備エンジニアはそういうミッションを与えにくくて、とても困ります。設備改善を現場目線で何か1つ提案すること、というようなテーマになるでしょう。目に見える成果がなくてもOKです。自分の意見を出すアウトプットの場をして使うだけです。
研究発表のように過剰に考える必要はありません。
- 化学工学系ならプロセス合理化の検討
- 設備系なら設備改造の提案
日報・レポート
実習中は報告書を書くことが多いでしょう。日報というのが意外と厄介です。というのも日々書く内容が無くなっていくから。
いわゆるネタ切れ状態になります。現場実習では日々のレポートのネタ探しのために、現場に行くという場合もあります。週報レベルで頻度を落とす方が良いと思います。
現場配属
現場実習と関連して現場配属はテーマになります。これは製造部のオペレータではなくて、現場付きのスタッフや主任などのポジションを目指すルートです。オペレータとは違う層なので、オペレータとは壁ができてしまいます。それでも現場に近い目線で仕事ができます。
だからこそ、多くの人に経験してほしいポジションです。ここに誰をいつアサインするかということは話題になります。4月に入社する院卒・大卒者は実験系・化学工学系・機電系などは製造部とは別の間接部門として配属されがちです。
彼らにとって現場実習はとても貴重な機会。でも、入社してすぐの現場実習って学べることが限られています。機電系エンジニアなんて、工場の設備を知らないまま入社して現場に放り込まれて現場を走り回り気が付いたら現場実習が終わっていた、なんてことも。
製造部と機電系の組織の関係性なんて理解できませんからね。実習から開けて実務に戻ると、多くの機電系エンジニアが現場の使い方が分からないといって悩みます。個人的には入社後3~5年で、一度現場のスタッフや主任に異動することが理想的だと思っています。
早すぎても遅すぎてもよくありません。早いと現場実習と同じ感覚で学ぶことが少ないですし、遅すぎると異動前の部門の思考で凝り固まってしまいます。私の場合、とても遅いタイミングで異動したため苦労しました。
現場実習を一回経験したから、現場のことは知っていて当然・あとは専門性を高めていくように、なんて綺麗ごとで非現実的です。ローテーションは大事ですね。
現場実習は新卒者のみ
現場実習は新卒者のみが対象となり、転職者は対象外となりがちです。特に機電系エンジニアのように、現場と接触する機会が少ないけども現場の考え方を知ることが大事な職場だと、この差は結構大きいです。
新卒者にとっては単なる一イベントの現場実習ですが、実は貴重なチャンスです。
関連記事
現場実習に関連してキャリアや仕事内容をさらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
最後に
- 現場実習の目的は「オペレータ目線での考え方の理解」。
- 見学が中心で、操作は基本的に行わない。
- テーマや日報は学びを整理するための手段。
- 実務では得られない現場文化や考え方を習得する貴重な機会。
現場実習で得た知識と経験は、化学プラントでのキャリアを築くうえで必ず役立ちます。新人のうちに現場理解を深めることが、将来の成長につながるでしょう。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
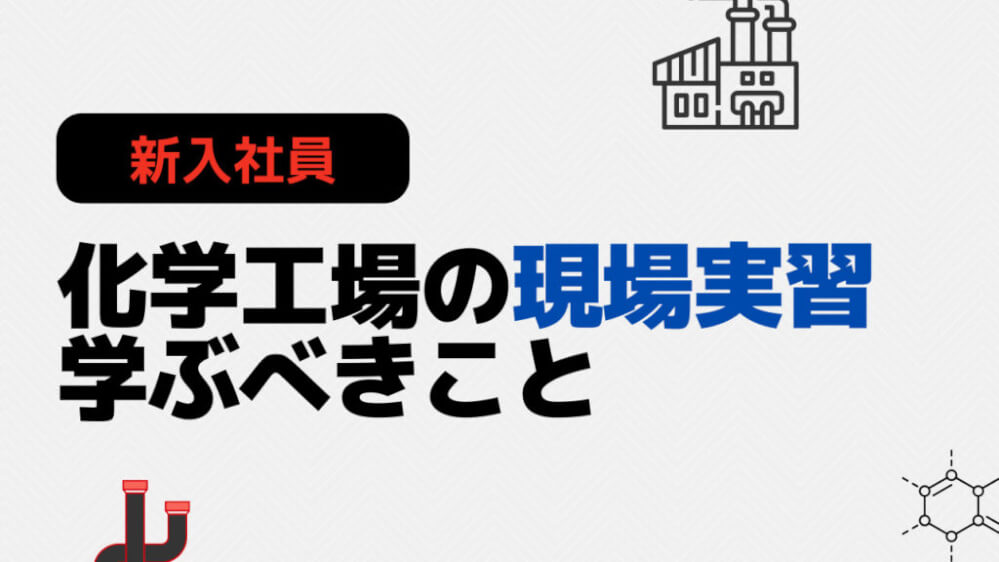
コメント