日本のものつくりの品質は極めて高い。こう言われて久しい一方で、品質問題が最近はたびたび発生しています。この側面には「過剰品質」があることは、最近では認知されるようになってきました。それでも、品質を下げることはとても難しいです。
この記事では、化学会社の品質について私が経験した範囲で、品質について感じている問題をまとめました。どうしようもないと思っていても表立って言えない問題、みなさんもありませんか?
この記事は、品質シリーズの一部です。
原料の品質を落としても大丈夫? 化学プラントで考える“製品への影響”
4M変更管理の重要性:品質トラブルを未然に防ぐために
化学プラントの品質トラブルは“工事”で起きる:設計者が注意すべき落とし穴
安全・環境・品質が化学プラントで深く関係する理由
オーナーエンジニアが現場で実践すべき配管工事の品質管理手法
とりあえず決めた原料規格
化学会社では、原料に対して化学反応を使って加工することで目的の製品を得ます。品質という場合に最初に目が行くのは「原料」です。
契約規格が厳しい
原料規格は、外観・含量・不純物などを契約時に取り決めします。この規格が以上に厳しいというケースはかなりあります。
この問題はユーザー側で気が付く可能性はあまり高くはありません。原料メーカーはとてもよく認識できます。特定の化学物質をユーザーから求められ、含量や不純物の差が出てくるからです。
原料メーカーとしては、各種ユーザーの要求に答えるように「通常グレード」と「特殊グレード」のようなグレード分けをすることになります。これははメーカーのプラントの稼働調整を難しくする要因となり、特殊グレードを要求するユーザーとしても納期調整を難しくすることになります。
PSSはもっと厳しい
仮に「高級グレード」を設定したとして、原料メーカーのCoAで規格を満足するかチェックするだけでは物足りないというケースは非常に多いです。
いわゆるユーステストをしないと判断できず、PSS(Pre Shipment Sample)が必要となります。これは原料メーカーでの分析では満足できず、ユーザーでも分析をして判断するというもの。契約で定めた規格以上に厳しいチェックがされます。
とくにGMPでは厳しいです。医薬に限りません。少しでも疑いがあれば排除するという印象でしょうか。これは原料メーカーにとっては、手間になることは間違いありません。
一度決めると変更が難しい
原料規格は一度決めてしまうと変更が極めて難しいという問題を抱えます。すでに作れた実績が1度でもある規格なので、仮にその規格で供給できる会社が製造中止になったとしても別の会社を探せるはずだという思想がそこにはあります。
この場合、ユーザーは原料を調達したり、製造指導をしたりする手間が加わります。規格を変更しようものならもっと手間が加わるので、それよりは被害が少ないだろうという発想です。
そこまでして製造を維持するくらいなら、製造中止にしても良いのでは?という製品も出てきます。
効果が分からない製品規格
原料として高い規格を維持し、厳しい品質管理で製造して、高級な製品が得られたとしましょう。これが本当に意味があるのか?というのが次の課題です。
良く分からないけど規格として設定してしまうと、製品中でどういう影響が出るかを誰も調べずにその規格を維持しようという動きになります。
結果、工場では0.01%の世界で痛い目を見ることになります。
手直し前提のプロセス
製品の品質を満足しないことがどこかで分かった場合(出荷前でも出荷後でも)、工場としては手直しを考えます。
ところが、製造現場では手直し専用の設備を用意することは稀です。100%良品を作ることを前提としている以上、万が一の備えをすることはありえないという思想でしょうか。
化学関係では例えば、製品粉体を仕込んで溶解・蒸留・晶析・濾過といったプロセスが該当します。これらのプロセスは通常ラインとしては設置していても、手直しラインとして設置していないと、手直しのために通常ラインを使用しないといけなくなります。これは、工場の稼働を圧迫させることになります。
過剰な洗浄
品質を維持するために、製造プロセスで過剰な洗浄をする場合があります。
反応後の水層・油層の分液は洗浄の典型例として考えれます。さらに配管輸送ラインの溜まりが次工程に流れないようにする洗浄も要因となります。
これらの効果が定量的に評価されていれば問題はありません。ところが意外とこれがなされません。単に収率を最大化させることが良しという風潮で、洗浄によって発生する廃棄物の処理費や、溶媒の回収に掛かる費用は、後回しになります。
新製品など初めて作る場合には、徹底して品質を上げるためにとにかく最高スペックを目指したとしましょう。安定して合理化を狙おうとして、洗浄を少し緩和しようとしても、すでに出来上がった品質と同等でないとNGと評価されてしまって、条件を緩和することができない展開が予想されます。
不純物の影響を誰も知らない
製品中の不純物が、次工程であるお客様にとってどういう影響があるか、実は誰も知らないということはありえます。
製品を作るメーカーはそれをお客様に聞くことがそもそも難しいです。製造メーカー目線では、原料メーカーとの関係を考えると分かりやすいでしょう。
次工程であるお客様も、不純物の量を多少増やした場合にどういう結果があるかを都度評価するには、コストが掛かり嫌がります。特定の不純物をスパイクして評価するか、という問題になりますね。
だからこそ、一度決めて作り上げた品質を維持するのが最も被害が軽いと割り切ってしまい、その規格を維持することが絶対だと信じ込まれていきます。
根拠の薄い設備仕様
製造面での品質は、関わる人が一定数居るので目立ちやすいです。一方で、設備品質は、エンジニアや製造管理者にとっては目立つものの、その他の人からは気が付かれにくい問題です。
いくつか例を上げましょう。
バフ掛け
粉体関係の金属設備では、金属粉が異物となることを回避するために表面磨きをするケースがあります。これは粉体の閉塞を回避する目的もあり、一定の効果があるように見えます。
ところが、長期使用しているとその効果が薄れ、またバフ掛けをすることになり、定期的なバフ掛けを求められることになります。
製造目線では、常時綺麗な状態を維持するという意味で良さそうにも見えるこの方法。誰も意見はしないものの、実は異物という意味ではどうだろうと思っています。
というのも、磨いて綺麗だった金属表面が、使用中にざらざらになるということは、何かしら削れたり剥離したりしているということ。これってどこに流れ込んでいるのでしょうね?
グラスライニング設備も使用しているとガラスが薄くなっていますけど、あれって本当にどこに行っているのでしょうね・・・。
超高級材質
設備の材質は腐食を回避するために、適切な物を選ばないといけません。ここで、取扱物質の腐食性が不明だからと、世間でも珍しい材質が候補に上がります。
例えばSUS304だと不安だから、SUS316Lにしてもいいけどそれでも不安。だからハステロイにするというような思考です。
腐食や異物という意味では問題は無くなるでしょう。代わりにコストは爆上がりです(とはいえ、もう少し俯瞰すると実はたいした問題ではないのですが)。
この場合に、SUS304で使っていき一定期間で交換するという割り切った方法は実は考えられます。だって、金属でもグラスでも腐食しても、文句言わないですものね。
異物除去装置を付けない
品質にこだわるラインでありながら、異物除去装置を疎かにしている例は結構見かけます。
例えば、粉体を投入する場合、内部に異物が入りこんでいてもおかしくないのに、それを除去する装置を設けないというもの。
粉体を投入して溶解して反応するという場合なら、ライン中にフィルターを付けて異物を取ることは容易に考えられます。これができてない例はあります。もっと酷い例では、粉体を投入した後、すぐに最終製品となり、異物を除去する隙すら無い工程。
結果的に、原料メーカーにしわ寄せがいき異物を入れないように指導と改善を繰り返すことになります。ここにも工数が発生するので、ラインにフィルターを付ける方が安いと考えてもいいのに対策が取られにくいです。
見た目だけの工事品質
設備仕様と同じように、工事品質も過剰で「見た目だけ」という例があります。
過剰な寸法チェック
設備の据付・配管の取付・ノズルの高さなど図面で表現できそうな部分は、寸法チェックの対象となりえます。
もちろんJISや各社基準で定める寸法を満足すれば良いはず。ところが、厳しい会社では、これらの一般的な基準よりも高いレベルを求めます。それが妥当な理由があれば良いのですが「今までこうやってきたから」という慣習に従っている例も。
検査要領書で各社が提示した基準に対して、自社基準で赤ペンを入れ、やり取りに時間をかける。嫌気がさしたベンダーは、検査ギリギリに要領書を提出し、ユーザーに赤ペンを入れる隙を与えない。ユーザーは改善指導を要求するものの、ベンダーはその場限りの受け答え。次回の製作時には同じことの繰り返し。
多少の寸法はずれても問題ないと割り切れないユーザーほど、のちのち苦労することになります。自社工場だけを見て他社を見てないユーザーほど、このパターンに陥りやすいでしょう。かといって、ベンダーから指摘するのが難しいのは、原料や製品の話と同じです。
溶接の焼け
溶接の焼けが見た目の問題になるから除去するように。
この指摘を過去に何度も目にしました。酸洗浄をしたり単に表面を削り取ったり。対策はさまざま。
GMP工場だから必要、クリーンルームだから必要。だから施工基準に定める。他の一般工場で施工基準を別に定めるのが面倒だから、同じように必要。と波及していきます。
溶接に限らず施工基準を統一化させていくと起こりえます。かといって、この工事だけは別と分けていると管理が大変になるもの確かです。
配管専有化
切替工場では生産ラインを組み替えるために、配管の接続を変えます。ここで、いくつかの配管は内容物が違っても共有化できる(行き先が同じ)という例は結構あります。
ところが、内容物が違うと製品への品質影響が良く分からないから、単独化させるという対応をとってしまいかねません。この場合、生産品目が多くなると配管が同じように増えていきます。気が付いたときには、どの配管がどの生産に使うか分からず、切替の時間が長くなります。結果、稼働日数は下がります。
別の品目を導入するための工事をしようにも、配管を通す場所が無くて施工費が高くもなりえます。
そこまでして品質を上げる必要があるのか、誰も責任を取れない問題ですね。
参考
関連記事
最後に
「品質重視」は製造現場において最重要項目とされていますが、行き過ぎた品質要求は、実は現場に無用な負担やコストをもたらし、全体最適から外れてしまうことも少なくありません。原料規格、設備仕様、洗浄手順、工事品質など、あらゆる工程に潜む“過剰品質”の実態を見直すことは、製造業の持続可能性と効率化に直結します。品質とは何か──改めてその本質に立ち返る時期かもしれません。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)X(旧Twitter)のDMでも可能です。
- 設備設計で悩んでいる
- トラブル原因の考え方が分からない
- 若手の教育方法に困っている
など、幅広くお受けしています。
*いただいたコメント全て拝見し、数日中に真剣に回答させていただきます。
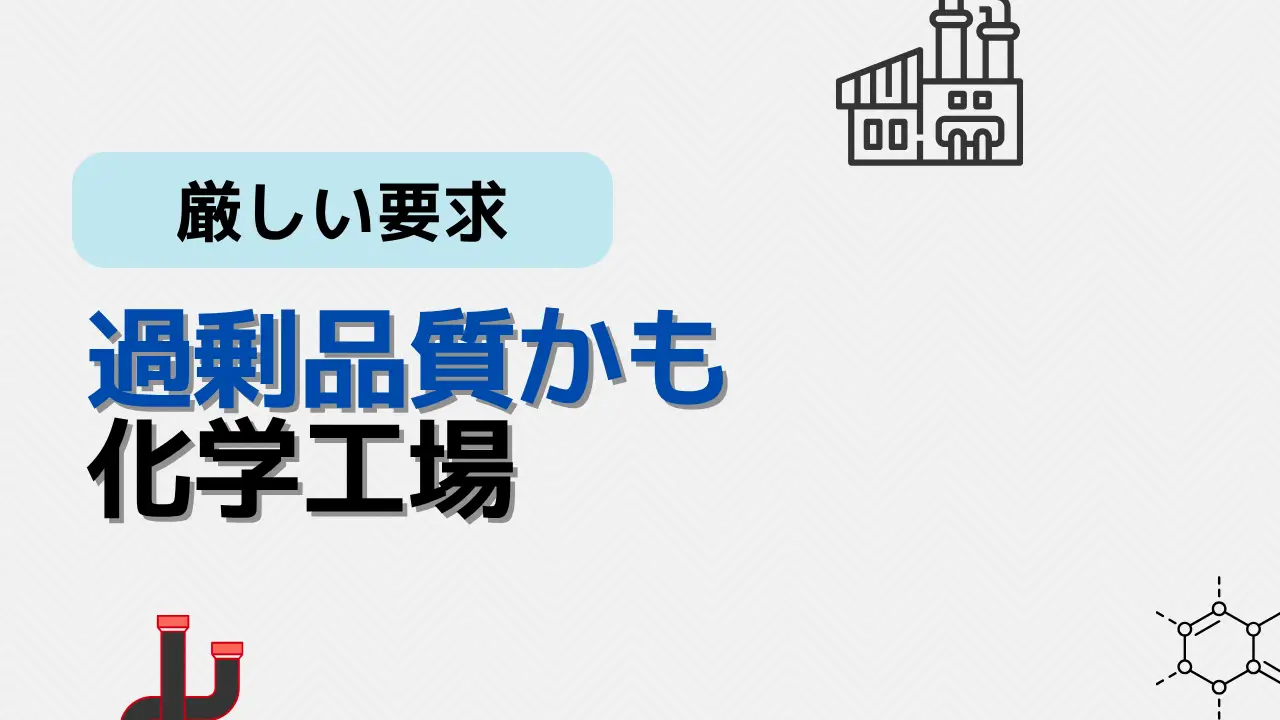

コメント