化学プラントの工事現場では、溶接や溶断作業にアセチレンがよく使われます。しかし、アセチレンは非常に危険なガスであるため、ただ「燃えるから」という理由だけで使ってよいわけではありません。
本記事では、なぜアセチレンが溶接・溶断に選ばれるのか、その特徴と現場での注意点を整理して解説します。機械系エンジニアでも理解できるよう、化学的な背景も含めてわかりやすく説明します。

この記事は、溶接シリーズの一部です。
化学プラントで役立つ「最低限の溶接知識」:機械系エンジニア向け実務ガイド
溶接修理の基本と方法|現場で役立つポイント解説
これで安心!化学プラントの溶接記号の見方と注意点
浸透探傷検査PTで溶接欠陥をチェック|化学設備向け
燃えやすい
溶接・溶断でアセチレンを使うのはなぜでしょうか?
アセチレンは燃えやすいからです。燃やすと大きな熱が出るからです。エネルギー効率が良いと表現してもいいかも知れません。少ない質量でも多くの熱が取り出せるため、各所で必要な熱源として効率的に運用が可能です。
熱を多く取り出せるのはなぜか?というと三重結合の最もシンプルな炭化水素だからです。エネルギー効率の観点から、危険なアセチレンを使用しています。
この辺の認識は薄くて、とにかく危険だからアセチレンを扱う設備は慎重に扱おうという程度の扱いを受けがちです。溶接作業者はちゃんと理解していても、工事現場の他の作業者が理解していなくて現場に張っているホースなどを雑に扱ってしまいがち。
爆発限界が極めて広い
爆発限界という単語は、化学プラントに勤める技術者なら必須の知識です。
一般に燃焼範囲が広い方が危険性が高いと言われます。燃焼範囲が広い物質として水素が挙げられますが、これは4.0~75%です。アセチレンは燃焼範囲が2.5~81%です。最高クラスである水素よりさら広い燃焼範囲です。危険性が高いです。
- 化学プラントの化学系技術者はアセチレンガスを工事現場で使っている意識が低い
- 機械系技術者はアセチレンガスが化学物質の中でどれくらい危険かを理解していない
というケアが行き届きにくい分野に溶接のアセチレン問題があります。参考ですが、家庭でも使うプロパンガスの燃焼範囲は2.2~9.5%です。
発火点が低い
発火点とは着火源が無くても自然と燃える温度です。これと別に引火点という表現があります。これは着火源があった時に燃え始める温度です。
アセチレンは発火点が299℃です。水素で585℃、プロパンで466℃です。発火点だけで安全対策を議論することはありませんが、これだけでも管理を厳しくしないといけないことは想像できるでしょう。
直射日光から避ける
アセチレンガスはプロパンガスよりも圧倒的に燃えやすいです。直射日光でボンベは60℃~70℃くらいまで上昇する可能性があります。プロパンガスなら問題ないかも知れませんが、アセチレンガスでは60~70℃は危険だと考えるべきです。
溶接で使うアセチレンガスも、プロパンガスと同じ感覚で使う施工会社が居るのか問題です。どちらも同じボンベの形をしているからですね。
自己分解しやすい
アセチレンは自己分解しやすい物質です。三重結合は自己分解しやすいと無条件に覚えこんでいいくらいのレベルです。衝撃を加えると自己発火・爆発する性質があります。それくらい不安定で内部にエネルギーを持っているので、溶接のエネルギーとして活用するということですね。
アセチレンガスをボンベに貯めこむためには、アセトンやDMFに溶解させています。接触面積と溶解量を稼ぐために多孔質物質を充填しています。充填物と気液接触の世界です。
銅・銀と接触を避ける
アセチレンは銅や銀と接触するとアセチリドを作ります。これがまた非常に危険。著しい爆発を起こします。
化学プラントでは近くに銅管トレースがある場合は、特に注意しましょう。化学物質で三重結合がある場合も、同じようなケアが必要です。
参考
プラントの生産技術系エンジニアなら溶接の知識は多少なりとも必要です。溶接の世界も非常に奥深いので、深く知りたい方は以下のような書式から始めると良いでしょう。
関連記事
溶接についてさらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
最後に
化学プラントで溶接・溶断に使うアセチレンには、燃えやすさ・高熱供給・広い燃焼範囲・低発火点・自己分解のリスク・金属接触による危険性と、さまざまな特徴があります。現場ではこれらを正しく理解し、安全に扱うことが不可欠です。エネルギー効率だけでなく、安定性や危険性にも注意して作業を行いましょう。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
この記事の内容を、あなたの職場・キャリアに合わせて整理したい方に技術・キャリア相談を行っています。海外プラント、製造管理、組織の病理、キャリア停滞など、あなたの状況に合わせて具体的にアドバイスします
→ 技術・キャリア相談はこちら
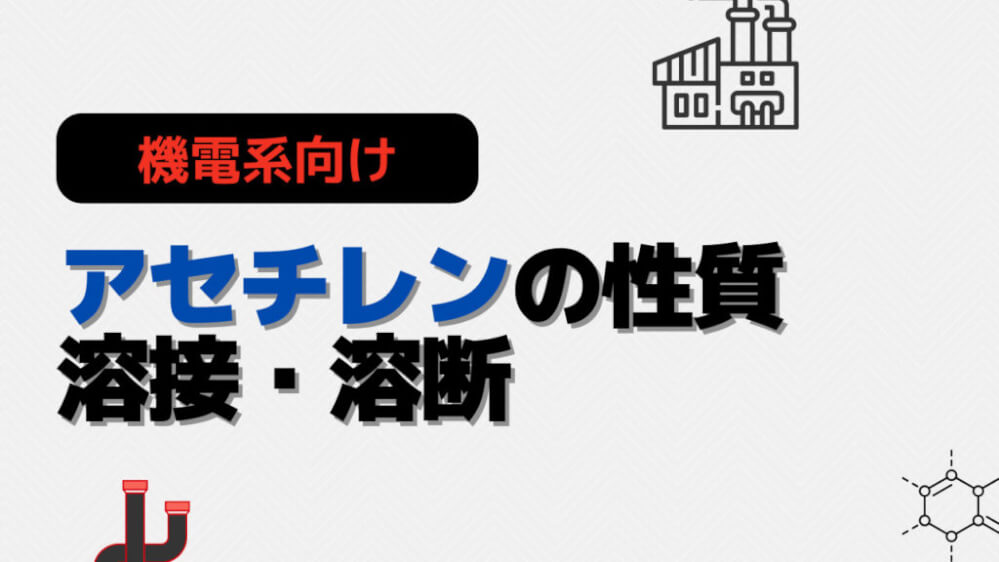

コメント