日本の製造業はこの10年くらいを見ると、非常に大きな変化が起こっています。リストラが分かりやすい例ですが、化学業界でも石油化学で再編が話題になっています。
私は石油化学系の仕事ではなく、他人ごとのように考えていました。ところが、最近はようやく「これはちょっとまずいのでは・・・」という危機感を覚えだしました。化学関係といっても様々な分野がありますが、将来が見えない分野もあるでしょう。
本記事では、なぜまずいのかを機械系エンジニア目線で語ろうと思います。私が良く取りあげる、オーナーズエンジニアの能力に関する問題とは別次元の話です。
この記事は、業界再編シリーズの一部です。
三菱ケミカルの希望退職に対して思うこと
住友化学も人員削減へ:三菱ケミカルに続く構造改革の波
プラントオペレーターが余る時代が来る?― 現場の人員過多とその影響を考える
化学プラントの設計職場で起こる窓際族問題を考える
オーナーズエンジニアの設備設計は将来性があるか?
化学工場の付加価値はどこにある?──各部署が抱える現実と構造的な価値低下を考える
化学プラントでアウトソーシングされる部門とは?その理由と人材の特徴を解説
リストラは突然起きない:実行前に社内で必ず現れる前兆とは
業績好調でも危ない会社のサイン:黒字リストラの裏側にある構造的課題
コモディティ化で起こっていること
石油化学の世界ではコモディティ化は良く知られていますが、少し離れた分野ではほとんど聞いたことすらない場合もあります。他人ごとでないということを理解するためには、コモディティ化の中で起こっていることを考えると良いと思います。石油化学に限らない課題が見えてきます。
反応プロセスの均一化
化学の反応という力を使って製品を作るプロセスは、例えば機械の製造プロセスと同じように「現状考えられる最適なプロセス」が採用されます。機械の場合でも、他社が真似をしようとしても、外見が同じで中身が違うというケースは珍しくないですよね。いくつかのプロセスが考えられますが、よりよいプロセスを探すのは製造業の使命の1つです。
ところが、無制限にプロセスを見つけられることはなく、限界があります。探し続けていくうちにこの限界点に到達してきます。
化学の場合でも同じです。最も最初にこの限界点に到達するのが石油化学系というだけの話。連続プラントで生産されるものは大量生産をしたいもの。真っ先にプロセス開発がされます。反応プロセスもバッチに比べて単純で、プロセス面での差がなくなってくるとコモディティ化に繋がります。
自動化による品質均一化
自動化したプロセスはとても楽で、製造オペレータはとても望むものでしょう。ところが、これがコモディティ化に繋がっています。
日本の製造業は、匠の技で言われるような手動で超高精度の質を作ることを良しと考えている節があります。ニュアンスは少し違いますが、「現場が大事」「工場が大事」と言っていることも背景にはこの考え方があると思っています。
自動化は化学の世界でも進んでいっています。自動弁を取り付けていく中で、手動に慣れているベテランオペレータからはさまざまな批判が出ました。
・運転時に危機感を覚えなくなる
・運転条件に応じた対応ができなくなる
・失敗したときに原因が分からなくなる
どれも主張は真っ当なもの。それでも自動化を進めていかざるを得ないのは、例えば労務費の削減(今では人が集まらないという問題)、生産速度の向上などが大きな理由です。
自動化はバッチプラントでも進んでいます。何も先進国だけで進んでいるわけではなく、例えば中国などでも新工場は自動化が活発に進められています。
この結果、自動化レベルの差がなくなっていき、コモディティ化に繋がります。自動化をすればオペレータの技術力の優位差がなくっていきます。
コスト差が明確に
プロセスが同じで、自動化程度も同じとなると、得られる品質も同じになってきます。そうなると、「どこで作るのが最も安いか?」ということが話題になります。
- 原料費
- 廃棄物処理費
- 加工賃(単価)
この辺りが鍵になってきます。
原料費は安い場所から調達することを考えると、輸送費の差(工場の立地条件の差)が効いてきます。廃棄物処理費は、安く処理できてしまう場所が有利になります。加工賃も単価の安い場所が有利になります。
プロセスで差がない以上、単純に安い場所が有利という当たり前の結果になります。
進むべき方向性
価格で勝負できないことが分かった後、どういう方向性に舵を取ればいいでしょうか。最近、私が良く考えていることです。
スリム化の覚悟
最初に必要なのスリムと思っています。これはいきなりリストラという話ではなく、いつでもリストラできるように各種整備をしていくことを考えています。
日本では正社員のリストラがとても難しく、安定的に採用をしている中で気が付いたら価格競争力の無いプラントがでてきて、そのプラントを閉じるまでに膨大な時間を掛けているうちに、定年して自然に減少するケースが多いです。
単純に石油化学が最初に話題になっただけであって、他の分野でも同じ展開が続きます。決心する人も、問題に直面して初めてどうしようか考えだして、数年経って任期が過ぎるのを待つ。その間は、その場所で作っても高い製品になることを分かっていても、作り続けないといけない。リストラや配置転換がいつでもできるという環境でなければ、早期の転換ができず競争力がますますなくなっていきます。
人のスリム化と同じように、プラントのスリム化も大事です。何でも作れるマルチプラントを目指すか、専用プラントをスクラップ&ビルトするか、という選択が1つの鍵。プラントを建てる瞬間に決まってしまうのですが、40年以上先まで響く問題となります。
高付加価値へのシフト
世間一般には高付加価値へのシフトが言われていますが、これは実はかなり難しいと思います。もちろん取るべき方向性としては間違っていません。
というのも、これまで担当していた業務とは全く違う分野の業務に適応できる人がどれだけいるか、が最大の課題になります。弊社の場合だと、同じ分野の製造でも生産品目が少し違うだけで対応できなかったりします。A生産では超ベテランの人でも、B生産を担当すると素人。本人の能力や教育環境の問題以上に、年齢や製造プロセスの複雑さなどの問題のような気がします。
化学の場合、高付加価値となると別分野へのシフトがイメージしやすいです。同じ分野のプロセスですら抵抗感があるのに、別分野に新たにチャレンジしたいと思う人がどれだけいるでしょうか。
この結果、事業や分野が変わっても変化が少ない「間接部門」への異動が進みます。もともと間接部門であった人たちとの競争。多くは管理職です。
窓際管理職に代表されるように、管理職であっても簡単に配置を変えることができないと、結局は人が減らないのでコストは変わらない結果になります。スリム化が大事だと改めて思います。
ソリューションの提案
ソリューションの提案も1つの方法です。これは、他社に製造を委託するという方法が分かりやすいです。安い国で作ってもらって、その指導をするという方法。
これは実は相当影響範囲が広い話です。製造方法は任せるけど、品質と数量を一定の価格でありさえすればいい。化学の場合でも、他社に委託するとなると自社の製造ノウハウはあまり求められなくなります。
工場で「改善」という名のもと技術力をいくら積み上げても、実は他社では使い物にならないノウハウだった。こんな可能性は十分にあります。そもそも規制が厳しく投資も厳しい日本では、工程変更の範囲が小さく、製造プロセスにおける改善が発揮できる場面が少ないです。決められたレシピ通り作る。これでソリューションが提案できるかというと、難しいでしょう。
では、プラントエンジニアリングはどうかというと、こちらもまた厳しい。オーナーズエンジニアは「特定の業界に特化する技術を持ったプラントエンジニア」という表現はできます。さらに厳しく言うと「特定の会社でしか使えない技術を持ったプラントエンジニア」です。
例えば、自社の製品を安価な国で作るために自社のエンジニアを派遣するという可能性が、どこまであるでしょうか?作る予定である国では、一定のノウハウがあってその国の人にあったオペレーションがありそこに適合するプラントがあるはずです。
自社のエンジニアが「我々はこうしてきた」と高品質を要求していると、実は対象国ではオペレータにとっては分かりにくく、問題があったら対処もできず、しかもコストも高いという結果が起こりえます。しかも、決心するまでに時間が掛かるかも知れませんね。
それなら、専門のプラントエンジニアに任せた方がいいのでは?という選択肢が出てきますね。
参考
関連記事
最後に
化学業界における「コモディティ化」は、石油化学の連続プラントだけの話ではありません。バッチプラントでも、同様にプロセスの均一化が進み、評価や技術の優位性を失っていきます。
これからの日本の化学業界は、スリム化の覚悟、高付加価値へのシフト、ソリューションの提案を早急に考える必要があると思います。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)X(旧Twitter)のDMでも可能です。
- 設備設計で悩んでいる
- トラブル原因の考え方が分からない
- 若手の教育方法に困っている
など、幅広くお受けしています。
*いただいたコメント全て拝見し、数日中に真剣に回答させていただきます。
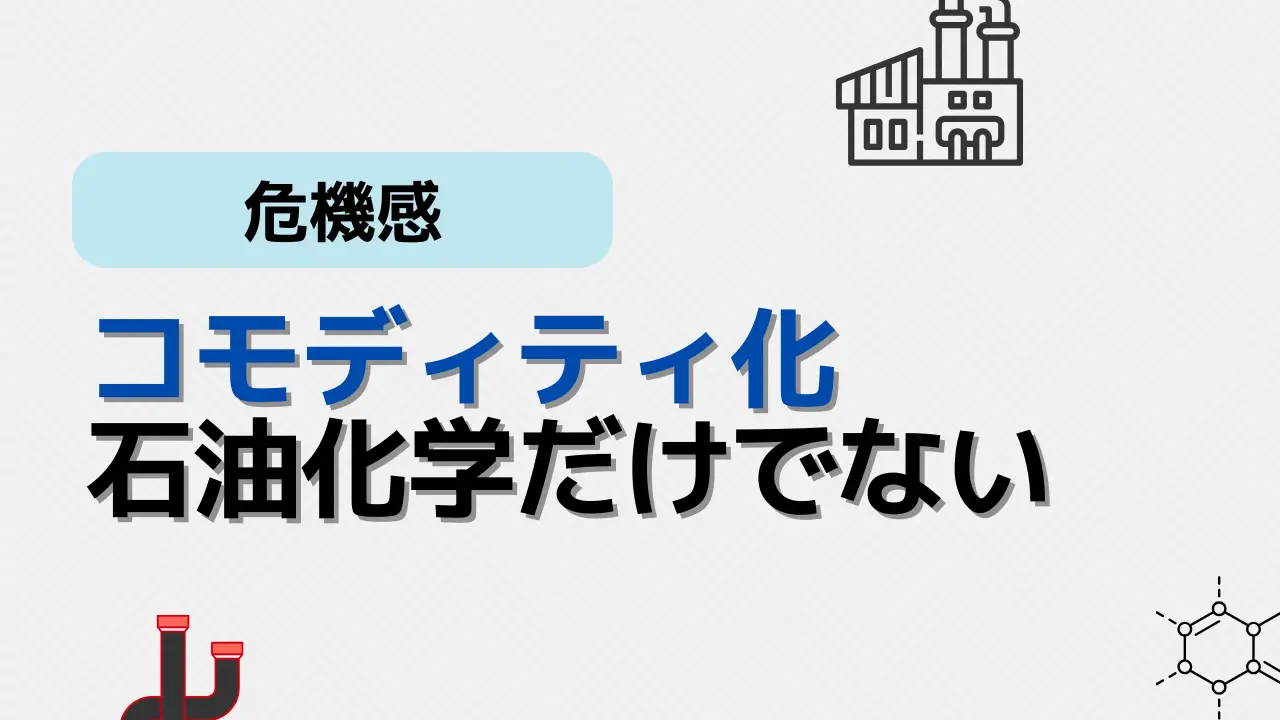

コメント