化学プラントにおける若手化学工学系エンジニアの成長速度には、部署ごとに大きな差があることをご存じでしょうか?多くの場合、製造管理と生産技術という2つのキャリアパスがあり、特に生産技術に所属するエンジニアの方が成長が速いと言われています。
本記事では、その背景にある理由を詳しく掘り下げ、依頼量や責任範囲、教育体制、時間管理といった観点から、なぜ生産技術が成長のスピードを上げやすいのかを解説します。これからのキャリア形成に役立つポイントをお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
新入社員を製造管理と生産技術のどちらにするかは、会社によって違うかも知れませんが、同じ会社でも時代によって意見が分かれる水物です。結局は人によるかもしれませんが、組織の環境の違いは1つの要因になるでしょう。
依頼する側は知識と自主学習が大事
製造管理も生産技術も、多くの部門に依頼することが多いです。
依頼は知識を習得するチャンス
依頼先が多ければ多いほど、成長するチャンスに恵まれています。
というのも依頼をするという言語化をするためにはそれなりの知識が必要ですし、結果を理解するためにも知識が必要だからです。
受注者側が気を使って、依頼主側が分かるような表現をする場合もありますが、大抵は専門的な表現になるでしょう。
そうすると勉強します。知識が広がっていきます。
製造管理の方が依頼量は多い
依頼の量という意味では、製造管理の方が生産技術よりも圧倒的に多いです。
であれば製造管理の方が成長は速そうですよね。
これは管理者でもリーダークラスに限定されます。
製造管理職の担当者は、製造に関する一部分しか仕事を担当しません。
他部署に依頼する量は限定的です。
生産技術は製造管理よりも全体としての依頼量は少ないものの、一人当たりの依頼量は多いです。
プロジェクトが多いと製造技術として依頼する機会が増えて、成長速度が上がりやすくなります。
一担当としての責任が重い
生産技術は一人の担当者辺りの責任が重たいです。
製造管理の場合は大勢の人数でその責任を分担し合うので、精神的には若干楽です。
責任が適度に重たいと、成長速度に良い意味で効果的です。
教育係の有無
製造管理は教育係が意外と少ないです。
年齢層のバラつきが大きい組織であるほど悲惨。
製造管理の方が人は多いけども、メンター的な要素が強くて教育担当者の割合が低め。
生産技術も教育係が少なくなっていますが、組織の割合的には製造管理の方が厳しい条件です。
学ぶ範囲が広く教育係も少ない製造管理は、成長する場として疑問符が付くと感じませんか。
現場で教えてもらう機会
製造管理だと現場で学ぶ機会は多そうに見えますが、人が少なくなっている現在では、よほど積極的に教えを請わない限り、現場で1:1の教育を受けることは難しいでしょう。
現場という最大のメリットが活かされてないのは、なんともったいない……
生産技術の場合、現場に行くときは1人よりも誰かと一緒のパターンが多いので、勉強できるチャンスはあります。
(生産技術でも受け身な人は、現場でも何の質問もせずに立っているだけで学習しなかったりしますが)
自分でコントロールできる時間の差
製造管理は自分でコントロールできる時間が意外と少ないです。
自分で頭を使って考えて学習していく時間が必要なはずなのに、朝礼や各種会議に参加することで時間が奪われていきます。
これらの会議は学習という意味で必要ではあるものの、本業を奪うという意味では成長速度に差が出てしまいます。
分からない状態で会議に参加して、会議中も会議後も質問ができず、分からないまま。
こうなると時間を消費しているだけですね。
生産技術も製造管理からの呼び出し・製造管理との会議など時間的な制約は発生しますが、頻度は少なめです(生産技術にいる人は多いと感じるでしょうが)。
参考
関連記事
プラントの製造管理や生産技術についてさらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
最後に
化学プラントにおいて、同じ若手エンジニアでも生産技術の方が製造管理より成長速度が早い理由は以下の通りです。
- 生産技術の担当者は依頼量が多く、実務経験が豊富
- 教育体制は生産技術の方が現場学習の機会に恵まれている
- 自主学習や考える時間が確保しやすい環境である
- 一担当としての責任が重く、成長を促すプレッシャーがある
キャリア形成の際には、これらの環境差も踏まえて自身に合った部署選択を検討すると良いでしょう。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
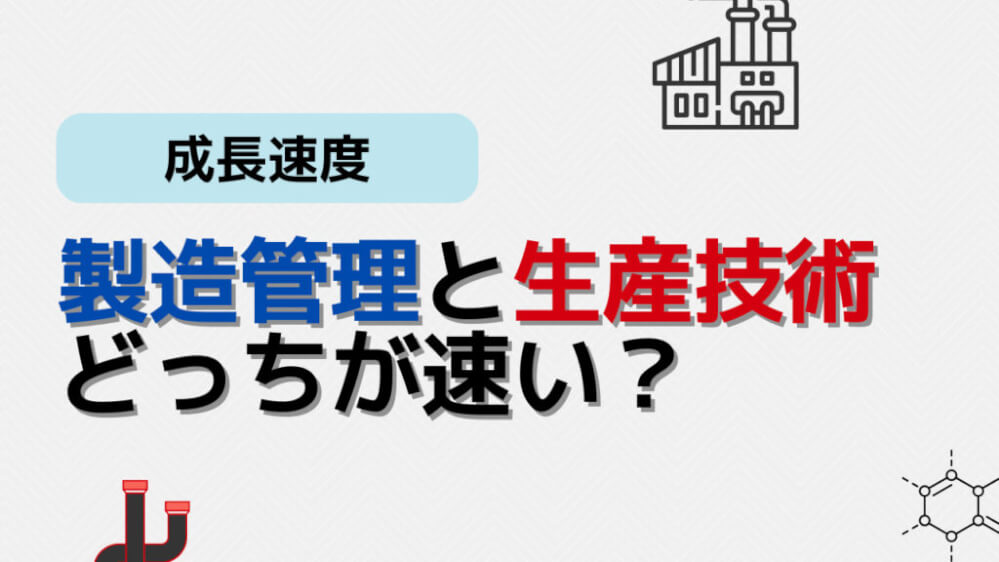

コメント