保安設備について解説します。
化学プラントの安全を保つために技術的にどんな処置をしているかをまとめてみました。
化学プラントって怖いですよね。
何しているか良く分かりませんから。
地域住民の立場だとそう見えるでしょう。
これは工場の人間も良く知っています。
工場を安全に維持するためにさまざまな方法を取っていますが、その対策が十分に知れ渡っていないことも。
保安装置
化学プラントの保安装置としては以下のようなものがあります。
- 防火壁
- 消火設備
- 防油堤、油流出防止装置
- 除害装置
- 保安電力、感震装置
- 緊急遮断装置、インターロック
- 監視計器
- 窒素
分かりにくいでしょう。数が多いとどうしても分かりにくいもの。これをいくつかのグループに分けてみましょう。
- プロセス内の原因で事故を止める仕組み
- プロセス外の原因で事故を止める仕組み
- 事故が起きた時の歯止め
事故は化学プロセスで起こると思うでしょう。当然です。
このために監視計器やインターロックなどの安全対策を取ります。そもそも事故のもととなる爆発性雰囲気ができないように窒素をふんだんに使います。これらの対策が第一の壁となります。それでもこの壁はいつかは破られます。
自然災害例えば地震は良い例ですね。地震で電気が止まって設備が動かなくなって大きな事故が起きましたよね。地震の対策や電源の確保などが第二の壁となります。この壁も越えてしまったら、危険物は流出します。
それを止めるための第三の壁が、除害装置や防油堤。除害装置はガスの流出を、防油堤は油の流出を防止するものです。この流出が続くと火災爆発に至ります。
これを防ぐために防火壁や消火設備があります。工場で事故が起きた時に消防車が来ますよね。テレビで見かけます。あの状況になるまでにはいくつもの壁があるのだということが分かればOKと思います。
監視計器
化学プラントの事故を防ぐ第一の壁。それが監視計器です。プロセスに使う計器だからプロセス計器とも言われます。
- 液面計
- 圧力計
- 温度計
- 流量計
- pH計
液面計、圧力計、温度計はプロセスの危険性を直接示します。
- 液面が大きいと、危険物の量が大きく燃えた時に大事故に繋がります。
- 圧力が高いと、漏れた時に勢いよく爆発する方向になります。
- 温度が高いと、物が燃える可能性が高くなります。
流量計やpH計は間接的にプロセスの危険性を示す可能性があります。
- 冷却水の流量が流れていないと冷却できていなくて温度が上がる
- pHが低いと不純物が増えて暴走する
プロセスや設備の条件によるので、これだけを見ても危険かどうか即断しにくい指標ですが、プロセス計器としては重要です。
圧力開放装置
プロセスが危険であるかどうかを示す中でも圧力はとても大事な要素です。高圧・負圧いずれも危険ですので、それぞれ対策が講じられています。
- 安全弁、安全板
- 逃し弁、リリーフ弁
- 液シール
- ベント、ブリーザー
それぞれ専門用語っぽいですよね。安全弁や安全板は圧力が高くなったときにそこから圧力を開放するための装置です。圧力が上がっていくとそのうち装置が壊れます。大事故です。そんなことにならないように代わりに壊れるのが安全弁などで、安全弁が壊れることで圧力を維持できずに逃がすことができます。
逃し弁やリリーフ弁も同じです。安全弁や安全板がガス用で、逃し弁やリリーフ弁が液用と用語を使い分けていたりしますね。
液シールはタンク内を一定圧力に保つために使用する古典的かつ原則的な保安装置です。非常に多く使います。簡単です。安いです。液として水を使うことが多いでしょう。水シールは安心感が強いです。変に計器に頼るよりは水シールのような原理原則を使ったプロセスを大事にしたいですね。タンク以外に除害装置や真空装置などいろいろな場面で水シールの原理を使っています。
ベント・ブリーザーも液シールと同じようにタンクの安全装置です。タンク内が加圧にも負圧にもならないように、大気とタンクを接続するラインです。ガスラインなんて言い方もします。
緊急処置
万が一プロセスの異常が起きた時には、緊急処置をしないといけません。以下のような処置を取るのが一般的です。
- 動力停止
- 流体停止
- 冷却
- 窒素封入
- 流体放出
化学反応で異常があった場合は、とにかく原料の供給を止めて冷却する。この基本が守られていたら、大丈夫です。これって原子力発電でも全く同じ発想です。
動力停止とは原料の供給ポンプなどのこと。原料の供給を止めます。
流体停止もポンプという意味では同じ。動力停止にはポンプ以外に粉体や気体も含みます。
化学プラントではとにかく高温になると燃えたり爆発したりするものが多いです。原料を混ぜると反応熱が出て勝手に高温になる曲者が多いです。そのために原料を止めますが、これではダメな時があります。放っておいたら勝手に分解して高温になる厄介者がいるからです。そういうケースにも備えるように、速やかに冷却しましょう。
窒素封入は冷却手段の1つとして使うことがあります。ただし圧力が増える方向になりかねないので、注意が必要です。
流体放出はベントと同じ発想。しかしこれは、緊急処置でも最後の手段。先に原料の供給を止めて冷却することを優先します。
消防設備
監視計器は言葉どおり監視するのが目的です。監視している対象に異常が起きた時に、人に知らせる設備も必要です。これをまとめて消防設備と呼びましょう。この辺はビルマンションでも同じですね。
- 自動火災報知
- 漏電火災警報
- 非常警報
- 通報設備
- 通信設備
- 避難器具、非常灯
- 排煙設備
- 非常電源
この辺りは一般の建物でも共通するので、消防設備というカテゴリに入ります。消防設備士という専門の資格もあります。
火が出たらランプやアラームで人に知らせるのが、自動火災報知・漏電火災警報・非常警報など。
消防署への連絡のために通報設備。
逃げる人がコミュニケーションを取るための通信設備。
逃げる方向を示す避難器具。
火災で発生した煙を逃がす排煙設備。
火災で電源供給が止まっても消火設備を動かすための非常電源。
いろいろな対策を講じています。普段はほとんど意識していませんが、ビルやマンションもこういう対策を取っていますよ。その意味では大量の危険物を扱う化学プラントと同様に、不特性多数の人が集まる商業施設も結構危ないということですね。
消火設備
まさに燃えた火を消すための設備があります。消防設備の中に含まれますが、消火設備と呼ぶことにしましょう。消火器も立派な消火設備。
消火器・消火器具
消火器は家庭やビルなどでも見る一般的な消火設備です。消火器には、A火災・B油・C電気それぞれの区分に応じて使い分けをしないといけません。
消火器には、粉末・水・ガスの種類があります。一般には粉末消火器を置いていると思います。
化学プラントではABC消火器というA火災・B油・C電気すべてに対応できる消火器を設置しています。化学プラントではありとあらゆる危険物施設に消火器は必須です。
屋内消火栓・屋外消火栓
屋内消火栓は、学校やビルや商業施設などで見かけると思います。印象に残りやすいのは、押しボタンとアラームとランプがセットになって壁に建てかけられている装置です。この装置の下に、ホースが入っていて、火事の時にはそれで消火を試みようというものです。
ホースの長さ分だけ移動可能です。範囲は狭いです。消火器のように人が無制限に持ち運ぶことまではできません。化学プラントの生産現場ではほぼ必須のアイテムです。
スプリンクラー
少し安いビジネスホテルなどに泊まればすぐに分かります。天井にシャワーノズルのようなものが付いています。これがスプリンクラー設備です。火災が発生したら、広範囲に水を一気に供給する設備です。建物に固定しています。ノズルの向きによって360度全方位に噴霧可能です。
水噴霧
スプリンクラーと同じような装置ですが、化学プラント向けです。
これは水噴霧が、スプリンクラーよりも細かい水を全域に噴霧するから。スプリンクラーでは油火災を消すことはできませんが、水噴霧は油火災を消すことができます。有機溶媒を大量に扱う化学プラントでは水噴霧は非常に頼もしい消火設備です。
泡
泡消火設備も水噴霧消火設備と同じように使います。水噴霧と似ていますが、純粋な水ではなく薬液の入った水を使います。薬液が入った水を噴霧すると発泡します。この発泡の効果で火災を抑えます。
水噴霧消火設備だと多量の水を必要としますが、泡消火設備だと水量が少なくて済みます。消火設備の配管費用を考えると、昨今は泡消火設備一択となっています。
不活性ガス
不活性ガスは二酸化炭素や窒素を使って部屋の空気を無くす方法です。水を使えない電気火災に対して使います。化学プラントでは計器室や電気室ですね。
不活性ガスを投入すると人が窒息してしまうので、かなり厳重な対策をしていないといけません。最近も二酸化炭素消火設備関係の事故がありましたね。
ハロゲン化物
ハロゲン化物は不活性ガスと同じ考えです。ハロゲン化物の方が危険なので、化学プラントでは普通は使いません。
粉末
粉末も不活性ガス・ハロゲン化物に近い扱いができます。ただし、現実的には駐車場などに使用し、化学プラントではほとんど使いません。
スチームカーテン
スチームカーテンは火の延焼を止めるためのものです。化学プラントの屋外タンクで火が燃えたら消防車が水を掛けますよね。
あれって燃えているタンクそのものに水を入れるのではなくて、周囲のタンクに水を掛けています。周囲のタンクに火や熱が伝わって延焼するのを防ぐためです。スチームカーテンはあれをもっと広範囲にしたものと考えればいいでしょう。
二重化
二重化は非常に大事な考え方です。化学プラントで二重化というと、緊急時の処置が1つの方法だけでなく、複数の方法を持たせることを示します。
1つ壊れたからその機能が発揮できなかったでは許されないのが化学プラントです。
電気の二重化
装置を動かす動力源としての電気を二重化させます電力会社の電気が止まったからどうしようもないでは許されませんよね。
そこで非常用発電機を確保するのが普通です。これが電気の二重化。通常は商用電源を使って、異常時は非常用発電機を使います。異常時でも非常用発電機で最低限の機能だけを動かして、プロセスを安定な状態に移行させようとします。
空気の二重化
気が付きにくいですが、空気も二重化します。空気が止まると自動弁が止まります。自動弁が止まってしまって、原料の供給を止めたり冷却をするという基本ができないと終わりですね。
空気生成源を二重化させます。さらに、空気が止まったときに自動弁がどういう動きをするかも決めておきます。
空気が止まったときに自動弁が閉まる動きをエアレスシャット。開く動きをエアレスオープンと言います。そのままですね。
原料供給系や過熱系はエアレスシャット。冷却系はエアレスオープン。
この原則は頭に入れておきたいです。
圧力開放の二重化
圧力開放装置も二重化させることがあります。安全弁を1つ付けるだけというプロセスが多いですが、屋外タンクなどでは2種類の圧力開放装置を使います。
ブリーザーと水シールという組み合わせが最も楽でしょう。どちらか1つが正常に機能しなくても、他方が機能してくれるという意味で二重化です。
冷却の二重化
冷却源も二重化します。チラー水などの低温水を使って緊急冷却をするのが普通ですが、チラー水が止まった場合にも対応液るように、
工業用水や循環水をバックアップで持っておくことが普通です。
参考
関連記事
関連情報
最後に
化学プラントの安全対策について解説しました。
保安装置・監視装置・圧力開放装置・緊急装置・消防設備・消火設備・二重化など。
いろいろな設備がありますが、発想は常識的なものが多いです。
緊急時に必要な物なので、機能はシンプルに・壁は何重にもするのが大事ですね。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
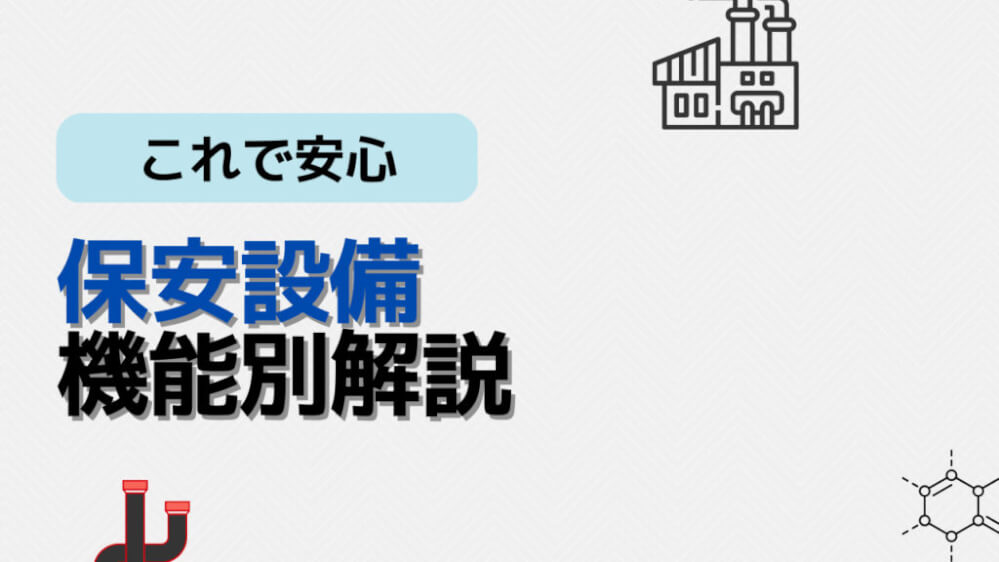

コメント