「2024年版ものづくり白書」は、日本の製造業の現状や今後の方向性を示す貴重な資料です。この記事では、化学プラントで働く機電系エンジニアの視点から、白書に記された課題や政策、実態について解釈し、現場の実感と重ねて考察します。
化学プラントの機電系エンジニアをしていると、目の前の事をこなすことでいっぱいにするこが可能です。そして、世間の情報を入手せずに、浮いた存在に。身の回りでもかなりそういう人がいます。避けるためにも、製造業情報としての「ものづくり白書」を読んだ感想をまとめます。
2024年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告)令和6年5月31日経済産業省,厚生労働省,文部科学省
https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2024/pdf/gaiyo.pdf
プラント関係にだけ着目しています。
この記事は、機電系エンジニア性質シリーズの一部です。
【妄想】AIで化学工場の機電系エンジニアリングがこう変わって欲しい
化学工場×データサイエンス:機電系エンジニアが直面する“現場とのギャップ”とは?
化学プラントの機電系エンジニアはどう評価されている?現場・本社・製造のリアルな視線
プラント建設が減る中で、機電系エンジニアに求められる力とは
機電系エンジニアの内面にあるこだわりと外から見た印象の違い
化学プラントの機電系エンジニアが陥る“予算感覚のバグ”:コスト意識の再構築が必要な理由
競争相手が少ない化学プラント機電系エンジニア
マンツーマン指導が減少する化学プラントの機電系エンジニア教育課題
専門性が高すぎる?化学会社の機電系エンジニアのジョブローテーションと職場環境の実態
設計と保全の違いと連携の重要性──化学プラントの機電系エンジニア視点
機電系エンジニアの業務実態:化学工場での典型的な1日の流れ
「化学工学の知識、機電系エンジニアに本当に必要?」—現場での実情を探る
視野の狭さを克服する!機電系エンジニアが知るべき標準化・パターン化のポイント
機電系エンジニアの狭い範囲で時代に残されないためにできること
転職で化学プラントに来た機電系エンジニアのキャリアルート3パターン
技術力が徐々に低下している|化学プラントの機電系エンジニア
働かないおじさんの典型3パターン|化学プラントの機電系エンジニア
視野が狭い化学プラントの機電系エンジニアが気を付けたいこと
なぜ機電系エンジニアは受け身になるのか?──若手・中堅・マネージャー全員に共通する“意識の低下”
機電系エンジニアが“抱え込み”やすい本当の理由──思考のクセと成長機会の損失
院卒・大卒・高卒まで幅広く機電系学生を歓迎する化学プラントの実情
図面と数値だけじゃ足りない!言語化ができる機電系エンジニアになる方法
化学プラントの職種別「1日の流れ」:機電系エンジニア・保全・製造部のリアルな時間感覚
機電系エンジニアの事務仕事実態:パソコン苦手がもたらす現場の課題
機電系エンジニアが化学プラントで直面する「分からない」11の壁とその乗り越え方
言語化で差をつける化学プラント機電系エンジニアの仕事術:設備情報・使い方・工事・運転を徹底解説
- 日本での製造が限界
- CX
- DX(P.5)
- ものづくり企業の人材育成(P.6~7)
- ものづくりに関する基礎的なデータ、施策等
- 製造業における人材育成の問題は、6割以上の事業所が「指導する人材が不足している」となっている。(P.19)
- 約8割の企業は従業員が身に付けた能力・スキルを実務で発揮するための取り組みを行っているが、配置転換やプロジェクトチームの人選まで踏み込む企業は限られている。(P.20)
- ①従業員の技能習得のプロセスを支援する「能力評価制度の導入」、「目標管理を通じた能力の棚卸し」や「個人ごとの育成計画の作成」などの環境整備が進んでいる。(P.22)
- ②身に付けた能力を実務で発揮するための取組として、「関連する部署・担当への異動・配置転換」や「プロジェクトチームへの人選の考慮」が進んでいる。(P.22)
- ③「昇給」や「役職等の昇進・昇格」をはじめとし、身につけた能力の処遇への反映が進んでいる。(P.22)
- 参考
- 関連記事
- 最後に
日本での製造が限界
今回の白書を見て、私が最初に思ったことです。
日本での製造は限界
表現はいろいろですが、全体を通じてそういうメッセージを感じます。
というのも、最近の私の業務でも業界を俯瞰する機会が増えてきて、実感しているからです。
- 日本での製造はこれから伸びていかず、海外に進出していかないといけない
- そのための仕組みと人材育成が必要
- 日本は一つのローカル会社
こういうキーワードは日常で頻繁に触れています。
それが白書にもちゃんと書かれていますね。
実は白書を毎年チェックしているわけではなかったのですが、23年度と単純比較をしただけでも、露骨にこの辺りの内容が書かれているので少し驚いています。
CX
最初はCXから
現状(P.2)
まずはP.2を見てみましょう。
目次のすぐ後のページで、早速やられました。
- 近年、国内投資の重要性が高まる一方、日系大手製造業の海外売上比率は20年間で急増し、過半を海外で稼ぐ構造に。また、従業員についても連結ベースでは6割が海外現地法人に従事。
- その結果、グローバルでの売上高は大きく拡大し、連結ベースで過去最高益を更新するも、利益率は低水準。事業規模が大きく、事業や地域が多角化するほど収益性が下がる傾向も見られる。
- → 多くの日系製造業では日本から海外現地法人に駐在員を送り込む一方、本国からのガバナンスはほとんどない「連邦経営」。企業グループ全体を上手くマネジメントできていないことが「稼ぐ力」に影響している可能性。
ここに書いてあることは首がもげそうになるほど、同意します。
安い労働力を求めて中国などに進出して20年以上。
気が付いたときには労働力の差はほとんどない状態になり、日本の方が安価となっている分野も増えてきています。
OKY(お前がここに来てやってみろ)に代表される、駐在員なら誰もが経験することが問題視されています。難のフォローもなく押し付けられて、成果がでないけど、撤退もしない。これが稼ぐ力に影響していると言うことは、何の違和感もありません。
日本国内で労働人口は減りつつ海外の力も使えていないので、収益が下がっていくという構図は、化学プラント関係でも非常に大きな問題になっています。
目指すべき姿(P.3)
P.3では目指すべき姿が提案されています。
- グローバル企業間で人材の獲得競争は激化。海外現法に従事する人材を含め、経営資源の最大活用を図るためには『日本+現法』という連邦経営から脱却し、国内・海外の組織がシームレスにつながる仕組みを整える必要。
- → これまで国内と海外とで分断され、個別最適化されてきたヒト・モノ・カネ・データに関わる共通基盤をグローバルで横串を通して整備していくことが必要。
表現は綺麗ですが、実施するのはとても難しいです。
人口が少なくなっている日本人に頼らず、海外の人に依存せざるを得ないということですね。
海外のキーマンを育てるという表現もないので、日本海外どちらも同じシステムを使い、誰がやっても同じ結果が出ることを期待しています。
多くの企業では、全社共通のシステムを自社製作ではなく外部購入しているのではないでしょうか?その流れが進んでいる会社は、ここを意識していると思われます。
少し前には住友化学で設備管理システムの刷新というニュースがありましたが、おそらくこれもそうでしょう。
日本人がグローバル人材として成長するシナリオには重きを置かないので、多くの日本人はグローバル企業の本国で働く人という位置づけから、グローバル企業の日本という1つのローカルで働く人、という位置づけに変わっていくと思います。
タケダはそういう雰囲気なのだと推測しています。
組合が強い日本企業でどこまで進めれるか、今後の注目ポイントですね。
DX(P.5)
DXは問題だけでお腹いっぱいになりました。P.5です。
- 製造事業者におけるDXは、依然として「個別工程のカイゼン」に関する取組が多く、「製造機能の全体最適※ 」を目指す取組は少ない。また、新たな製品・サービスの創出により新市場を獲得し、「事業機会の拡大」を目指すDXの取組は更に少ない。※経営戦略の遂行に向け、製造部門だけでなく、設計、開発、調達、物流、営業等の部門とも連携し、例えば、原価管理、部品表、工程表の一元管理等を行うこと。
- 産業データ連携については、欧州の自動車サプライチェーン(Catena-X)を中心に、個社や業界を超え、産業規模でCO2排出量等のデータを共有し、産業規模でサステナビリティや競争力強化を図る取組が進行。日本でもウラノス・エコシステム等の取組が始まっているが、産業データ連携への参加意向はわずかに留まる。
製造機能の全体最適を目指すことは非常に難しいです。
個別工程のカイゼンが多く、設備関係だけをとっても既存システムが自工程で使えるか(使えなければ採用しない)という流ればかり。
自工程の仕組みを変えて使えるようにしたり、前後工程含めた最適化を議論することができません。
設備関係を扱う機電系エンジニアが、化学工場では外様的な扱いになっていることも1つの要因でしょう。
同じように、開発・調達・営業なども分断化されています。
この課題に対して、一元管理をするために大きなシステム(例えばSAP)を使おうとしたら、とても使いにくく、かえって時間が掛かります。
同じく機電系エンジニアではExcelの扱いすら疑わしいもので、能力向上を望むのは非常に厳しいです。
であれば、全体最適による成果を期待しないで、別の方向を考える方がまだ健全なのでは・・・?とも考えています。
ものづくり企業の人材育成(P.6~7)
ものづくり企業の就業動向と能力開発の現状
- 中小企業における製造業の人手不足感※をみると、2020年に弱くなったが、2022年、2023年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前(2019年)より強い。
- 従業員の能力開発を実施した事業所の割合は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前の水準には戻っていない。
能力開発の取組と効果
- 能力開発を行っている企業のうち、経営面または人事面の効果を「実感している」、「やや実感している」とした企業は6割程度。その中で経営面と人事面どちらも効果を「実感している」とした企業(1割程度)について分析すると、能力開発周辺の仕組みの整備※に取り組んでいる割合が高い。
デジタル化に対応した人材の確保・育成
- ものづくり企業において、デジタル技術を活用している企業は、2019年は5割弱だったのに対して、2023年は8割を超えている。
- 中小企業のうち、デジタル技術の活用が進んだ企業は、2019年から2023年にかけて営業利益を伸ばしている割合が高くなっており、賃上げなどの従業員の処遇改善も進んでいる。
ものづくり産業における人材育成に係る主な施策
- 人材開発支援助成金により、雇用する労働者に訓練を実施した場合の訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成。
- デジタル技術を含む多様な職業訓練の提供、教育訓練給付による個人の能力開発の支援。
- 技能検定の推進、「団体等検定制度」の創設により能力評価の環境を整備。
ここで書いていることは、人手不足で応募者も少なくなっている製造業で人集めをするにはDXしか手がない、と読めます。
能力の高い人はデジタル関係も当然明るいので、そういう人たちを取り込むためにも会社としてDXに関する基盤整備が必要。競争です。
ただし、体感的にはデジタルが強くても現場に弱いというパターンが多いです。
デスクワークはできても、現場の実態を知ったりトラブル時に調整したりということができそうではありません。
今は残業代無制限の管理職がカバーする形で、表に見えにくいですが、そのうち部外からも露骨に見えるでしょう。
1つの会社として一定の水準での人材確保が難しく、分社化が進むと予想しています。それぞれの会社の範囲内でDXを進め、人材を確保していくということになるでしょう。
その結果、現場での調整がさらに難しくなります。
DXを進めないと生き残れないが、そこだけを考えればいいというわけではありません。(若い人からのDXに対する不満が出たときは、この辺の思考が抜けていると思っています)
現場軽視と繋がっていく流れで、日本で製造を続けていくことは諦めて別の方向性を探していくという流れでしょう。
ものづくりに関する基礎的なデータ、施策等
P.7までですでに情報過多となっているので、後は飛ばします。
P.18~22から気になった点だけを見ていきましょう。
製造業における人材育成の問題は、6割以上の事業所が「指導する人材が不足している」となっている。(P.19)
これは確かにその通りです。
- 管理職になったベテランは疲れ切っている
- 窓際のベテランは逃げ切り戦略
- 中間層を採用し、育てる風潮が無くなった
- 慌てて新人を採用しても、手遅れ
指導する人材が不足という一言が目立っていて、あたかも指導者が悪いように見えますが、問題は20年~30年前から起こっていることです。
もちろん若手に対する問題も書いてはいますが、指導者自身も犠牲者側。
誰が悪いという展開に持っていくと解決が遠のくと思います。
約8割の企業は従業員が身に付けた能力・スキルを実務で発揮するための取り組みを行っているが、配置転換やプロジェクトチームの人選まで踏み込む企業は限られている。(P.20)
これもその通り。
配置転換を真面目に考えて、かつ、成功した例を、私の身の回りでは経験したことがありません。
いつもその場その場の判断で転換。
何の専門性があるのか分からない、その会社でしか通用しない人材だと不満が出てます。
もっとも会社全体を知らないとDXなど全体最適を狙うことはできません。
そこが重要視されていないことが問題です。
機電系エンジニアのように配置転換が難しい職でも、プロジェクトチームの割り当ては1つのチャンスです。
ところが、これも時期によって変動があります。
プロジェクトが発生するかどうか自体が運に左右されるので、しっかりした教育計画とはなりません。
プロジェクトにアサインされてもそこで成長しない人も居ますし、個人の意識による部分の方が大きいとは思っていますが・・・。
①従業員の技能習得のプロセスを支援する「能力評価制度の導入」、「目標管理を通じた能力の棚卸し」や「個人ごとの育成計画の作成」などの環境整備が進んでいる。(P.22)
能力評価を体系的にしようという取り組みは、会社としては当然でしょう。
ただ、これはこれで問題があります。
機電系エンジニアの場合、プラント建設・合理化改造・保全などの大きなテーマに対して、評価を設定したとしても、経験しないまま年数を経過しやすいです。
例えば、ずっとプラント建設にだけ関わる人も居れば、ずっと保全だけに関わる人も居ます。
そこで不足している能力が分かったところで、今さら向上させることはできないと諦めてしまいます。
能力評価が設備ごとになされてある場合、例えばバッチでは蒸留塔は扱わないことが多いのに、蒸留塔周りの評価項目が低いということにもなるでしょう。
会社として一律の評価基準を作れば作るほど、地域差が目立つようになります。
その不足分を補う努力が配置転換しかなく、その配置転換もなされないまま放置されていると、何のための評価なのだろうと疑問を持ちます。
機電系エンジニアだけでも難しいのに、運転・プロセス開発・品質・合理化など様々な分野の人とレベル合わせをすることはもっと難しいでしょう。
現実的に、この能力評価で昇進を決めるのは難しく、結果的に年功序列システムに落ち着きます。
②身に付けた能力を実務で発揮するための取組として、「関連する部署・担当への異動・配置転換」や「プロジェクトチームへの人選の考慮」が進んでいる。(P.22)
これはどんどん進めてください。
個人的に気になっているのは、希望が叶って移動した人が叶わなかった人のことを考えないこと。
「僕は・私は希望してここに来た」
という主張が最近目立つようになっています。特に都会に異動したパターン。
その希望が叶って当然だというニュアンスです。
私のように、希望しても僻地で10年以上という人も居て、その人の目の前で発言するシーンを見かけます。
これが解決されないと、単に世代や運による格差が広がっていき、窓際を解消する方向には進まず、人材不足がますます進んでいくと思います。
③「昇給」や「役職等の昇進・昇格」をはじめとし、身につけた能力の処遇への反映が進んでいる。(P.22)
結局は、これが一番大事だと思います。
年功序列の昇進や、昇給額の差が少ない企業だと、努力の意味が無くなります。
適切な育成をしたら昇進するというわけでもなく、適切なスキルを習得したら昇給というわけでもない。
そういう仕組みで、モチベーションをあげようとすることの方が変だと思います。
参考
関連記事
最後に
2024年版ものづくり白書は、製造業における構造課題を浮き彫りにするとともに、変革に向けたヒントを与えてくれます。現場に立つエンジニアとしては、政策と実態のズレを意識しながら、自社の改善につなげる視点が重要です。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
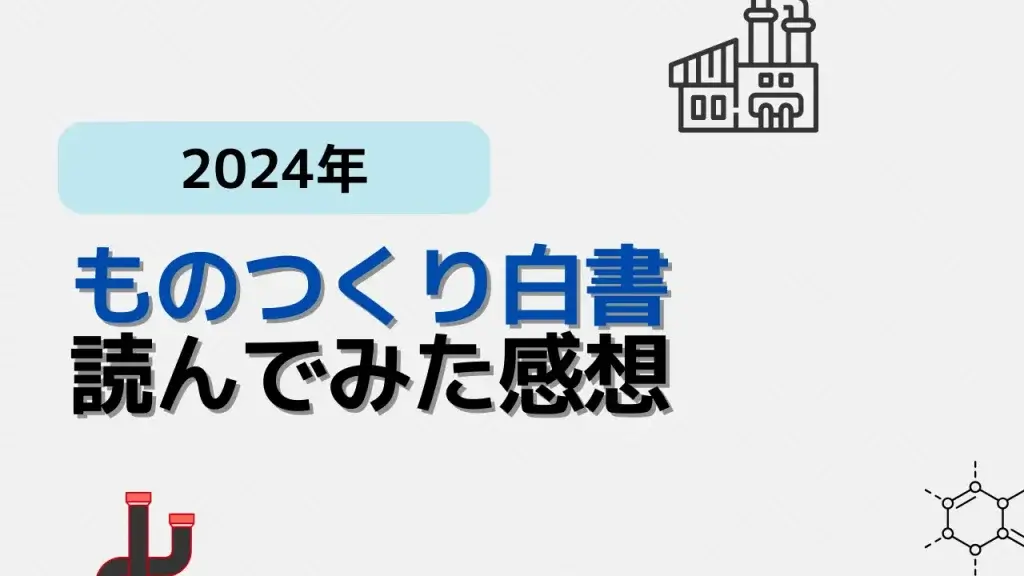

コメント