化学プラントでは「危険」という言葉に敏感になるのは当然のことです。特に「非定常作業」と呼ばれる、日常の運転とは異なる作業はリスクが高く、多くのトラブルが発生しやすい現場です。
本記事では、非定常作業の中でも特に注意が必要な4つの典型例について解説し、安全管理のポイントを分かりやすくまとめました。プラントの設計・保全・運転に携わる方は必見の内容です。
化学プラントは危険だというイメージはほとんどの人がお持ちでしょう。硫酸試薬が新幹線で漏れた事例でも、「大丈夫です」がとっさに出るのは、良く分からない危険な液に対する恐れを、抱くのが普通だからです。
良く分からない怪しげな物を作っている化学会社でも、危険がどこにあるかは相当真剣に考えられています。運転に関しては、マニュアル化や自動監視などの各種対策を手厚く取ります。それでも危険性が残っている作業は、「非定常作業」として取り扱います。
運転以外が怖い
化学プラントで定常というと運転です。非定常というと運転以外ですね。
運転以外の業務で、危険なものはどういうものか典型4パターンを解説します。
設備洗浄
設備洗浄は危険リスクが極めて高い非定常の作業です。
- 運転と同じ薬液が残っていて、量の大小の差はあるがリスクは残る
- 運転とは違う方法・ルートで液を扱う
- 配管やポンプを解放状態にして、液をかぶる可能性がある
- タンク内に入って窒息する恐れがある
現に、設備洗浄でのトラブルは非常に多いです。
マニュアル化も自動化も限界がありますし、解放しないといけないので危険リスクは残り続けます。
生産切替や工事をするために必要となる洗浄ですが、できるだけ実施したくないのが本音です。
洗浄すればその日数だけ、生産機会が無くなりますしね。
工事
工事も非定常の固まりです。
- 毎日作業内容が違う
- 火気、高所など人に直接被害のある作業が多い
- 作業員が現場に慣れていない
人だけは工事時期を上手く分散化させて、閑散期・繁忙期を無くすことで、同じ作業員に仕事をしてもらって慣れてもらうことは期待できるでしょう。
それでも工事規模が大きいと、不慣れな人に仕事してもらわないといけないので、リスクは残ります。
危険作業自体は作業員は慣れていますが、プラント環境が日々変わるのでリスクも変わり残り続けます。
この管理がオーナー側にとって神経を使う部分です。少なくとも管理者層はとても気を使っています。
試製造
試製造も非定常の固まりです。
- 運転方法が確立していない
- 運転員が作業に慣れていない
初めてプラントで運転するという未知の領域の作業です。
関係者全員が力を合わせて、できることを最速で決定して実施していき、立ち上げていきます。
学校の文化祭と同じような雰囲気を感じれる、数少ない仕事です。
未知であるがゆえに、リスクは高いです。
とはいえ、それを見越して1つ1つ丁寧に確認していくので、トラブルは意外と起こりにくいです。
原料変更
原料変更も非定常の1つです。
- 運転方法はほぼ確立
- 運転員も作業にほぼ慣れている
- 他に関わる人が居ない(安全側)
小実験で予め評価したうえで実施しますが、未知の部分は残ります。
試製造よりは遥かにリスクが低いですが、関わる人も少ないので、リスクは残ります。
とはいえ、原料変更で危険になったという例は私は出会ったことはありません。
バッチ運転は非定常ではない
非定常と定常という単語を使ったとき、バッチと連続という2つの単語との違いが気になるでしょう。
定常と連続が結びついて、非定常とバッチが結びつくような錯覚を覚えます。
現実的にはバッチ運転も定常という扱いをしています。
運転方法は時々刻々変わるものですが、1バッチというローテーションをくりかえすので、定常という扱いができます。
シーケンス・マニュアルなど運転方法も整備が可能です。
連続運転ほどの定常感はないものの、非定常というほどではありません。
参考
関連記事
最後に
非定常作業は化学プラントで最もリスクが高い業務の一つです。特に設備洗浄・工事・試製造・原料変更の4つは注意深く管理しなければなりません。人や作業方法が変わる非定常は、日頃の安全意識と綿密な準備がトラブル防止の鍵となります。
安全なプラント運営のため、これらの特徴を理解し適切な対策を講じましょう。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
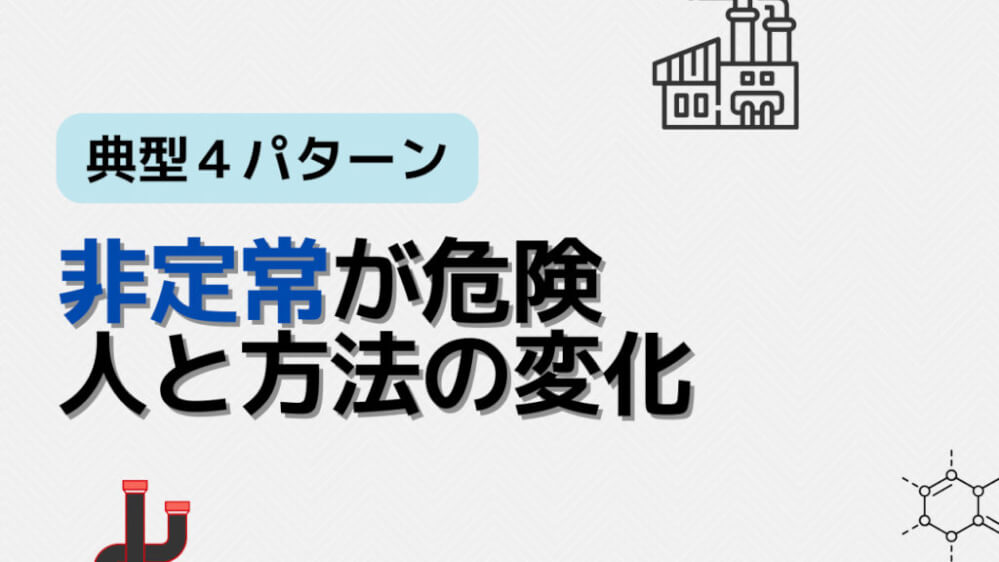

コメント