日本の製造業、特に化学工場では「問題が起きたら何かを足す」という“足し算の思考”が根強く残っています。一見、問題解決に向けた前向きな行動に見えるかもしれませんが、実際には複雑化・高コスト化・非効率化を招き、改善を阻む大きな要因となっているのです。
- 今までのシステム全体のどこが悪かったかは良く分からないが、ここが悪かったのは確か
- そこに対策を追加すれば、システムは良くなるはずだ
- 今までの取り組みの何かを減らすことは考えられない
本記事では、製造現場や監査、設備導入、ベンダー対応など、さまざまな観点から足し算思考の限界とその深刻な影響について掘り下げます。
この記事は、プラント設計(長期)シリーズの一部です。
将来用途を含めないプラントを建てた後の悲劇
プラント設計の最適化|プロセス面と設備面のバランスを考える
バッチプラントの特徴は特殊装置の性質で決まる|生産管理と設計のポイント
化学プラント建設は“立ち上げ”で終わらない!バッチ運転を見据えた設計の心得
スクラップビルドが化学工場の長期計画で大事な理由
オーナーエンジニアが知っておくべき“標準ユニット”の思想と実践
プラント設備をこんな風に標準化してはいけない
何か改善に取り組むことができない
製造部関係の話です。製造部では自部門での管理範囲内で、製造に関する各種改善に取り組みたいと思っています。現状より少しでも楽に作業ができると作業者は楽になります。今なら、退職者を少しでも減らすという喫緊の課題として位置づけられたりします。
ですが、製造の改善を判断すべき管理者がとても忙しいという問題が出てきます。何か改善しようにも検討に時間が掛かり、ワークライフバランスのために検討に時間を掛けることができず、各種依頼に回答することを優先佐是るを得ず、検討しようとしても積み上げられた各種の仕組みがハードルとなって採用できなくなります。安全上問題ないのか?という疑問が生じた瞬間に、改善がストップします。
このやり取りを続けていく中で、製造部としては現状維持が精いっぱいで、積極的に改善しようとするモチベーションを無くしていきます。
製造部が製造に特化した仕事ができるように。この号令は定期的に発信され、その瞬間は緩和されても、時間が経てば少しずつ依頼業務が増えていき首が回らなくなります。不思議なものです。その流れに飲み込まれる製造部としてはたまったものではないですが・・・。
多くの工数をかけた監査
監査関係では、足し算の論理で工数をいっぱいかけていくことになります。安全・環境・品質などテーマはどんどん細分化されて膨張していきます。
この対応が取れる部署は年々減っていっています。外目にはトラブルという形で見えてきます。なぜトラブルが起きるのだろう?という解析をしたら、システムの足りない部分を見つけようとし、底を足そうとする取り組みを続けます。
監査でも過去のトラブルに対する対策が取れているか、ということのチェックが増えていきます。首が回らなくなった事業所から順番に、評価が下がっていきます。
監査の評価を上げるために努力することは大事なことですが、内部で関わっている人からはこういう声が出てきます。
- この事業所に依頼するのは限界では?
- そもそも監査で管理すべき対象から外せないか?
監査がコストとして顕著になると、そのグレードを落とせないか?という検討が始まります。これが大きな会社だと自社で持つのかグループ会社にするのか委託会社にするのか、という露骨な流れになります。自分たちで自分たちの首を絞めていき、沈み行く船の中でどれだけ生き残っていけるか、という世界の話になっていきます。
監査というほど大きな話でなくても、現場で何かトラブルが起きれば色々な人が集まって審査会が開かれるでしょう。現場のパトロール回数が増えていきます。事務所での検討会議も増えていきます。
引き算ができるだけでも、寿命は伸ばせそうな気がしますけどね・・・。
高価な設備になる
足し算ばかりだと設備は高価になります。
- 少しでもリスクがあるとNGなので、高級材質にする
- 過去のトラブルを解決すべく、各所を自動化していく
- シーケンスを綿密に組んでいく
その工場目線では安全レベルを高めることができ、レベルアップした感があるでしょう。ところが、他社などと比較すると、レベルアップが必ずしもいいとは限りません。
レベルが高いから事故が起こるかというと、その関係性を知ることはできない。だからといって、できることをすべてするという論理は、自社では通用できても他社では通用できない。
ゼネコンなど大きなプロジェクトになると、開発が始めりレベルの違いが顕著になったタイミングで、納期が間に合わない・人手が足りないなどの問題に繋がっていきます。
自社で製造せずに委託会社に製造を依頼すると、安全やシーケンスに関するレベルを合わせることは不要で、それでも製品ができてしまうと高価なシステムを社内で構築することが無意味に見えてきます。この話は、社内の工場担当者の存在価値を脅かします。
過去の情報を活かすことができない
過去の知見が蓄積されればされるほど、その全容を知ることができずに活かせなくなります。機電系なら、設計情報や設備のトラブルデータが該当します。製造なら安全・環境・品質に関する現場でのトラブル事例、プロセス開発なら個々のプロジェクトで検討した設計情報などでしょう。
紙で膨大な資料になれば誰もみませんよね?サーバーにデータを格納することを仕組化しようとします。担当者は忙しくて入力をしなくなっていくでしょう。第三者に依頼して社内でデータベースを作っても、それを維持管理する人が必要ですし、作っていくほど種々のシステムが構築され、いちいち各lシステムを見に行くことができなくなります。
AIに調べてもらうという世界になれば、実は見落としがあるのでは?という不安を抱くでしょう(人が見ても見落とすというところは度外視して)。
導入に時間が掛かる
足し算を続けていって仕組みが複雑になれば、導入に時間が掛かります。
例えばある製造プラントで、何かの生産品目を追加したり現在の品目の合理化をしたりすることを考えましょう。これに必要な時間が1年以内というプラントと2年以上というプラントがあれば、どちらを採用したいと思いますか?
1年以内とは海外の委託会社で2年以上は国内の自社工場です。委託会社であれば、国内の自社工場のような膨大なシステムに取り込まれることなく、自由に動き回れます。となると、普通は委託会社に依頼しようとします。それでも国内の自社工場を採用しようとするなら、社内政治的な何かがあると考えられるでしょう。
設備に乗っかかっている機電系エンジニアとしては、自社のプラントを付かないとなると仕事場が無くなり大問題になります。
採用可能なベンダーが減っていく
足し算ばかりで要求事項が増えていくと、それに答えるベンダーは減っていきます。特に設備関係はこの罠にハマるでしょう。
私が入社したときには、要求事項は増やせば増やすほど設備の質が良くなる、といわれてきました。それは設備が40年持っていたものを41年に増やす程度の効果しかないものに対して、10社あるベンダーを1社に絞り込んでしまうような取り組みです。
原料関係でもベンダーを減らすことになります。製品だから仕方ないと思われがちで、同じ製品品質を維持するためにはこの原料でなければいけない、と盲目的になってしまいます。PLの話になってやむを得ないのですが、1社しかベンダーがなくてそのベンダーが生産中止になってしまったら則終わりというビジネスになってしまう可能性が十分に考えられます。
参考
関連記事
最後に
化学工場において、“足し算”による対応は一時的な安心をもたらしますが、長期的には改善不能の構造を生み出すリスクがあります。重要なのは、既存の仕組みや対策を見直し、不要なものを引き算するという思考です。複雑化・高コスト化・非効率化から脱却し、本質的な価値を見直す時がきています。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
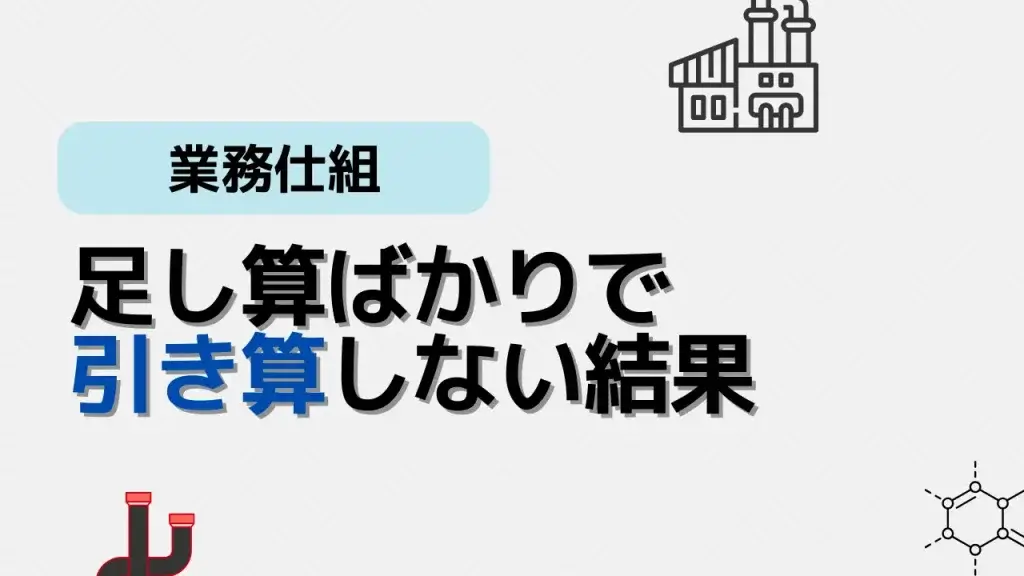

コメント