CADといえば3Dが当たり前という世界になってきたでしょうか。化学工場の配管設計でも3D-CADがを使う機会はゼロではありません。ただし、個人的には極めて機会が少ないと思っています。10年以上前から話題になっていても、実現ができない理由を少し掘り下げました。
過去に2Dと3Dの比較をした記事を作成しています。このアップデート版です。
この記事は、DX実態シリーズの一部です。
なぜプラントのDXは広がらないのか? 現場に潜む本当の壁
【化学プラントの現実】データ公開しても誰も見ない理由とは?
私の部署が経験した3Dスキャナー活用のリアルな壁
設備保全DX導入の現実:費用対効果評価の落とし穴と進め方
なぜDXが進まない?バッチ系化学プラントに残る「人が欠かせない理由」
設備保全のDXが進まない本当の理由:化学プラントが抱える根深い課題とは?
DXでは難しい日常点検、現場で求められる5感の力とは?
Excelと紙がプラントエンジニアの基本ツール
設備管理システム、導入したのに楽にならない?よくある7つの落とし穴
電話多用の背景を読み解く:保全担当がチャットより電話を選ぶ理由
プラントエンジニアが紙を使う理由とは?デジタル時代でも紙が欠かせないワケ
過去に考えていた問題
過去記事で考えていた問題を改めて考えてみます。
スキルが必要
3D-CADを使える人が少ない、という問題は依然と残っています。これはプラントエンジニアリング会社の課題ではなくオーナーズエンジニア側の課題です。
オーナーズエンジニアは自身もしくは委託先で配管設計を行います。そのマンパワーは非常に小さく、数人~10人レベルの世界。今までずっと2Dで仕事をしてきた人が、いきなり3Dに切り替わるには、とても強力なニーズが無い限り無理です。
3Dを使いこなすには一定のスキルが必要となるので、3D-CADが進まない原因となります。
環境整備が必要
3D-CADの環境整備は個人的には課題とは認識していません。2D-CADでも同じだからです。
現場での照合が難しい
3D-CADで作った配管図を現場に持ち込むのは難しいです。既存プラントでの増改築が多い会社ほど、3D-CADを有効に活用できないです。
2D-CADで書いた図面を紙に打ち出して現場に持っていく、というのはシンプルです。
オーナーズエンジニア側の課題
ここからは、過去に考えた課題以外の課題を掘り下げます。オーナーズエンジニアの立場と、オーナーズエンジニアが3D-CADに触れる数少ない機会であるプラントエンジニアリングの立場それぞれを考えてみます。
日常の補修改造を反映する仕組みが作れない
オーナーズエンジニアが3D-CADを使おうとしない最大の理由は、日常の補修改造工事だと思っています。
3D-CADは見た目が綺麗で分かりやすく積算などの付帯業務も簡素化できるという点で、メリットがあります。ところが、建設時にしっかり組み立てた3D-CADモデルは、日常補修であっという間に崩壊します。
配管が故障したり現場で応急処置的な対応をしたりすることは、プラント運転では当たり前。この都度、配管設計者に連絡してモデルを変更することは非現実的です。例えば夜間にトラブルがあって、配管仮設をして問題が解決したときには恒久対策として配管改造をしたりします。
これらの情報を配管設計者に伝えるということは、プラント運転者側にとってはとても苦痛です。早く問題を解決して次の課題に取り組みたいのに、連絡先が増えることは面倒でしかありません。
一方で配管設計者側からすると、運転側から適切な情報が得られずに困り果ててしまいます。
3D-CADでプラントの配管情報をデータ化できるという魅力的なメリットは、それを維持管理する人が居て初めて実現できることです。
・夜間にトラブルが起きない安定的な運転
・トラブル情報をタイムリーに情報共有できる仕組み
・配管改造の依頼を、図面レベルで指示できる人や仕組み
・3D-CADの維持管理が、プラント運転と同じくらい重要という認識つくり
上記はどれも相当のハードルがあります。組織の大きな改造が必要なレベルで、変えないと難しいでしょう。
既存工場への展開が難しい
3D-CADはプラント建設など、多くのリソースを割り当てる場合には可能です。問題は既存工場。既存工場を3D-CAD化するには、別にリソースが必要となります。
2D-CADから3D-CADに切り替えるという決心をする大きなハードルです。結果、既存工場は2D、新プラントは3Dと分けてしまうとCAD関係のコストが増えていきます。
既存工場の増改築がほぼゼロというエンジニアリングができるなら2Dから3Dに切り替えても良いでしょう。この場合、既存工場は以下のような条件が入っているはずです。
・既存製品を安定的に作り続ける
・既存製品の合理化をするメリットがない
・新製品を入れる必要性がない
・新製品を入れるにしても設備改造が不要
・既存工場の寿命がほぼない
多くの既存工場を動かしている中で、新工場が1つ入っただけで既存工場も影響が出るというのであれば、既存工場側は納得感が得られにくいです。
操作に対する過剰なこだわり
3D-CADを使うメリットとして、ユーザー側が自分のイメージを可視化できるということがあります。2Dで作った配管図を見ながら、頭の中でイメージできる管理者は非常に少ないです。結果、工事が終わってから「こんなはずじゃなかった・・・」と不満がでることは、過去に何度も経験しました。
でも、これって実は過剰な品質のための過剰なこだわりである可能性があります。
配管図を長年見て、その結果である工事現場を見て、運転員の操作方法もある程度見ていると、図面上でのこだわりは非常に強いと思っています。運転員が本当に不満を持っているなら、多少の投資をしてでも、工事が終わった後の次のSDMで改造をします。そんな例がほとんどなかったから、強烈な不満というほどではないと思っています(余裕があれば改造したいという程度)。
オーナーズエンジニアはオペレータが使いやすいようにするために、使い方を細かくヒアリングし、現場を調査して、時間を掛けて質のいい図面を作ろうとします。一方で、パソコン関係では全社を意図してか個々のユーザーには優しくない雑な進め方をします。これでもユーザー側は「みんなが使うから仕方がない」などとクレームを出すことはほぼないでしょう。これを考えると、配管の質が多少悪くても、クレームを出すことは少ないと考えれます。昔は、配管の立ち上がりが垂直でなくて少し斜めになっているだけでも、クレームが出ましたが・・・。
プラント建設のニーズ減少
3D-CADはプラント建設時に使うもの。こう割り切ったとしても、プラント建設のニーズは減少していくばかり。積極的に3D-CADを使うモチベーションが出てこないです。
エンジニアリング目線では、新技術を導入できず競争力が下がっていくことになりますが、3D-CADだけを考えて憂いても仕方ないと思います。
エンジニアリング会社側の課題
エンジニアリング会社側の背景も考えてみましょう。
ユーザーのニーズを把握できない
エンジニアリング会社にとっては個々のユーザーのニーズや使い方を把握することは、非常に難しいと思っています。多種多様な業界があって、実績のない会社での設計をすることは多いはずです。過去に実績があっても、10年以上前でユーザーの考え方が変わっている場合も。
このニーズを的確につかんで図面に落とし込む技術を、エンジニアリング会社は持っていないと思います。もともと持っていたか持っていなかったかは分かりませんが。
だからこそ、エンジニアリング会社は3D-CADを基本にしたいと考えます。2D-CADの技術者を抱える必要性が低いということですね。
作るだけが仕事
エンジニアリング会社にとってはプラントを建てることだけが仕事になります。オーナーズエンジニアの日常的な運用は視野に入れません。3D-CADでしか建設ができないエンジニアリング会社に依頼しないといけないオーナーズエンジニア。
ゲームチェンジ的な側面はありますが、プラント設計の技術力はそもそもCADの2Dや3Dの話とは別のもの。オーナーズエンジニア側がその考え方を変えざるを得ないと思います。(ということは、プラントエンジニアリング会社も知っていて欲しいですね)
配管図をデータとして保管する必要性
3D-CADで配管図を作る場合、プラントデータとして様々な用途に活用することを視野に入れがちです。しっかりしたデータなので、有効価値は高いように見えるでしょう。しかし、ここには落とし穴があります。
情報量が多いと使わない
配管図のデータがあれば、P&IDと連携させたり保全データと連携させることが考えられます。これを実現するには3D-CAD以上にデータの入力と維持管理が大変になります。P&IDと配管図なら、作成する人が似通っている場合にはある程度のコントロールは可能でしょう。配管図と保全データとなると、同じ人が管理する例は少ないので、データの入力の抜け漏れが出てきます。
これをしっかりしようとしたら、第三者がデータの維持管理をして、設計や保全上の情報を伝えるという仕組みが必要となります。これだけでも大変。
仮に上手くいったとしても、データが膨大になっていくことも問題です。アクセスするのが大変になり、目的の情報を調べようとしたら複数のボタンを選択することになるでしょう。これを面倒だと感じる人は多いです。結果、使われにくくなるでしょう。
データの一元化は作業効率アップを狙ってのことなのに、データの維持管理のために人が必要となると本末転倒、という話です。
図面と施工がそもそも一致しない
最後に、3D-CADの配管図が現場でその通りに作られないという問題があります。2D-CADの配管図でも同じです。微妙に高さが変わったり取り回しが違ったりするでしょう。
この情報をしっかり入手するのは困難です。工事会社から情報は来ません。CADオペレータが現地を確認することになります。ここには膨大な工数が発生します。そこまでして現場の情報をデータとして再現する必要がどこまであるでしょうか。
配管図だけならまだ良いでしょう。例えば計装・電気ダクトやコンジット管などの情報は、そもそもルート図程度しかないのに、CAD化することは工数アップに繋がります。
一度建設したら長期的に運転が約束されていて、しかも増改築がほとんどない、という理想的な条件でないと難しいと思います。
参考
関連記事
最後に
3D-CADは見た目や機能の面で魅力的ですが、化学プラントの実務においては課題が多く、特に既存工場や日常の補修改造対応では大きなハードルがあります。
オーナーズエンジニアとしては、技術的な理想だけでなく、現場の運用や組織体制まで含めて判断することが求められます。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)X(旧Twitter)のDMでも可能です。
- 設備設計で悩んでいる
- トラブル原因の考え方が分からない
- 若手の教育方法に困っている
など、幅広くお受けしています。
*いただいたコメント全て拝見し、数日中に真剣に回答させていただきます。
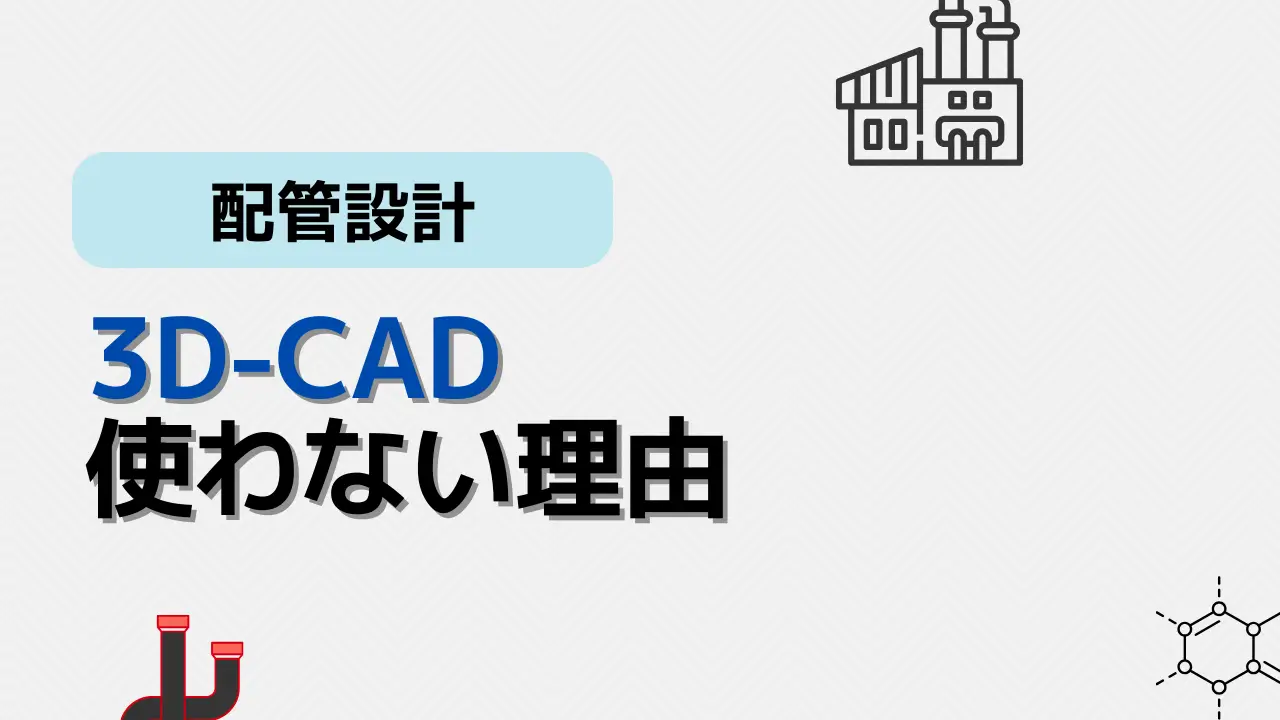
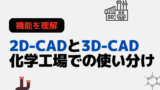

コメント