配管設計やプラントの計装設計に欠かせない「PID(配管計装図)」。この図面には多くのシンボルが使われており、それぞれが計測・制御機器を表しています。初めて見る方は「この記号は何?」「どうやって読むの?」と戸惑うことも多いでしょう。
この記事では、初心者でも理解しやすいようにPID配管計装図で使われる代表的なシンボルを一覧で紹介し、それぞれの意味や用途をわかりやすく解説します。これを読めば、配管計装図の基礎がしっかり身につきますよ!
この記事は、P&IDシリーズの一部です。
【バッチプラント入門】P&ID(配管計装図)の読み方|化学工場の現場で役立つポイント解説
切替ラインでP&IDが複雑になって管理が難しくなる理由
P&IDが一枚に書けなくなった時の分割するコツ
P&IDのラインスペックから見えてくるさまざまな情報
P&ID記号の基本|機器・配管・バルブの見方と実務での使い方を解説
The Engineering ToolboxのP&ID Templateを使ってみました
変量文字記号
P&IDには計器用の記号を書くのが普通です。計器用の記号をJIS Z 8204計装用記号において変量として定義しています。化学プラントでの計装用記号の使い方を紹介します。
JIS Z 8204 計装用記号
まずはJIS規格を確認しましょう。計装用記号は変量記号・変量修飾記号・機能記号の3文字から成り立つます。
変量記号
第一文字目である変量記号について、JIS規格内から化学プラントで使いものをピックアップしました。
| D | 密度 | Density |
| E | 電流 | Electricity |
| F | 流量 | Flow |
| H | 手動 | Hand |
| L | 液面 | Level |
| P | 圧力 | Pressure |
| Q | 導電率 | Quality |
| T | 温度 | Temperature |
| U | その他 | |
| W | 重量 | Weight |
ほとんどの文字は英語とリンクしていることが分かるでしょう。例外はQ:導電率と、U:その他くらいでしょう。Qは品質というカテゴリー内に導電率が定められていて、Uは多量の変数というカテゴリーに位置付けられています。Uはon-off自動弁に使うことが多いでしょう。
P&ID上でこれらの変量記号を見るだけで、どの計装機器であるかが一目で分かります。
変量修飾記号
二文字目である変量修飾記号を紹介します。
| I | 指示 | Identify |
| J | 自動走査 | JIdou? |
| Q | 積算 | Quantity |
これは数が少なく、例外も多いです。IはJIS上は二文字目に定めていません。Jはなぜ自動走査なのか、良く分かりません。Qは積算ですが、別にIntegralでよかったのでは?
疑問は残りますが、いずれにしろ「そんなものだ」という理解で十分です。ほとんどすべての計器はIかQを使います。Iが瞬時値、Qが積算値のイメージです。これだけで十分。
機能記号
三文字目である機能記号を紹介します。
| A | 警報 | Alarm |
| C | 調節 | Control |
| I | 指示 | Identify |
| Q | 積算 | Quantity |
| V | バルブ | valve |
| Z | 安全緊急 | – |
二文字目の変量修飾記号と同じくIやQが出ています。他にはいくつか文字がありますね。これらをまとめると、
- 一文字目の変量記号はかなり厳格
- 二文字目・三文字目は割とフレキシブル
であることが分かるでしょう。
P&IDでよく見るシンボル組み合わせ例
変量記号の組み合わせ例を見ていきましょう。
圧力
PIA
PIAだと圧力(P)を指示(I)して警報(A)を出す計器だという意味です。Aを付けるかどうかは、工場の思想によるところでしょう。PIと表記するだけでも良いかもしれません。
というのも圧力の指示計を付けるということは、圧力の大小がプロセスに影響がでるから。それなら警報を出した方が良いでしょうという意味ですね。ただでさえ、DCSではHH,H,L,LLのアラーム設定をすることができますからね。
流量
流量はP&IDシンボルの中で最も種類が多く、制御を左右する大事な要素です。
FQC
FQCは流量(F)の積算(Q)を調整(C)する計器です。流量調整をして積算もする素晴らしい流量計ですね。ここまでしていればバッチ系ではほぼ完ぺきです。滴下などに使います。
FIQ
FIQは積算流量の一般的な方法です。流量調整は必要でないけど、合計値は知りたいという場合に使います。
バッチでは運転開始時の溶媒や水の仕込など、毎バッチ行う一定量のフィードによく使います。所定の量が投入されて反応を行ったプロセス液を、どこか別の場所に送る時には流量計はあまり使いません。すでに量が決まっているからです。量が決まる前段階では、こういう積算流量計が活躍しているわけです。
FIC
FICは瞬時流量を調整するものです。積算流量よりもランクの低いものという認識です。滴下までではないけども、それなりに流量をコントロールしたいときに使います。例えばスチームの流量調整などが該当します。
温度
温度はP&IDシンボルでも、最も数が多いです。というのも、温度を表示したい場所が一番多く、簡単に表示できるからです。
TIA
圧倒的多数の温度計はTIAです。温度を指示するだけ。圧力計とほぼ同じ。温度の上限下限をDCSのアラームに設定します。
TIC
一部の温度計はTICとして調整機能を持たせます。スチームで蒸留させる場合などが典型例です。FICとTICを使うカスケード制御も良く使います。連続プラントなら温度についてはTICが一般的でしょう。
液面
LI
液面の大多数はLIです。上限に近くなればインターロックを掛けるなど、運転を止める方向になります。上限も下限もバッチでは工程ごとに設定するため多少複雑です。
- 工程開始時には液面がゼロでなければいけない
- 液を入れ終わった後に、次の液を入れるときには液面が一定値以下であってはいけない
- バッチ終了時には液面は一定値以下でなければいけない
工程ごとに判定条件が変わります。運転を安全に行うためにとても重要な機能です。
LIC
液面をLIC制御掛ける例はまれにあります。滴下送液をするときに、流量計でのFQCに加えて滴下タンクの液面で制御を掛ける場合です。メインの判定条件ではなく、サブの判定条件として使います。
その他
WIC
WICは重量を使った調整です。ロードセルを使った滴下反応で、ロードセルの指示値に応じて滴下量をコントロールする場合に使います。
液面が高いうちは弁開度が高いと大量に液が流れるため弁開度を絞ります。液面が低くなるとヘッドが低くなって液が流れにくくなるので、弁開度を開けて流量を確保します。滴下量を一定に調整したいけど、液面に応じて滴下量が変わってしまうのが厄介な点です。
FQCで制御した方が上手くいく場合もありますが、WICの方が確率的には高いです。
UJV、HJV
UJVはon-off弁のイメージです。その他多数のU、自動走査のJ、バルブのVを組み合わせています。XやVを使うケースもあるようです。
HJVも使うことがありますが、こちらは手動開閉でエアーを供給するon-off弁のイメージです。DCSから操作して開閉するわけでなく現地で操作。バルブの開閉の駆動力は人ではなくエアー。
バルブが大きいなど自動弁にしたいけども、手動作業がある場所なのでわざわざDCSに取り込む必要はないというケースです。手動作業が多いバッチならではでしょう。
参考
関連記事
最後に
P&IDの計装記号の表現ルールを解説しました。
PID配管計装図のシンボルは一見複雑ですが、基本の記号を覚えればぐっと理解が深まります。初心者の方も、この記事の一覧と解説を参考にしながら図面を読み解いてみてください。
配管設計や計装の現場で困ったときには、ぜひ何度も見返して役立ててくださいね。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
この記事の内容を、あなたの職場・キャリアに合わせて整理したい方に技術・キャリア相談を行っています。海外プラント、製造管理、組織の病理、キャリア停滞など、あなたの状況に合わせて具体的にアドバイスします
→ 技術・キャリア相談はこちら
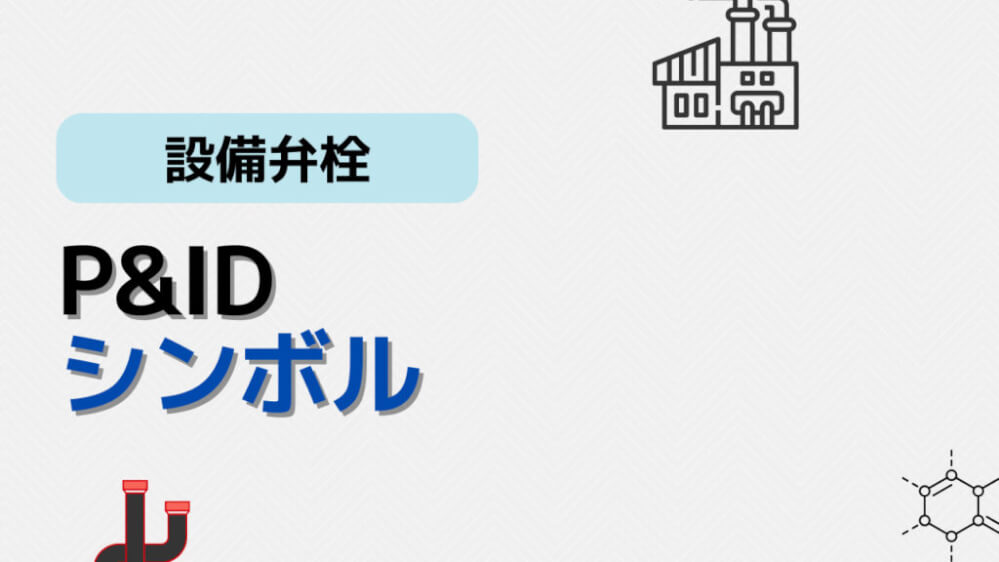

コメント