既存メーカーだけに依存していませんか。価格上昇、納期遅延、メーカー撤退リスク。調達環境が不安定な今、新規設備メーカーの開拓は避けて通れない課題になっています。
しかし、
「どこまで技術確認すればよいのか分からない」
「既存と同じ仕様でないと不安」
という理由で、具体的な一歩を踏み出せないケースも多いでしょう。
本記事では、製缶機器を対象とした、新規メーカー採用の進め方を整理します。
この記事は、設備メーカーシリーズの一部です。
人材不足とOJT任せの限界――化学設備業界の崩れる技術基盤
化学プラントで感じる“面倒なメーカー対応”の実態とは
エンジニアと設備メーカーがお互いに歩み寄ると効率化が進みます
フッ素樹脂ライニング製マグネットポンプのメーカー比較:設計と保全で選ぶ最適解とは?
GLメーカーってこんな感じ?私の正直なイメージ
設備トラブルの原因対策についてメーカーと打ち合わせするときの落としどころ
化学プラントにも起こりうる“対応の遅い設備メーカー”の3大問題とは?
製缶(タンク・熱交換器)のメーカー見積に対するユーザー査定
なぜ新規メーカーが必要なのか
化学プラントで使う設備は定期的な交換が必要です。プラントの建設や改造をするときには設備を多数購入することもあります。大きな工場だと全体を見たら毎年一定量の購入をしていることになります。
これらの設備のサプライヤーは、複数抑えておくことがユーザー側ではリスク管理として大事です。ユーザー目線だとサプライヤーの数が少ないと供給途絶の危険性があるので、複数のサプライヤーから購入できる体制を常に確保しておくことが大事。既存サプライヤーとの関係維持は大事ですが、新規サプライヤーとの関係構築を渋っていい理由にはなりません。
新規採用は製缶品が狙い目な理由
設備といっても様々な種類がありますが、私は製缶機器(タンクや熱交換器)がねらい目だと思っています。
失敗リスクが比較的小さい
製缶機器は失敗が起きにくい種類の設備です。連続系など厳しい環境であれば特殊性も出てきますが、バッチ系では条件が比較的穏やかな環境が多いです。
製缶機器は色々な工場で幅広く使われているので、新規メーカーといってもこれまでと全く違う設備になる確率は低いです。むしろ今までより良い設備になる可能性すらあります。
成功すると水平展開しやすい
製缶機器は世間で幅広く使われているので、1つのプラントで一度でも採用されると展開がしやすくなります。緩い条件から初めていき、徐々に厳しい条件の設備も採用していくという流れが理想的です。
製缶機器メーカーはいっぱいあると言っても、普段取引のある会社は多くはないはずです。最近はメーカーも倒産のリスクが高くなっているので、ユーザーとしては常に複数社から購入できる体制は整えておきたいものです。少なくとも製缶機器は1社購入という状況は避けたいものですね。
特殊設備は新規採用が難しい
製缶機器に対して特殊設備は新規採用のハードルが高いです。特殊設備は各ベンダーで毛色が違う部分があります。
こういう状況を知らない製造課などは、特殊設備だからユーザーのニーズを全部聞いてくれるはずだ、と勝手に思い込みがちです。結果、既存メーカーと同じ仕様を新規メーカーに押し付けようとして、採用ができないということもありえます。
特殊設備は使う側も良く分かっていないブラックボックスの部分があり、何か1つでも条件が変わると問題となりえます。問題が起きたときの運転面での対応をするのが面倒だから、既存と同じにしたいと主張する課長は、残念ながら一定数います。
結果的に、チャレンジするとしても製缶機器くらいだろうというのが私の実感。
自社スペックの棚卸
新規メーカーを採用する場合に、エンジニアが最初に実施することは自社スペックの棚卸です。
既存図面や仕様書から抜き取り
自社スペックを1つの情報にまとめているなら、それを使いましょう。これは実はそれなりに難しいことです。現実的には、既存図面や仕様書に書いてある情報をリストアップします。
複数のメーカーがある場合、それらの図面を並べます。図面でしか表現できない事項もあるでしょう。一度まとめてしまっても、新規メーカーを採用したらその情報もアップデートしないといけません。
社内の情報として膨大に図面や仕様書があっても、まとめる作業をしていない会社も多いと思います。これまでの経験で個々人の知識として蓄えられているだけで、会社や部署としての知識となていないかもしれません。ベテランですら、まとめた資料を見て初めて気が付くこともあるくらいです。
他社にも出せる程度の一般的な表現に加工する作業も必要です。
参考図面のチェック
新規メーカーは参考図面を出してくれる可能性があります。これは1つの情報源として有効です。
少なくともこのメーカーはNGと判定する材料となりえます。ただし、失敗しにくい製缶機器だと図面でNGという可能性は相当低いでしょう。
図面上では特に問題なくても、溶接とか仕上がりの部分で差が出る可能性があります。本当に気になる場合は、モックアップや工場見学などの対応を考えましょう。
プラントの本質的要求事項
当該プラントにとってどういう設備が要求されているか、意外と整理されていないものです。これはプラント設計思想に関わる深い話です。
既存メーカーとは何らかの条件差があるとして、それを許容するかどうかを判断する際にプラントにとっての要求事項に立ち返ることがあります。ここを避けた議論をしていると、新規メーカーの採用確率は下がります。良く分からないから既存と同じで・・・という展開ですね。
メーカー目線では、新規取引をする場合に若手に対してコミュニケーションをとっても上手くいかないと感じるかも知れませんが、内部ではこんな理由でNGとなるかも知れません。
生産体制・供給能力の確認ポイント
新規メーカーの情報として、生産体制のチェックはしましょう。図面など技術的な部分だけ見て採用を判断できるものではありません。
工場稼働とキャパシティ
工場の稼働についてヒアリングしましょう。製缶機器の場合は波が激しいので、安定しているかどうか・主要な顧客が他にいるか、といった定性的な情報は聞いておきましょう。
実際に購入しようとしたら、稼働がいっぱいで納期に間に合わなかったとか、1基だけなら問題なかったけど本格購入になったらキャパが追い付かなくなったということもありえます。
輸送(立地場所)
輸送もしくは立地場所については当然確認が必要です。納期の問題よりも、何かトラブルがあった時に駆け付けれる場所の方が有利です。
製缶機器の場合だと、設備の製作だけでなく工事もできる場合があり、現場での据付や付帯の配管工事まで担ってくれる可能性もあります。メーカーがプラントに近くにあるほど費用も抑えられるので、できるだけ地元を使う方が良いでしょう。
スケジュール管理能力
仕事の進め方という点でのスケジュールは確認が必要です。とはいえ、これは実務を扱わないと実態が分かりにくいです。
・見積ができる時間
・発注後、図面ができる時間
・図面の修正の時間
・製作開始のタイミング
・製作完了と完成検査のタイミング
新規メーカーであればいろいろなトラブルが起きることは当然と考えて、納期は余裕を持った方が良いです。この情報を社内で共有し、2回目以降はどう落ち着くかを見ていけば、安定化は早くなるでしょう。共有しないことの方が多かったりしますが・・・。
スケジュールコントロールがNGで一度採用した会社でも取引しなくなったというケースはあります。一度でも採用を判断したからには取り下げるにはそれなりの理由が必要なので、よほどの問題が起きたと考えた方が良いでしょう。それも一度や二度ではなく。
参考
関連記事
最後に
新規メーカーとの取引はリスクもありますが、特に製缶機器のように幅広く使われ、失敗の少ない設備から始めれば成功しやすいと言えます。
新規メーカーの採用は、単なる価格競争だけでなく、調達リスクの分散や将来の技術力向上につながります。エンジニアとして技術確認を怠らず、長期的に信頼できるパートナーを増やしていくことが、プラント運営の安定と競争力強化につながるでしょう。
メーカーの立場を想像するに、面倒な要求事項を出す会社にパイプ繋ぎをすることは、労力に見合っているかどうか気になります。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)X(旧Twitter)のDMでも可能です。
- 設備設計で悩んでいる
- トラブル原因の考え方が分からない
- 若手の教育方法に困っている
など、幅広くお受けしています。
*いただいたコメント全て拝見し、数日中に真剣に回答させていただきます。
この記事の内容を、あなたの職場・キャリアに合わせて整理したい方に技術・キャリア相談を行っています。海外プラント、製造管理、組織の病理、キャリア停滞など、あなたの状況に合わせて具体的にアドバイスします
→ 技術・キャリア相談はこちら
【著者:ねおにーーと】
化学プラントで20年以上、設計→製造→保全→企画まで一気通貫で経験したユーザー側エンジニア。 バッチプラントの設備・運転・トラブル対応を中心に、現場で本当に役立つ知識を発信しています。 → 詳しいプロフィールはこちら
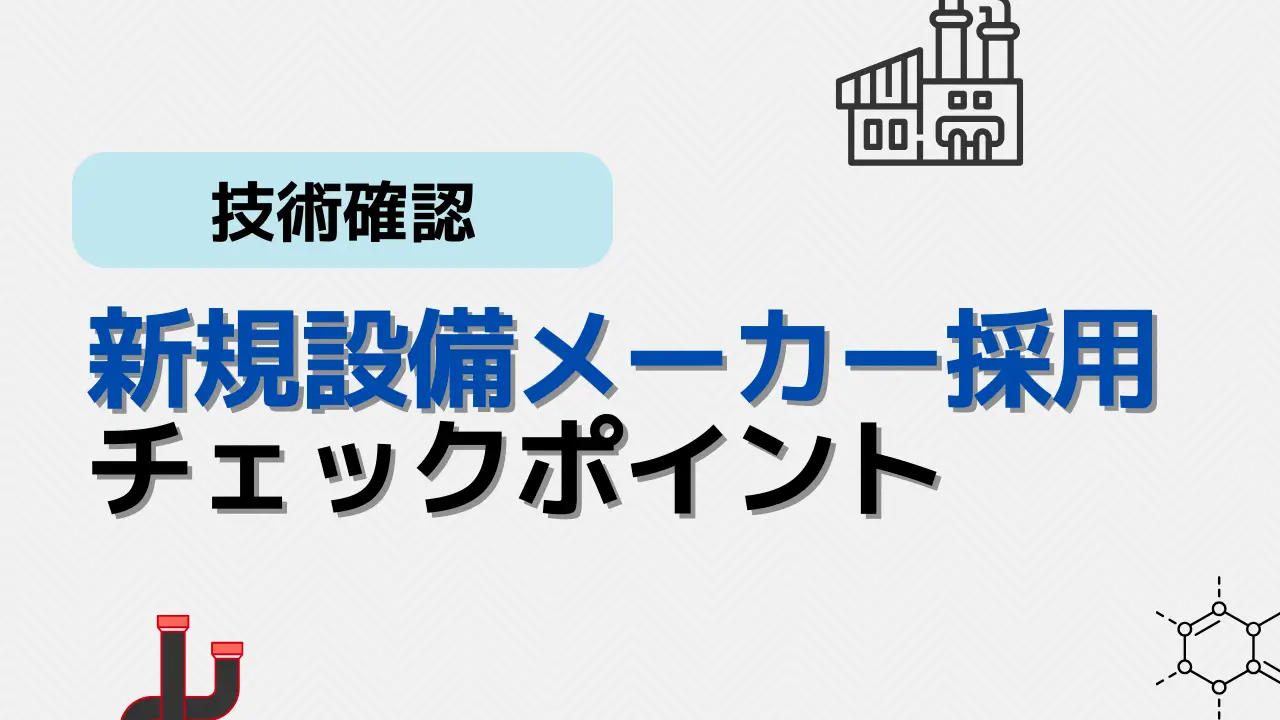

コメント