化学プラントでは、ガスや可燃性物質を取り扱うため、爆発リスクへの対応が欠かせません。特に、設計や保全に携わる機械エンジニアは、防爆機器の基礎知識や適切な選定基準を理解しておく必要があります。しかし、防爆構造には「耐圧防爆」「安全増防爆」「本質安全防爆」など複数の種類があり、それぞれの使い分けには一定の知識が求められます。
この記事では、防爆機器の種類や選定の基本ポイント、防爆記号の読み方、技術的基準との違いについてわかりやすく解説します。これから防爆の理解を深めたい方、実務での適用に迷いがある方は、ぜひ参考にしてください。

こんな自動化がしたいです!

非防爆だから無理!
こんなやり取りをすることなんて1度や2度ではないでしょう。
- 防爆が無いから仕方ない
- 防爆が必要だから時間や納期が掛かって仕方がない
現状は確かにその通りです。防爆に関して規制に関する話だけがクローズアップされがちで、そもそもの技術的な内容を理解している人は意外と多くありません。
この記事は、防爆シリーズの一部です。
・放出源・換気・距離の視点から考える化学プラントの現実的防爆設計
・防爆設備はどちらを選ぶ?安全増防爆と耐圧防爆の違いと実務判断
・プラントの危険区域の精緻な設定方法を試してみた
・現場でできる防爆対策の基本:モーターを防爆型にするか、非防爆を遮断で守るか
・「電気は無理?」ならこれを試そう:化学プラント向けエアー代替の現実解
燃焼の三要素
防爆構造とは、電動機などの爆発に対する構造を言います。電動機などの電気を扱う部分が、可燃性ガスと接触すると爆発を起こす可能性があります。火災爆発が起こる条件として
- 着火源
- 可燃物
- 支燃物
の3点があります。これを燃焼の三要素と呼びます。現実的に取れる対策は着火源。可燃物と支燃物は化学プラントの運転では除去することができません。
- 可燃物は周辺の可燃性ガスです。
- 支燃物は酸素です。
電動機的には着火源である火花が問題となります。これに対する構造を取るのが防爆構造です。
防爆の種類
防爆の種類はいろいろあります。
安全増防爆と耐圧防爆
化学プラントで使用する電気機器の防爆では耐圧防爆と安全増防爆が重要となります。
- 耐圧防爆 電動機内で爆発が起こっても外部ガスに引火しない構造
- 安全増防爆 安全度を上げて着火源とならないようにした構造
というのが定性的な表現です。もう少し具体的にみると、
- 耐圧防爆は、電気回路は一般的なもので、外部を機械的に強固にしたものです。
- 安全増防爆は、機械的強度の増加だけでなく、絶縁性能の向上・温度上昇の低減・保護装置などの電気回路の性質も向上させないといけません。
という表現ができます。
一般には、耐圧防爆の方がランクが上と言われます。ただし、耐圧防爆も安全増防爆も、着火源・可燃物・支燃物の3つの対策を同時に満たしたものではありません。
耐圧防爆の方が高価・長納期
耐圧防爆の方が安全増防爆よりも高く、長納期と言われます。
これが耐圧防爆の方がランクが上と言われがちな理由でしょう。
安全増防爆の生産は減少傾向
ところが、安全増防爆は一部企業で生産を中止しています。これからその流れが増えていきそうな気がしています。この辺はモーターメーカーではないので分かりませんが・・・。
2021年以降、コロナ禍による物流停滞が社会問題になっています。特に安全増防爆は非常に厳しいと言わざるを得ないでしょう。サプライチェーンの大きな問題となっています。
内圧防爆
内圧防爆構造は、容器内部に窒素ガスなどを封入して圧力をあげます。その容器内に爆発性雰囲気が侵入しないようにする仕組みです。
これは内圧室と同じ発想です。
耐圧防爆構造とほぼ同じ発想ですので、電気回路は一般的です。封入ガスを導入するために、設備コストが増えることがデメリットです。
油入防爆
電気回路を油の中に入れてしまい、爆発性雰囲気が侵入しないようにするという思想です。内圧防爆と同じで、爆発性雰囲気を侵入させないところがメリット。
- 油が安定していること
- 油が分解して可燃性ガスが蓄積しないこと
- 電気伝導度の低い油であること
色々な要求事項が必要となります。これならは内圧防爆の方がシンプルだと思います。
本質安全防爆
本質安全防爆は、電流・電圧を下げて電気回路を作動させることで電気火花や温度上昇を防いで、火災爆発を防ぐ発想です。
電気装置で発生する電気火花を測定し、最小着火エネルギー未満であれば、その爆発性雰囲気下で使用してもいいという考え方です。
特殊防爆
その他として、粉体充填・樹脂充填などの発想があります。これは油入防爆の発展形として考えています。
構造規格・技術的基準
防爆規格には2種類あります。
構造規格と技術的基準です。
電気屋にとってはそれなりの違いを理解しているでしょう。
でも機械屋にとっては「良く分からない」という印象を持っているはずです。私もそうです。耐圧防爆はd2G4、安全増防爆はeG3などと覚えることもありましたが、気が付いたらその基準名が変わってしまい、混乱してしまいました。
そして、どうでもよくなり耐圧防爆か安全増防爆かを理解していればいいという結論に至ります。
構造規格は日本の規格
簡単に言うと、構造規格は日本の規格です。
「電気機械器具防爆構造規格」(昭和44年労働省1)告示第16号
がその基準のようです。
技術的基準は国際的な規格
こちらも簡単に言うと、技術的基準は国際的な規格です。
「国際整合防爆指針2015」(平成27年8月31日)基発0831第2号
が現在の基準のようです。
d2G4・eG3は構造規格
私が仕事を始めた当時は、耐圧防爆はd2G4、安全増防爆はeG3という理解でした。これは構造規格です。現在はこの名称、ほとんど見ません。現在では技術的基準に変わっていっています。
構造規格と技術的基準の違い
構造規格と技術的基準の違いを確認しましょう。
| 規格 | 種類 | ゾーン 0 | ゾーン1 | ゾーン2 |
| 構造規格 | 本質安全防爆 i | ○ | ○ | ○ |
| 耐圧防爆 d | × | 〇 | 〇 | |
| 内圧防爆 f | × | 〇 | ○ | |
| 安全増防爆 e | × | △ | ○ | |
| 油入防爆 o | × | △ | 〇 | |
| 特殊防爆 s | ー | ー | ー | |
| 技術的基準 | 本質安全防爆 Ex ia | ○ | ○ | ○ |
| 本質安全防爆 Ex ib | × | 〇 | 〇 | |
| 耐圧防爆 Ex d | × | 〇 | 〇 | |
| 内圧防爆 Ex p | × | 〇 | 〇 | |
| 安全増防爆 Ex e | × | 〇 | 〇 | |
| 油入防爆 Ex o | × | 〇 | ○ | |
| 特殊防爆 Ex s | ー | ー | ー |
構造規格と技術的基準の主な違いは安全増防爆を1種場所でも使えるかどうかです。構造規格の方が厳しめに判断しているという解釈ができます。なお、以下の特徴も重要です。
- 本質安全防爆が最も安全である
- 耐圧防爆と内圧防爆は、本質安全の次に安全度が高い
- 安全増防爆は、部品の劣化故障により安全度が損なわれる
- 油入は、油の劣化・漏洩により安全度が損なわれる
これらの考え方から、0種場所・1種場所・2種場所への適用可否を判断しています。
安全増防爆の信頼度が低いのは、
電気部品を信用度 < 機械部品の信用度
だからです。この傾向は日本に特に強いです。
ところが、私は、内圧防爆も同じように信頼度に疑問を持っています。空気や窒素などで内圧が確保されていることが肝心ですが、その監視指標が無いからです。この意味では安全増防爆と大差ないと思います。
爆発等級
爆発等級は基本的に3段階に分かれます。ガスまたは蒸気の最大安全すきまによって分類します。構造規格と技術的基準で表記が多少違い、複雑になりがちですがまずは構造規格側から見ていきます。
構造規格では1,2,3
爆発等級では1,2,3の3段階で表記します。
| 爆発等級 | ガスまたは蒸気の最大安全すきま |
| 1 | 0.6mmを超えるもの |
| 2 | 0.4mmを超え0.6mm以下のもの |
| 3 | 0.4mm以下のもの |
ほぼすべてのテキストはこれで終わっています。これは素人には分かりません。
等級の数字が高い方が堅牢強固ということを意識してください。
この調べ方は、爆発等級の具体的な物質を見ることです。水素やアセチレンが等級3に該当します。そのほかの物質はほとんどが等級1です。この関係から、等級3の方が厳しいということが分かります。
- 水素は燃焼範囲が広い
- アセチレンは燃えやすい
こういう特性とリンクさせれば、等級を整理することはできます。上記の爆発等級と隙間の関係は
- 等級が大きいほど、すきまが小さい
- すきまが小さいほど、爆発等級の高い(燃えやすい)物質も通りにくい
という解釈ができます。
技術的基準はII A,II B,II C
技術的基準も構造規格と同じく3段階で区分します。すきまに対する数字が異なります。
| 爆発等級 | ガスまたは蒸気の最大安全すきま |
| II A | 0.9mmを超えるもの |
| II B | 0.5mmを超え0.9mm以下のもの |
| II C | 0.5mm以下のもの |
構造規格の方が数字が低い側なので、厳しい扱いをしていることが分かります。
発火度・温度等級
発火度は構造規格側の表現です。6段階で表現します。
発火度
| 発火度 | 発火温度 |
| G1 | 300~450℃ |
| G2 | 200~300℃ |
| G3 | 135~200℃ |
| G4 | 100~135℃ |
| G5 | 85~100℃ |
| G6 | 85℃以下 |
数字が高い方が、堅牢強固
ということを意識してください。発火温度が低い物質にも適用できる規格という位置づけができますね。
温度等級
温度等級としてT1,T2,T3,T4,T5,T6の6段階で表現しますが、これは発火度と同じ意味合いで使います。
発火度では発火温度に対して定義しますが、温度等級では最高表面温度に対して定義します。
発火度は物質の固有値である発火温度に関連しますが、温度等級は物体の構造で決まる最高表面温度に関連させています。
発火度の方が本質的な固有値を使っているため正しそうに見えますが、実際に発火するのは表面温度で決まるため、表面温度で規定する方が合理的と思います。
d2G4とeG3
防爆記号は、構造規格と技術的基準の2つに分かれ、それぞれに防爆構造の種類で区別されます。耐圧防爆、安全増防爆などの種類です。さらに、爆発等級や発火度で分類されます。
まずは構造規格に着目して、d2G4とeG3の意味を見ていきましょう。
d2G4の意味
d2G4とは以下の意味になります。
- 耐圧防爆のd
- 爆発等級の2
- 発火度のG4
これらを組み合わせてd2G4です。
耐圧防爆のdは単なる記号の当てはめだけなので、意味はありません。
爆発等級は2
耐圧防爆はすきまを持った構造であるため、爆発等級に関する規定が定められます。
とはいえ、爆発等級3は種類が少なく、防爆以外に特別な要求を受けることもありますので、例外として考えます。
爆発等級3以外なら何でも使えるように、という狙いで2を一般的な爆発等級として採用していると考えられます。
発火度はG4
発火度もこれと非常に似た思想です。
化学プラントで扱う物質はほどんどがG3より低い値です。
発火度G4に該当する物質はアセトアルデヒドやエチルエーテルです。機械屋にはなじみが薄い物質でしょうか。アセトアルデヒドは一般的には地味がなければいけない物質ですけどね。。。
発火度G3でガソリンやヘキサンが該当します。この辺りは日常的に使う物質です。
G3を一般的な発火度としてもよさそうだが、1ランク上のG4を一般的な発火度として採用していると考えられます。
eG3の意味
eG3とは以下の意味になります。
- 安全増防爆のe
- 発火度のG3
安全増防爆は爆発等級に関する規定がありません。「すきま」という概念で設計するわけではないからです。発火度はG3です。d2G4の項目で記載した通り、ほとんどの化学物質はG3以下の値です。だからこそ、安全増防爆ならG3でもいいとして一般的な発火度に採用したのでしょう。
耐圧防爆の方が安全増防爆よりも信頼性を上にするために、耐圧防爆の発火度を1ランクあげてG4にした。
といえなくもないです。というかこちらが正しい解釈でしょう。
技術的基準では
d2G4もeG3も構造規格上の表現です。技術的基準ではどう表現されるでしょうか。
| 構造規格 | 技術的基準 |
| d2G4 | Exd IIB T4 |
| eG3 | Exe II T3 |
余計な記号が入っていて嫌になりますね(笑)記号の表現自体は構造規格の方がはるかにシンプルです。構造規格が先に設定されたから、という理由でしょう。
技術的基準にはExという頭文字が付きます。私は勝手にExtraと解釈しています。機械屋は無視していい記号です。
Exの後にあるdかe
これが最重要。最重要のdとeという記号を先頭に持ってこないという思想は反対です。現場を無視した記号付けだと思います。
それが私が技術的基準を好きになれない理由。IIBもIIも爆発等級ですが、これも無視可能。爆発等級が2であれば十分という後続規格の思想がそのまま引き継がれます。T4とT3はG4とG3そのままです。
技術的基準には構造規格に対して、余計な記号としてExとIIが加わった。
と理解していれば十分だと思います。
現場で使える覚え方
機械エンジニアにとって防爆記号に触れる機会があります。
ちゃんと使えるレベルにするために、最低限ここは実践できるようにしましょう。
電動機図面の確認
電動機を機器本体と一緒に、機械エンジニアが購入を担当することが多いです。
ここで、図面を最初に確認するのは機械エンジニア
機械エンジニアは設備全体を統括して確認する責任があります。電気のことなので「知らない」ではすみません。少なくとも、防爆規格が要求を満たしているかどうかを確認しないといけません。
そこで、電動機図面から防爆規格を読み解く必要があります。
現場工事時の確認
購入した設備が、現場工事において適切に施工されているかどうかを確認しないといけません。ここで、電動機のネームプレートを読み解く力が必要です。
耐圧防爆はd、安全増防爆はe
現場レベルで使うのは、耐圧防爆と安全増防爆のみです。この2つの記号は、耐圧防爆がd、安全増防爆がeです。これを反射レベルで使えるようになればOKです。
個人的な覚え方を紹介します。
eはeasy・安い・安全
いきなり強引な語呂合わせと、強引なこじつけです。受験勉強ですらこういうこじつけは少ししかやっていないのですが、会社に入ってからこんなこじつけをすることになるとは思ってもいませんでした。
eはeasyのeです。
これは譲れません。安全増防爆はeG3という記号が多くeGがeasyと同じ読みであることからも、これは連想が容易です。次からが超強引です。
easyだから安い
簡単・シンプルだから安いでしょうという連想です。
安いと安全はどちらも安
最後が強引なこじつけ。安いと安全にどちらも「安」という文字が入っています。私はこんな情けない覚え方をしています。
easy → 安い → 安全(増防爆)
dはeより前
dはeよりアルファベット順で前にあります。
前にある方が、強そうなイメージがありませんか?
耐圧防爆の方が安全増防爆よりも強そうですよね?
だから、安全増防爆より強そうな耐圧防爆がeよりも強そうなdと把握しています。これもこじつけですね。
dはeより前
参考
関連記事
さらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
最後に
防爆機器の理解は、化学プラントの安全を守るうえで非常に重要です。機械エンジニアや保全担当者が最低限理解しておくべき防爆構造の種類や使い分け、規格の読み解き方を把握することで、より安全で効率的な設備設計や運用が可能になります。
実務では、技術的基準と構造規格の両面から適切な防爆対策を講じることが求められます。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
この記事の内容を、あなたの職場・キャリアに合わせて整理したい方に技術・キャリア相談を行っています。海外プラント、製造管理、組織の病理、キャリア停滞など、あなたの状況に合わせて具体的にアドバイスします
→ 技術・キャリア相談はこちら
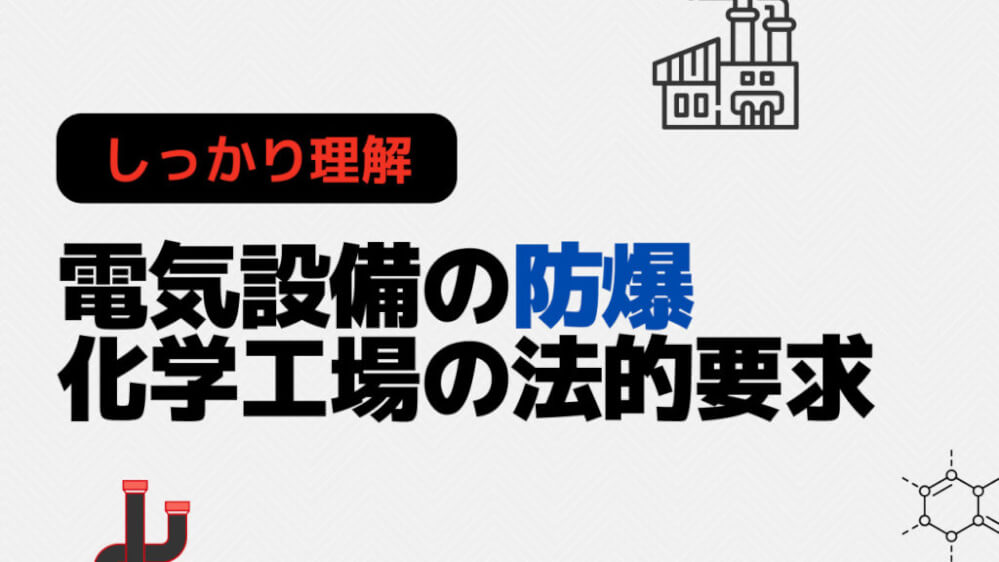

コメント