化学プラントでは、運転データや設備トラブル情報、設計書など、さまざまな情報が共有されています。しかし、これらのデータが実際に活用されているかというと、必ずしもそうではありません。
本記事では、データ公開が期待通りに機能しない背景と、その改善策について考察します。
会社で仕事をしていたら、さまざまな部署でデータや情報を取り扱い、それらを共有する仕組みを作ることが求められます。
いろいろな背景が考えられますが、例えば以下のような理由は容易に思いつきます。
- ある人に聞けば分かるがその人が居ないと分からなくなる
- 聞けばわかるけど、その手間を省きたい
- 手動で記録せずに、自動で記録したい
化学工場でももちろんこのニーズはあります。○○システムが乱立していきます。導入している側の気持ちとは裏腹に、使っている側としては悩みを抱えることになり、進展しにくいです。その辺りの背景を考えます。
この記事は、DX実態シリーズの一部です。
化学プラント配管設計に3D-CADが普及しない理由と現実
なぜプラントのDXは広がらないのか? 現場に潜む本当の壁
私の部署が経験した3Dスキャナー活用のリアルな壁
設備保全DX導入の現実:費用対効果評価の落とし穴と進め方
なぜDXが進まない?バッチ系化学プラントに残る「人が欠かせない理由」
設備保全のDXが進まない本当の理由:化学プラントが抱える根深い課題とは?
DXでは難しい日常点検、現場で求められる5感の力とは?
Excelと紙がプラントエンジニアの基本ツール
設備管理システム、導入したのに楽にならない?よくある7つの落とし穴
電話多用の背景を読み解く:保全担当がチャットより電話を選ぶ理由
プラントエンジニアが紙を使う理由とは?デジタル時代でも紙が欠かせないワケ
PIシステムは見ない
化学工場の大きなデータといえばDCSのデータでしょう。PIシステムなどで、各種計器のデータを記録して、計器室以外でも情報が見れるようにする仕組みです。
オペレータとしては相当嫌がります。自分たちが仮にミスをしたらそれを隠すことができず、仮にリカバリーしても怒られたり処罰されたりするだろう、と考えます。
一方で、このシステムを使う側からすると、実態としてはほとんどの人が見ません。見るのはそのプラントを管理する製造管理者くらいです。その管理者ですら毎日見ているとは限りません。見て、オペレータが考えるような展開を持っていくことも基本ありません。よほどのミスでない限りは、そういう指示をした管理者自身に責任が回ってきます。
計器室以外で見れるということでプロセス開発者や企画系の人も見るだろうと、製造管理者やオペレータは考えがちです。ところが、これもほぼありません。膨大なプラントの運転データを製造管理者と同じように毎日見るには相当の時間が掛かります。その暇があれば別の仕事をしています。製造管理者から問題があったり改善しようとしたときになって初めて運転データを見に行くというのが実態です。
見られていると思うと気持ち悪いのですが、実際には誰も見ていない。この事実に気が付くには私は相当の時間を掛けてしまいました。
設備トラブルは見ない
設備トラブルが起こったら、その情報を共有する仕組みが考えられるでしょう。この仕組みを導入しても見る人は少ないです。
システムとしては結構難しいもので、故障パターン別や故障モード別の解析をしようものなら、判断に時間が掛かります。その解析よりも先に対策を取ることを優先するので、終わったらまた別のトラブルを対応することになります。トラブルが起きたらその情報をキャッチして専任で管理する人が必要かもしれません(それが本来の保全の仕事であるはずですが)。
またトラブルが起きてその情報を公開するには、そのドキュメントを作る能力が求められます。この辺は企業文化にもよるでしょう。
- 変な情報を出したら責任論になる
- 論理的に疑わしい表現になっている
- 原因分析や対策が書けない
- 承認する際に、多くのコメントが出る
- ドキュメントを発行したら、すぐにコメントが出る
仕組みの問題が大きく承認ルートを広げすぎたり、質問の窓口を一本化したりなど、考えられなくはないです。
ドキュメントを発行する際にはいろいろと抵抗されますが、いざ発行して数年も経てば誰も何も言わなくなります。当時の人が異動してしまって経緯を知らなくなるからですね。こうして情報を集めていけば良いのですが、最初の抵抗感が大きいと仕組みが回らなくなります。
システムにドキュメントを入力しても、それを都度チェックする人が居ない点は、PIシステムと同じです。毎回毎回チェックするのは相当の工数が掛かります。入力したら関係者全員にメールが行く仕組みでなくて、気が付いたら入力されていた(そもそもそんなシステムがあったことすら他部門は知らなかった)くらいでも良いかもしれません。
ドキュメントそのものを作ることに抵抗がある人も多いのも問題ですね。だからこそ、口頭で出回る情報を記録と共有をしたいのですが・・・
設計書は見ない
設計書も設備トラブルと同じような運命をたどります。設計書も書いて発行する時には抵抗感がいっぱいあります。
設計書は設備トラブル以上に、書く内容が難しく、完了するまでの時間も問題になります。結論だけを書いて、背景を書かない設計書も多いです。意味のない設計書を無機質に書き上げても、見る人が少なければまさに無駄。
書こうとする担当者は、それが多くの人の目に触れるかも知れないと思うと手が出にくくなります。製造管理者はこの情報があれば、わざわざ設計者に聞かなくても対応できるかもしれないのに、都度設計者に聞かないといけなくなり、困ります。それ以外の人は、設計書に触れる機会すらあまりないでしょう。
目標件数の設定は意味がない
機電系エンジニアの毎年の成績目標には、定量的な指標が入れにくく、こういうシステムへの入力件数が評価になったりします。
これもあまり意味が無いと思っています。担当プラントや投資の時期によってトラブルや設計すべき機器の数が変わります。複数ある目標の1つに設定しても、結果の大小で成績が変わることは少なく、手間がかかる割に公開されて皆に見られるという想いの方が嫌だと思うでしょう。
設計や保全の難しい所です。
参考
関連記事
最後に
データの公開や共有は、化学プラントの運用において重要な要素です。しかし、実際には閲覧されない、活用されないといった課題が存在します。これらの問題を解決するためには、情報共有の目的や意義を明確にし、関係者全体で共有文化を醸成することが求められます。また、システムの導入だけでなく、運用体制や評価指標の見直しも必要です。
化学工場では多くのデータ、特に時系列データを扱い、それを記録して公開する場合が多いです。このせいで担当者としては見られているという緊張感の外に、やりたくないというネガティブな想いを抱きがちです。
そのデータを有効活用する側は、実は機会は少なく、見る人も多くはありません。この事実を知っているかどうかで担当者としては動き方が変わるでしょう。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
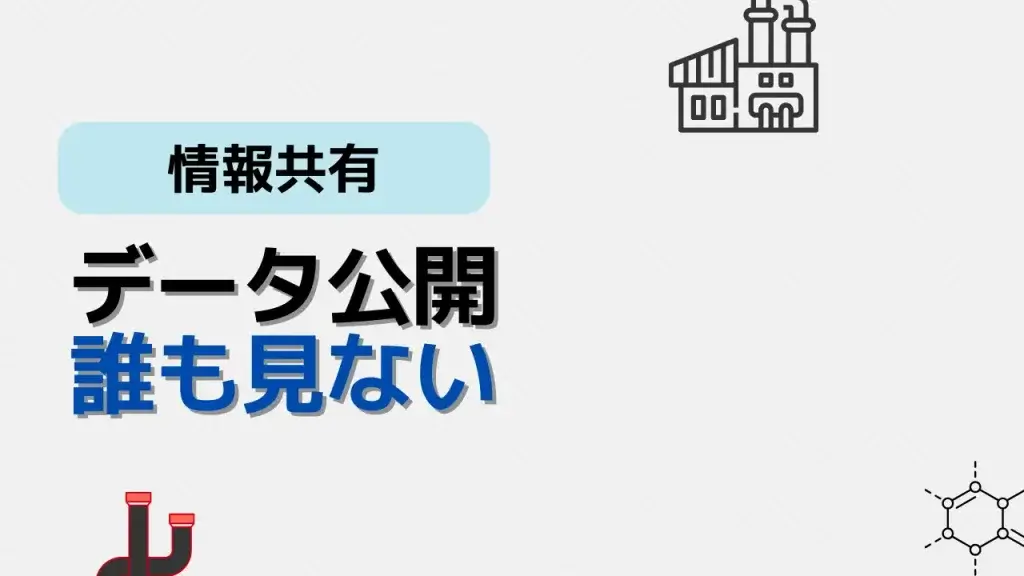

コメント