安全は特に製造業ではとても重要で常々この単語が飛び交います。化学工場の「安全」と一言でいっても、その中身は多岐にわたります。化学物質の危険性を扱う化学安全、設備やプロセスの制御を扱うプロセス安全、現場作業に関わる作業安全、そして日常的なヒューマンエラーを防ぐ行動安全。
この記事では、それぞれの「安全」の意味と、現場での関わり方の違いを整理して解説します。
この記事は、工事安全シリーズの一部です。
化学プラントの地面は危険だらけ!工事の時はここに注意
熱中症を化学プラントの工事現場で起こさないために
化学プラント工事の現場で活躍する元方安全衛生管理者とは?役割と課題を解説
安全配慮義務を果たすための化学プラント工事パトロールの実態解説
化学プラント工事で多発する転落事故|開口部管理と現場の安全対策
化学安全
化学安全は、化学物質そのものの安全を意味します。具体的には引火爆発などの危険性や毒性などを指します。これらはSDS(安全データシート)として情報がまとめられます。
化学物質を実際に使用する製造工場だけでなくて、運搬する物流会社など広い範囲で大事になる情報です。工場だけならその会社の教育でカバーできても、工場外となると難しいですからね。
新たな化学物質を合成する時に話題になるだけではなく、例えば原料を変更して出来上がった製品に新規不純物が発見された場合にも話題になります。安定して作っているように見える製品でも、化学安全は事あるごとに問題になります。工場の機電系エンジニアにとっては、関わる機会はほぼありませんが・・・。
プロセス安全
プロセス安全は、プラントで取り扱う化学物質の安全と考えています。
HAZOPや他の安全評価指標を使って、危険な化学物質をいかに安全な状態に制御して取り扱うかを考えます。プラントの設備内で例えば圧力や温度といった分かりやすい指標で危険性を議論するが第一ですが、特にバッチのHAZOPでは「ずれ」のパターンが連続よりも膨大にあり、検討するべきパターンは段違いです。
バッチであろうが連続であろうが、化学物質をプラントで取り扱うというのは結構カバー範囲が広いです。
・工場内に原料を受け入れたときの安全(外部倉庫も同じです)
・プラント内で原料を保管している時の安全
・プラントの設備で実際に使用している時の安全
・使い終わった原料や副生物の安全
化学安全と重なる範囲もありますが、どちらでも見てなかったということだけは避けたいです。倉庫で長期保管している時に危険な状態になることが予想されるなら、それを化学安全として見るかプロセス安全として見るかは意見が分かれるかも知れません。
プロセス安全は一度決めると変更の可能性はあまり高くはありません。何かが変わってもプロセス安全の評価結果が変わらないようにするというほうが実際でしょう。最初の評価で見落としが無いように仕組みを作ることが大事です。
機電系エンジニアだと設備に関わるので、プロセス安全にも関わっていると言えるでしょう。
作業安全
作業安全は、プラントの運転で人が実際に行う作業の安全です。これもプロセス安全と同じでカバー漏れがないように気を付けたいです。
・原料を設備に投入する
・反応物質をサンプリングする
・製品を取り出す
・原料や製品をプラント内外に運搬する
・分析室で分析する
・定期修理などの工事
化学工場のパトロールの大半は、作業安全が中心となります。どれだけマニュアルを作って標準化しても、実際の作業がどうなっているかを書面や記録媒体上だけで確認するのは限界があり、実態を知って対策を取るためにもパトロールは継続されます。
プロセス安全のように体系化が難しいのが作業安全の難点でしょう。
作業安全には定期修理や改善工事などの工事も含みます。ユーザー側としては工事をする前の設備の引き渡しに洗浄作業が発生することと、作業中に周囲に危険性がないようにすることが、中心です。作業をする工事会社自身も安全を考える必要があり、ユーザー側も工事会社が危険な作業をしていたら、安全配慮義務の一環として止める必要があります(止めるときには揉めやすいので勇気が要りますが・・・)。機電系エンジニアは工事会社に発注する関係上、安全に対する指導を求められたりします。
行動安全
行動安全は、化学物質に関係ない範囲で人が行う行動の安全という位置づけで考えています。例えば以下のようなものが行動安全です。
・階段を上り下りをするときにつまづく
・道路を歩いている時に転ぶ
・カッターナイフを使って怪我をする
・紙を触って指を切る
化学物質に少しでも触れる可能性がある作業は作業安全としてカバーしようとしますが、ある程度カバーすると行動安全にかかわるヒヤリや災害が目につきます。行動安全を気を付けようとすればするほど対策が過剰になり、何もできなくなります。カッターナイフがその例ですね。
品質安全?環境安全?
品質安全や環境安全という単語がありますが、個人的には反対です。何にでも安全を付ければ良いというものでも無いでしょう。品質は品質、環境は環境で、安全とは切り分けたいです。
環境も広い言葉ですが、化学工場で環境というと自ずと環境に対する保全を意味するので、環境安全と安全を付けなくても良いのでは?という単なる一意見です。
参考
関連記事
最後に
化学工場の安全を、「化学」「プロセス」「作業」「行動」という4つの視点から切り分けました。
- 化学安全:物質そのものの危険性を理解する
- プロセス安全:プラント内での制御と設計により事故を防ぐ
- 作業安全:人が行う作業そのものを安全にする
- 行動安全:日常的な行動に潜むリスクを防ぐ
どれも独立して存在するのではなく、互いに補完し合う関係にあります。
特に機電系エンジニアにとっては、直接関与する範囲が限定されていても、全体像を理解しておくことが、安全文化の成熟につながります。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)X(旧Twitter)のDMでも可能です。
- 設備設計で悩んでいる
- トラブル原因の考え方が分からない
- 若手の教育方法に困っている
など、幅広くお受けしています。
*いただいたコメント全て拝見し、数日中に真剣に回答させていただきます。
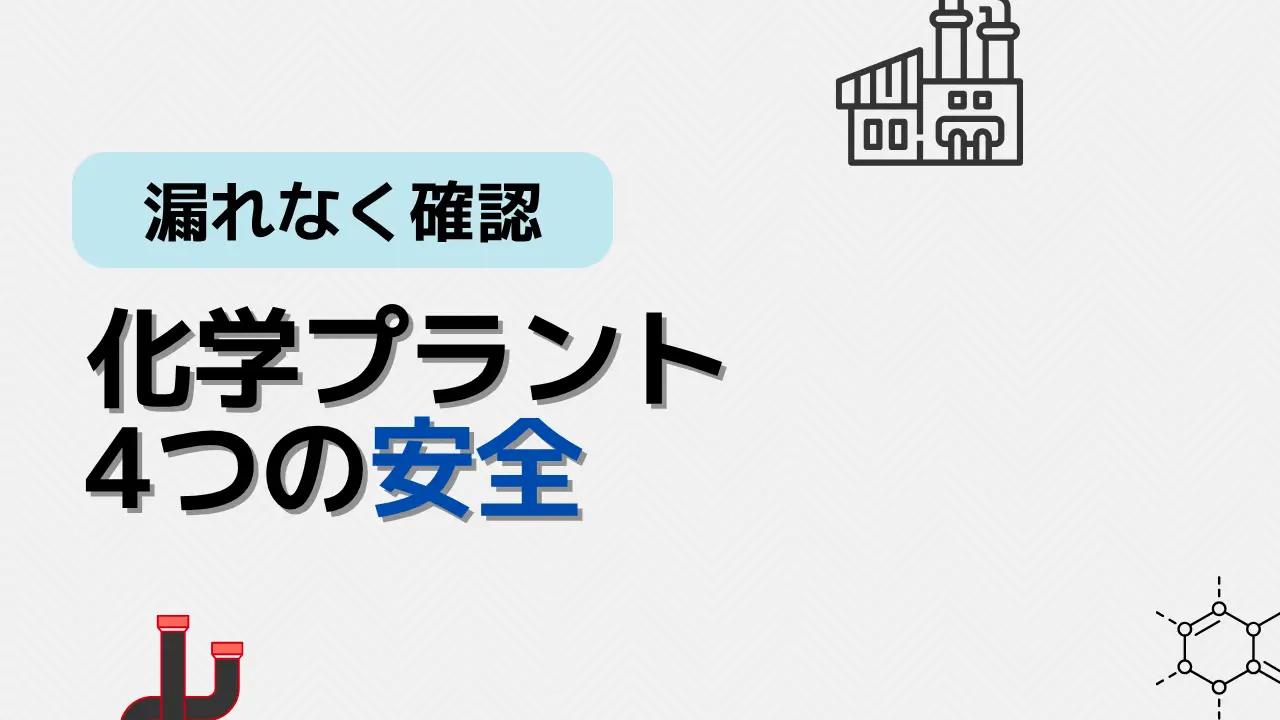

コメント