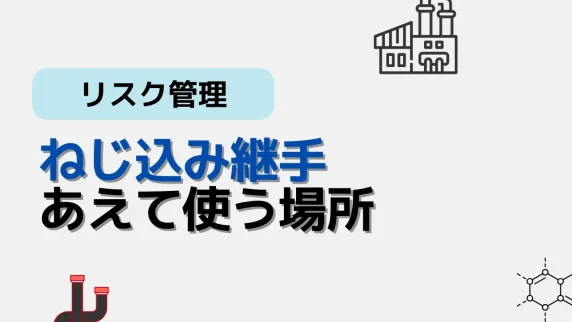 配管
配管 化学工場でねじ込み継手を使うときに知っておくべき注意点
化学工場でねじ込み継手を使う際の注意点を解説。漏れや耐圧、腐食リスクを踏まえた適切な選定と管理方法を紹介し、安全な配管運用をサポートします。
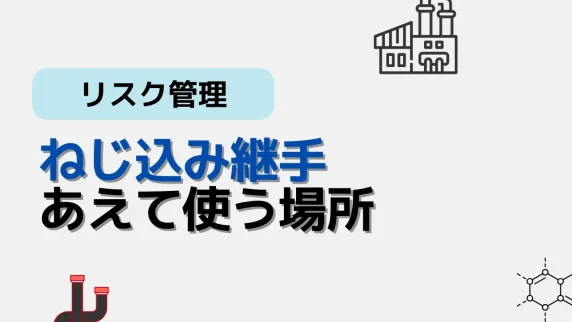 配管
配管 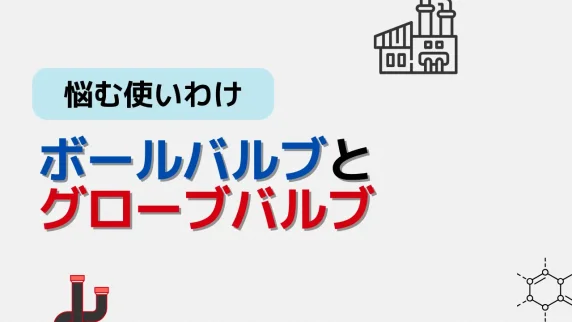 配管
配管 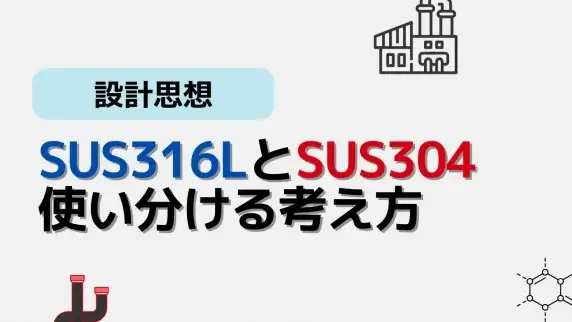 配管
配管 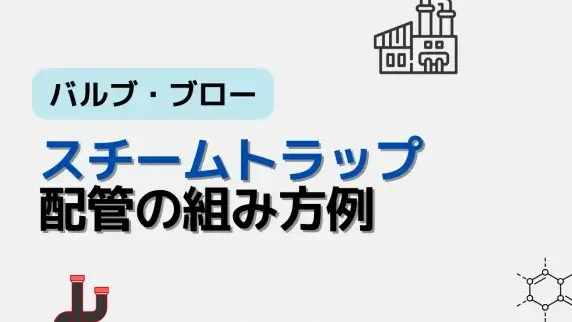 配管
配管 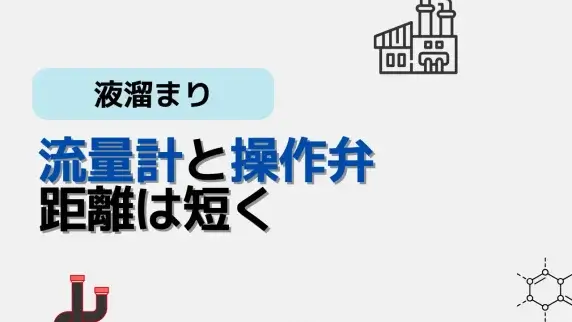 計装設計
計装設計 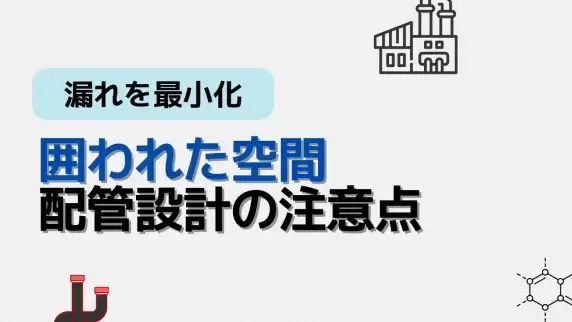 配管
配管 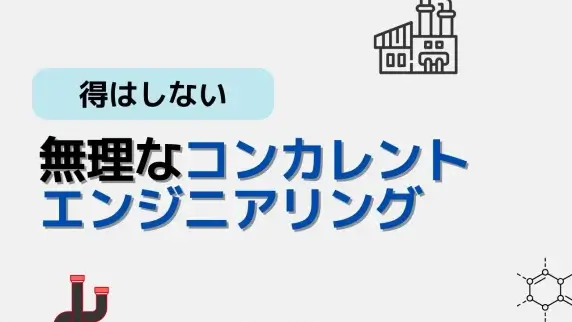 プロジェクト
プロジェクト 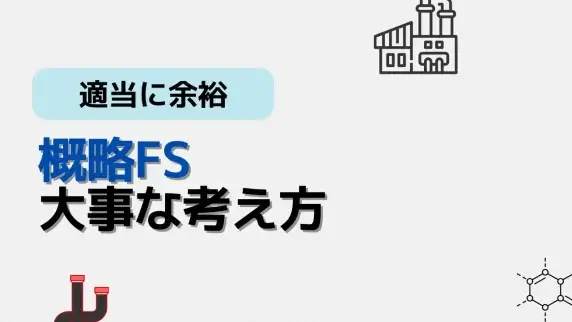 プロジェクト
プロジェクト 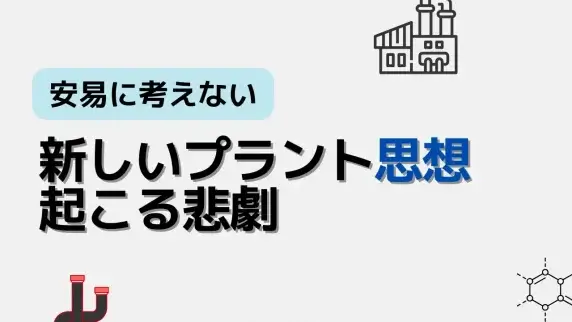 プロジェクト
プロジェクト 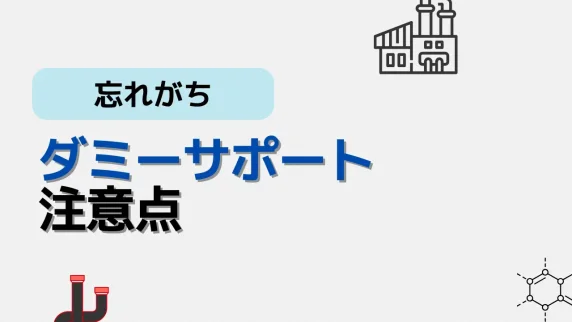 配管
配管