化学プラントでモーターなどの回転機器を扱う際に、電気測定器は欠かせません。特に「アナログテスター」と「クランプメーター」は、電気エンジニアには必携のツールですが、機械系エンジニアの中には詳しく知らない人も多いです。しかし、基本的な知識として押さえておくことで、現場での作業効率や安全性を大きく高めることができます。
今回はこの2つの測定器の特徴と使い方をわかりやすく解説します。
アナログテスター
アナログテスターとは、テスターと言われることも多いでしょう。
電気や必携の測定器具です。
電気エンジニアが使っている姿を1度は目にしたことがあるはずです。
これ1つで、測定できることは非常に多いです。
一言でいうと電気回路のチェックに使えます。
赤と黒の線の末端部を、金属部に付けると指示針が動くアイテムです。
電気回路の状態測定
テスターで測定できる対象は下記のものがあります。
- 電流
- 電圧
- 導通
- 抵抗
機械屋が目にすることが少ないのは当然でしょう。
化学プラントでこれを使う機会は主に電気室の電気盤だからです。
電気室に入らないと目にすることは無いかもしれません。
ボンディングで活躍
そんなテスターですが、化学プラントの現場で活躍する場所が1つあります。
それがボンディング。
化学プラントでは、静電気対策として浮き導体をゼロにすることが求められます。
浮き導体にはいわゆるアース線を接続して電気を逃がすようにしますが、その効果検証にテスターが使えます。
導通チェックです。
クランプメーター
クランプメーターはアナログテスターよりも必携したいアイテムでしょう。
何だったらこれ1個でいいかもしれませんね。
機械屋のコンベックススケールと同じ位置づけです。
原理的には電気ケーブルから発生する磁界を検出するものです。
安全性
クランプメーターでは、運転時に回路を切らずに以下の測定ができます。
- 電流
- 電圧
- 抵抗
- 温度
- 周波数
ケーブルの外周部に測定部をセットすれば、測定できます。
電磁誘導を使って検出する賢い仕組みです。
テスターとの違いは安全性。
テスターは電気が通っている金属部の手前まで、手で端子を近づけないといけません。
感電する恐れが高い!危ない!ということになります。
ところがテスターでは金属部に触れることがなく安全に測定ができます。
試運転での電流測定
クランプメーターを利用する機会は機器の試運転
特に、メーカー工場での立会検査で大活躍します。
仮設のケーブルで装置に接続するため、測定装置が完備されていないことが多いです
ユーザー工場に設置した場合は電気室の盤内である程度の測定はできますが、メーカーの仮設場ではそうもいきません。
メーカーがユーザー工場で試運転をするときに、メーカーSVがこのクランプメーターで測定することが多いです。
照度計
電気に関連して、照明の照度を測定する機会があります。
機械屋が目にすることはまずありません。
運転時にも何となく暗かったら照明をつける・照明を増やすというだけなので、照度計のお世話になる機会は少ないでしょう。
作業環境測定で使う時があるくらいです。
現場で使う電気測定器としてはあまり重要ではありませんね。
参考
関連記事
さらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
最後に
アナログテスターとクランプメーターは、化学プラントでの電気測定に欠かせない基本的なツールです。
機械エンジニアも電気の基礎知識として、両者の特徴や使い方を押さえておくと現場でのトラブル防止や安全確保に役立ちます。特にクランプメーターは安全で便利な測定器として重宝されていますので、ぜひ使い方を習得しましょう。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
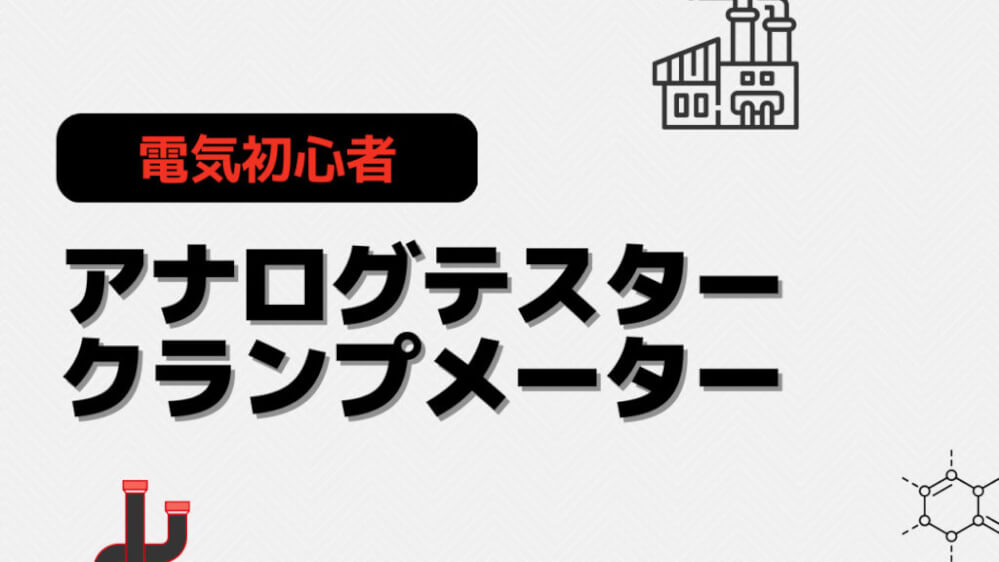

コメント