グラスライニング配管やフッ素樹脂ライニング配管は、化学プラントなど腐食性物質を扱う場所でよく使います。プラントの老朽化が話題になっている昨今、保全の重要性は上がっていくばかり。
設備関係の保全はよく話題にあがりますが、配管は意外とケアがされていません。この記事では、特に重要なグラスライニング配管やフッ素樹脂ライニング配管の保全の考え方を一通りまとめました。通常の保全を言語化しただけですが、それそのものが意味のあることだと思っています。
この記事は、グラスライニング配管シリーズの一部です。
グラスライニング配管の特徴|プラント初心者向け
グラスライニングの閉止フランジを使いますか?
グラスライニングの配管設計はスペーサーによる調整が大事
後から拡張しやすい:バッチプラントの配管ヘッダーをグラスライニングで設計する考え方
BMで交換
グラスライニング配管やフッ素樹脂ライニング配管の保全は、BMが基本です。壊れたことに気が付いてから、交換します。1ライン・2ライン程度なら適切な保全ができても、プラント全体に張り巡らされているラインに対して、(TBMやCBMなどの一見適正に見える)保全を実施するのは不可能でしょう。
TBMは特殊な個所のみ
BMが基本とはいえ、TBMで見るべきラインもあります。とても特殊な薬液を通すラインです。私が担当しているプラントでは過去に数ラインあった程度です。配管に対してTBMという考え方自体が特殊なので、実際はかなり手探りになるでしょう。
・1年経てば配管をサンプル的に取り出して健全性を確認する
・翌年まで使えるかリスクを関係者で協議
・限界に到達して交換が必要となったら、その前年までの年数を交換周期に設定
状態に応じて用途分け
グラスライニング配管やフッ素樹脂ライニング配管は、その劣化状態に応じて用途分けが可能です。例えばグラスライニング配管なら、
・新品をAランク
・光沢が無くなった程度をBランク
・触ったらざらつく程度をCランク
というような3ランクくらいに分けます。(グラスライニング設備と同じような考え方です)
Aランクは新品なのでどこのラインでも使用できます。BランクになるとTBMで使用するようなラインは少し不安になります。Cランクだと少なくともTBM対象ラインは不可で、条件が厳しくないラインに回そうとしたりします。
管理するラインが多いとそれだけ大変なので、3ランクで採点して管理台帳に載せることすらできないでしょう。日常の管理の範囲内で、目や手が届く箇所(例えばヘッダーとかポンプ周り)だけでもある程度の頻度で見ていくことが現実的でしょう。
発見を少しでも早めるためにできること
BMで管理すると言っても、発見は少しでも早い方が好ましいです。そのために保全上できる管理方法を説明します。
ボルトをチェック
フランジ間のボルトをチェックしましょう。ここは最初からやられやすい箇所で、外から見やすい場所でもあります。ガスケットもチェックポイントになりえますが、少し見づらいのが難点。
同じラインや他のグラスライニング配管のラインと比べて、ボルトが錆びたり変色したりするのが速ければ、そこは要注意です。
フランジをチェック
ボルトに合わせてフランジもチェックしましょう。もしかしたら液体が漏れているなどの傾向があるかもしれません。TBMで管理するようなラインなら、液漏れが見つかった瞬間に交換できる体制にしましょう。
フランジカバーを付ける
フランジカバーを付けることも効果的です。これは液体の漏れより先に起きるガスの漏れに気が付こうとする取り組みです。ガスが漏れたらアクリル製のカバーが白色して、これまで内部が見えていたのが見えなくなります。注意ランクを1つ上げるための監視ポイントとして使えます。
フランジカバーは水が入ったらダメ、腐食そのものの対策になっていないからダメ、などと考える人もいますが、早期発見できるというのは大きなメリットです。いざ大ごとになってからでは遅いです。
フッ素樹脂ライニング配管なら外側の鉄配管にプラグが打ってあって、早期発見できるようになっているタイプもあります。
ピース数を減らす
ピース数を減らす取り組みは、保全上とても有効です。配管はフランジが弱点です。グラスライニング配管やフッ素樹脂ライニング配管はフランジ数が多くなってしまうため、少しでも少なくすることは努力できるポイントでしょう。
初期施工時はどうしても図面作成段階で測れない箇所があって、ピース数が増えがちです。運転してから「なんでこんなにピースが多いのか良く分からないが、そのままにしておこう」と考えてしまうと、いつまでもピース数を減らすことができません。運転や保全のフェーズで是非とも変えていきましょう。
参考
最後に
グラスライニング配管やフッ素樹脂ライニング配管は、腐食環境下での信頼性確保に欠かせません。BMを基本に据えつつ、特殊ラインでTBMを組み合わせる、劣化状態で用途分けする、早期発見の工夫をする、ピース数を減らすなどの取り組みが効果的です。現実的にできる範囲で管理を工夫し、プラント全体のリスク低減につなげましょう。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)X(旧Twitter)のDMでも可能です。
- 設備設計で悩んでいる
- トラブル原因の考え方が分からない
- 若手の教育方法に困っている
など、幅広くお受けしています。
*いただいたコメント全て拝見し、数日中に真剣に回答させていただきます。
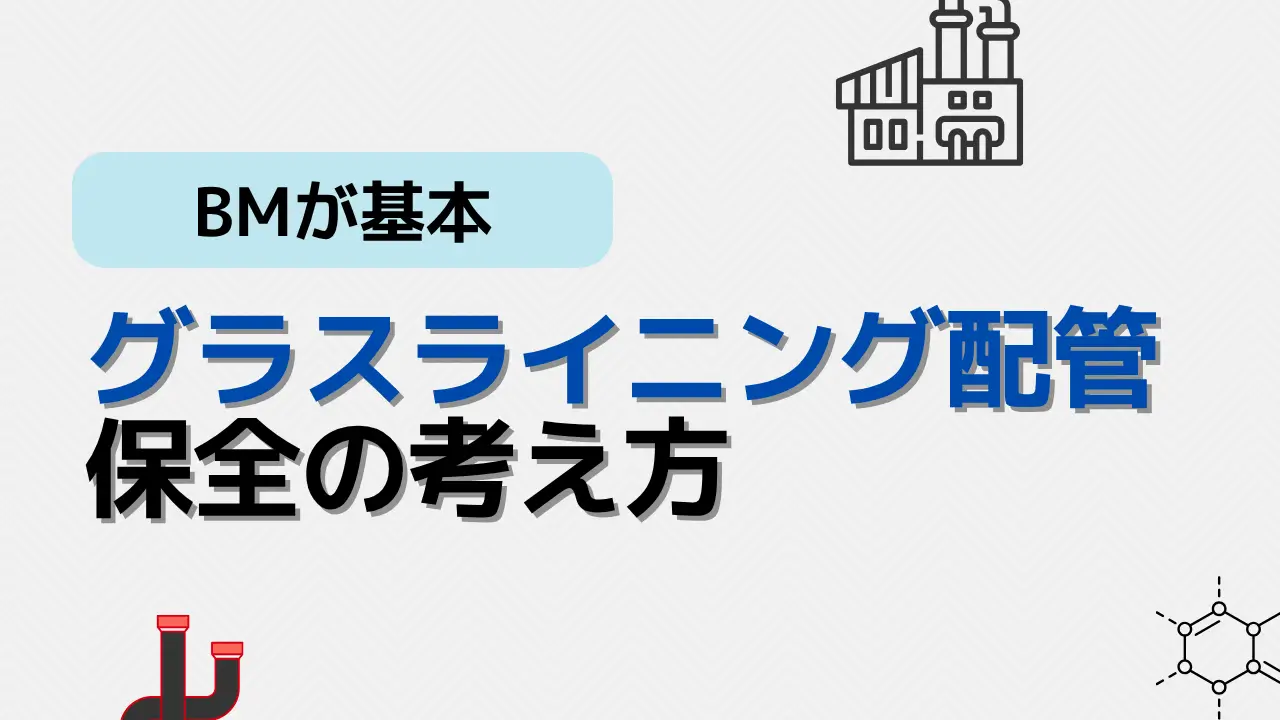

コメント