ニュースで取り上げられた八潮市の陥没事故は、多くの人に衝撃を与えましたが、特に化学工場に携わる製造・保全の現場では他人ごとではありません。このような老朽インフラの問題は、実は大手企業の化学プラントでも静かに進行しています。「大企業だからしっかりしている」と思い込むのは危険です
本記事では、築50年を超える化学工場が抱える深刻なメンテナンス問題と、軽視されてきた保全の盲点について掘り下げていきます。
この記事は、ライフサイクルシリーズの一部です。
製品とプラントのライフサイクルを両輪で考える:化学工場の持続的運転戦略
プラントライフサイクル入門:設備寿命から設計まで考える長期保全戦略
製品ライフサイクルを機械屋目線で考えてみた|化学プラントの場合
プラントライフサイクルを決定付ける設備検査7選
プラントライフサイクルとメンテナンスコストの関係:バスタブ曲線で読む保全戦略
プラント設計の最適化|プロセス面と設備面のバランスを考える
40年経過した老朽プラントを長持ちさせるために
40年使った高所配管に潜むリスクとは?設計と保守の見直しポイント
メンテナンスをしない
化学工場は日本ではおそらく高度経済成長期あたりで勢いよく建設されていきました。もう50年以上前のプラントや工場というのも結構珍しくはありません。これらの設備が寿命を迎えてきています。
でも、この設備をメンテナンスしようという発想は何故かあまり生まれていません。道路や上下水道と同じで、作る時にはそれが壊れることを想定しておらず、作れば作るほど良いという考え方で出来ていったと思います。設備のように運転に影響が出るものは、寿命を意識して更新を考えますが、その他大多数の配管はメンテナンスという発想が希薄です。
この配管からの漏れは今後ペースを増していきます。危険物の漏洩も増えていきます。工場内で止めれたら良いのですが、頻度が多くなれば自ずと外部に漏洩するリスクも高まります。
大手企業だからしっかりメンテナンスしているだろう、というのは完全に思い込みです。公共設備はしっかり見ているだろうというのと同じくらい思い込み。
この状況は、例えば中国で不動産をいっぱい建設して結局は廃棄するということと、似ているように思います。作った後ちゃんと使うか使わないかの違いだけであって、メンテナンスをしないという部分は同じだと思っています。
投資の先送り
企業がメンテナンスをしないというのはどういうことでしょうか。しっかりメンテナンスしているだろうと思いますよね。
企業にはよりますが、メンテナンスはほとんど考えていないと思います。
- 毎年一定額の投資をしているから問題ない
- 設備トラブルが起きてから夜間工事で応急対応すればいい
- 問題未然に防ぐDXに取り組んでいるから問題ない
これくらいの考え方だと思います。八潮市の問題と同じで、そもそも問題が起きるはずがない・起きないように管理するのが工場の当然の責務、とくらいに思っています。問題を起こしたら工場長の管理が悪いのであって入れ替えれば良い、とすら思っています。
50年も経過している工場やプラントなら、補修に関る費用は右肩上がりのはずで昨今のインフレも相まって、修繕費は相当の右肩上がりでないと追い付かないはずなのに、ほぼ一定額で抑えようとしているはずです。これで工場が良くなるはずがありません。
そもそも点検ができない
メンテナンスをしない発想や投資を先送りするという問題もありますが、そもそも点検ができない設備構造になっている部分も多いです。
これは機電系エンジニアの責任もかなりあります。
例えば、高所のラックに配管を多数設置していたとして、日常の運転では問題なかったとしてもメンテナンスはできない構造になっています。真面目に見るなら多数の足場を設置して点検します。これならラックにちゃんとしたアクセススペースを設けておけば良かったのに、と思います。最初にその費用すら削減してしまうと、後の人が困ります。同じようにトレンチの配管も同じです。
設備回りの配管も似たような要素があります。適切な場所にフランジを設けておくと楽なのに、漏れを気にするためにフランジを極小化して返ってメンテナンスを犠牲にします。フランジ数を削減する取り組みは、当時はコスト削減として絶賛されたことでしょう。
点検にするにはコストが掛かり、点検する人が少なく数量も膨大なので時間が掛かり、メンテナンス周期を真面目に設定しようにも時間が掛かりすぎるでしょう。こうなると、保全とは何だろうと自問自答します。
コストが高い
最低限のメンテナンスしかしてこなかった工場で、実際に必要なコストを試算しようとしたら大問題になります。10倍程度の高い修繕費が必要だと分かったとして、それを会社として充当できるかという問題です。
予想をはるかに超えるメンテナンス費が必要だと分かった会社はどう考えるでしょうか。
- メンテナンス費が高い
- 工場で物を作るのも高い
- 工場に人が集まらない
メンテナンス費をきっかけに、我慢していた他の問題も浮上して、そもそもその工場で作らなくていいのでは?という発想になると予想しています。
今後、海外展開がますます増えていくことでしょう。そして日本の工場はどんどん縮小していきます。
プラントライフサイクルと言えば格好は良いのですが、終わりはあっけないものになるはずです。特に判断基準に関しては意外にもルーズ。
機電系エンジニアとしてはプラント保全に全力を尽くすはずですが、設備トラブルが起きないような直前の歯止め策としての業務ばかりです。そこに捕らわれすぎていると、メンテナンス費を一定額に抑える努力ばかりが進み、見てこなかったメンテナンス費が問題になるのを抑止することになります。
一度建てたプラントは一定年数で廃棄を前提として、最低限のメンテナンスをして、時期が過ぎれば別のプラントに移行する。プラント建設には、こういう背景も考えられます。繰り返していくうちに、プラントを建てる場所が無くなるでしょうが、それはかなり先の話でしょう。
参考
関連記事
最後に
化学工場における設備の老朽化は、目に見えにくい形で確実に進行しています。
50年以上の歴史を持つプラントは、メンテナンス軽視と構造的な問題から、今後ますます多くの課題を抱えることになるでしょう。
「壊れてから直す」では間に合わない時代に入っており、今こそ保全の在り方を根本から見直す必要があります。
企業・技術者・現場の全員が、プラントの「終わり方」まで見据えた維持管理を行わなければ、気づいた時には手遅れかもしれません。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
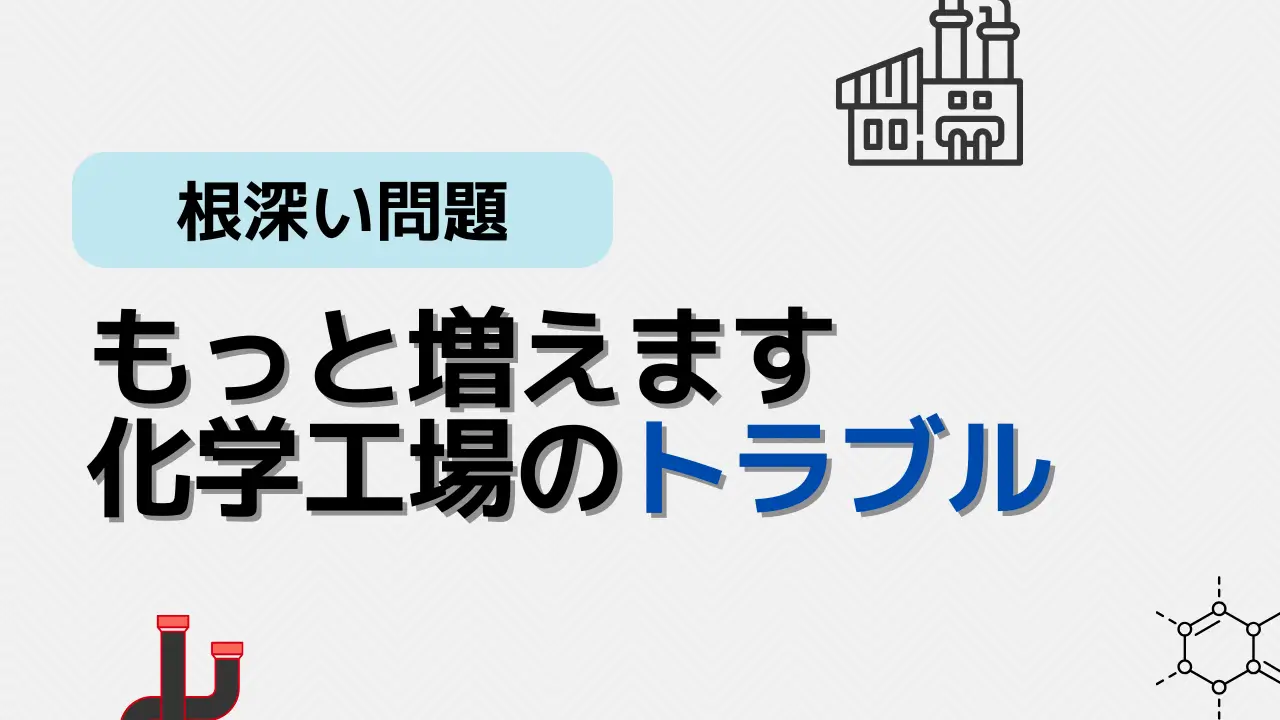

コメント