化学プラントでは、モーター駆動機器の制御手段としてインバータが広く普及しています。「インバータ=高性能・省エネ・万能」というイメージを持たれがちですが、実際には注意すべき落とし穴も多く存在します。
この記事では、インバータの導入を検討する際に見落とされがちなデメリットと、化学設備での適切な選定ポイントについて解説します。良い所を見ていきたいですが、悪い所も冷静に見ていきたいですね。
寿命が短い
インバータの寿命は思ったより長くありません。
10年くらい経てば交換していきましょう。
40年以上使い続ける化学プラントにとっては、メンテナンスコストとして結構載ってきます。
何でもかんでもインバータにしてしまうということは、運転時の省力化や安定化の面で有利ですが、コストはアップします。
それでも運転を優先させてインバータにしているということと、しっかりとお金をかけて交換していくという姿勢を会社として確立しておかないといけません。
いつ壊れるか分からない
インバータはいつ壊れるか分かりません。
インバータでなくて油圧駆動であれば、油圧装置の外観や振動騒音からある程度の把握ができます。
しかも、油圧の場合は意外と寿命が長いもの。
インバータの場合は、設備がある場所とは違う専用の電気室をわざわざパトロールすることになり、しかも外観を見ても劣化度が分からないという問題を持っています。
運転中に万が一壊れてしまったら、運転を止めないといけないかも知れませんね。
それだけならいいのですが、修理に時間を要することで反応物が危険な状態になるプロセスも結構あるのが化学プラント。
壊れるまで交換しないBMでの対応がインバータとしては許されないのですが、CBMができない以上、TBMにしないといけません。
それでも寿命が短いので、交換頻度が結構高いのがネックになります。
期待していた効果が出ない
インバータ駆動では思った効果が出ないという場合があります。
典型例がポンプ。
回転数を落として省エネを期待していた割に、回転数は意外と落とせなかったりします。
回転数を落とした分だけ揚程が落ちるので、すぐに流量が落ちてしまうからです。
大容量のユーティリティポンプに対して省エネ効果を期待していたら、効果があまりなく、交換費用だけが発生し続ける。
なんてことになりかねません。
手動バルブで絞るだけでも十分だと、考えるべきでしょうね。
そもそも使えない
インバータ駆動にしようと思ってもできない物があります。
主に高圧の設備です。
容器内部で圧力を維持するための、駆動装置やシール装置として電気装置を使うことが考えられますが、力は弱いです。
油圧をすべて電気に変えることができるわけではないので、インバータにすれば万能と思い込まないように気を付けたいですね。
電気盤が大型になる
インバータを付けるということは、電気盤が大型になります。
これは電気室の容量を圧迫させることになります。
新規プラントなどでは室の大きさを広げてしまい、コストアップに繋がります。
既存プラントでインバータ化するということは、電気室の通路などを狭くしてしまい安全上の問題が起こりえます。
現場では油圧や減速機などの装置が無くなり、スッキリしたように見えますが、裏の見えないところで苦労があるということですね。
参考
関連記事
最後に
インバータは化学プラントにおける運転の安定化、省力化、省エネに寄与する強力なツールですが、その導入には寿命、予兆管理、省エネ効果の限界、非対応設備、電気室設計への影響など多くの注意点があります。
「インバータにすればすべて解決」と過信することなく、適材適所での選定と、確実な保守管理体制の構築が必要です。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
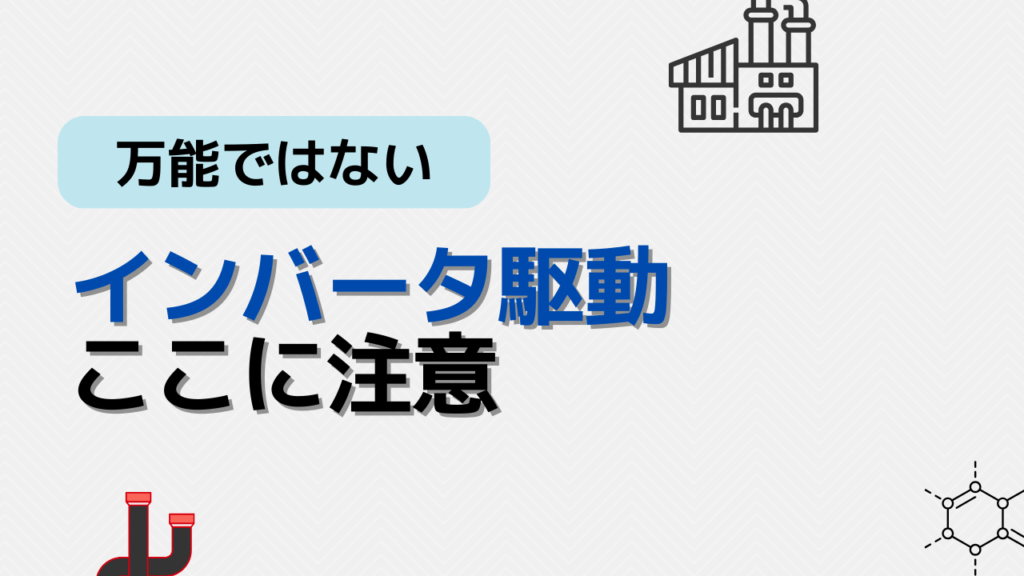

コメント