私の部署では製造現場の効率化を目的に3Dスキャナーを導入しましたが、思うように使いこなせず多くの課題に直面しました。
この記事では、部署の実体験を通じて初心者が陥りやすい問題やその対策をわかりやすく紹介します。3Dスキャナー導入を検討している方の参考になれば幸いです。
色々と理由を考えてみましたが、使う人たちにその気がないという結論に落ち着きそうです。成功しないでコストばかり掛けているので、早く打ち切れば良いのにそれもできない。負のイメージばかりが伸し掛かっています。
導入から失敗に至る現在までの過程をざっくり解説して、何が問題なのかを整理しようと思います。繰り返しますが、他の会社でも似たような感じだと信じています。でもそれでは駄目だということも・・・。
化学プラント配管設計に3D-CADが普及しない理由と現実
【化学プラントの現実】データ公開しても誰も見ない理由とは?
なぜプラントのDXは広がらないのか? 現場に潜む本当の壁
設備保全DX導入の現実:費用対効果評価の落とし穴と進め方
なぜDXが進まない?バッチ系化学プラントに残る「人が欠かせない理由」
設備保全のDXが進まない本当の理由:化学プラントが抱える根深い課題とは?
DXでは難しい日常点検、現場で求められる5感の力とは?
Excelと紙がプラントエンジニアの基本ツール
設備管理システム、導入したのに楽にならない?よくある7つの落とし穴
電話多用の背景を読み解く:保全担当がチャットより電話を選ぶ理由
プラントエンジニアが紙を使う理由とは?デジタル時代でも紙が欠かせないワケ
導入期
3Dスキャナという目新しい機械が発売されたことを知った会社は、「何としても速く導入するように」と飛びつきました。特に私の職場は、そういうことに敏感な人が数人いて、チャンスだと思っていたようです。化学会社の中でも導入したのは、かなり早いと思います。
その時には企画者を中心に、すごく積極的な取り組みをしていました。
保全や設計など機械系エンジニアの仕事がこれで楽になるはずだ。
そう信じて誰も疑ったなかったのでしょう。でも実は・・・
押し付けられて撮影
3Dスキャナは現場を撮影して、モデルをくみ上げていきます。当然ですが、現場で撮影するための工数が掛かります。
導入初期の機械は撮影時間が長かったり固定しないと行けなかったり、実用には多少の課題が残っている状態でした。それでも、早く導入して形にすることが求められた時代。
撮影をするために、機電系エンジニアの手も借りました。1日に1~2時間くらいの時間を使い、その分の残業が発生し、何とか撮影をしました。ただ、機電系エンジニアにとってはそれがどういう意味を持つのかイマイチ理解しておらず、上から撮影しなさいと指示があったから止む無く撮影していた感じでした。
実はこの段階ですでに失敗の傾向が出ています。やらされ感がある人達には新しいことは向いていないと判断できれば良かったです。
業務負荷の全体を把握していない
機電系エンジニアは自分の仕事や部の仕事の全体像をあまり理解してなかったりします。1日で何にどれだけの時間を使っているか整理しようとしたら、意外とできません。
- 毎日仕事内容が違うから
- 時期によって違うから
- 担当課によって違うから
違うことの理由を探し、共通項をまとめようとする人が誰もいない状態。一匹狼の保全のスタイルが受け継がれている部署だと、チームとしてまとまることの意味を全く考えないことを認識しました。
メーカーの営業の人なら、Aさんから技術的な質問が来たときに同じ部署のBさんがすでに導入している、というような例を何度も経験しているでしょう。ここには部内・チーム内で力を合わせようとしないメンバーの意識を感じることができます。こういう部署だと、3Dスキャナ他DXはとにかく失敗しやすいです。
業務の標準化ができていないのに仕組みだけ導入しても駄目。当たり前のはずですが、導入時には盲目的になります。
実用開始
私は3Dスキャナの導入にそれなりに関わっていました。機械を購入して、自分で時間と手間をかけて撮影して、いざお披露目となったときのことを、今でも覚えています。
見た目の受けは良い
モデルを組んで撮影に協力してくれた人に見せたら、みんな興味を持ってくれます。
「すごい」
大抵はこの意見だけです。そうです。そういう意見を聞くと努力が報われた気になります。
ただ、見た目は凄いのですが、それ以上の意見が出てきません。しばらくすると誰も何も言わなくなります。
管理職など一定の人は、後で「これでどういう成果を出せるだろうか」「これで合理化しないと生き残れない」と考えます。でも彼らでも考えるだけ口を出すだけ。提案したり、実際に手を動かすということはしません。成果が出てくるのを期待するだけです(それでも意見すら言わない人よりはマシですが)。
機電系は次の日には忘れる
スキャナの画面を見た次の日には、機電系はそのことを忘れています。
目の前のことが忙しくて、それどころではないのでしょうか。
機電系エンジニアのような設備に関する仕事をしている人で、事務所と現場が遠い場所にあって移動時間がもったいないという仕事をしている人に対して、3Dスキャナは絶大な効果を発します。
ところが、3Dスキャナで作業時間を短縮しないといけないという危機感が少ないからか、いざ実務で問題が起きたときには、現場に行ってしまいます。慌ててしまい、すぐに解決しないと行けなくて、これまでの経験で反射的にできる「現場に行く」という行動をとってしまいます。これを否定する人はおらず、実際に触る機会がどんどん無くなっていきます。
導入効果は、「関わる人の数」×「削減の時間」と考えると、人数の多い機電系こそが対象になるのですが・・・
プロセス系の人がたまに使う
3Dスキャナを意外と使っている人が居ることに気が付きました。
プロセス系の人です。
機電系と同じように現場に関わる検討をすることがあり、運転中に現場に行くことはあまり良くないと教わるので、こういうツールを重宝します。
完全に偏見ですが、職場内では機電系よりもプロセス系の方がスキルは高く・意識も高いです。3Dスキャナもその効果を認識し、機会を見つけて使っていこうという意識を持ってくれます。
衰退期
導入期を過ぎたと思ったら、いきなり衰退期に入ります。
安定期なんてものは存在しませんでした。導入して1年も経たずに衰退です。
アクセスが意外と面倒
3Dスキャナを使うためのアクセス方法が意外と面倒だったりします。起動に時間が掛かったり、使える人数が少なかったり。
数分待てば立ち上がるのですが、使おうと思ったときは大抵が雑談や議論の途中なので、その立ち上がり時間がもったいないと感じてしまいます。結果、見るのが面倒だから「後で現場を見に行く」という会話の終わり方をします。
これが常態化してしまって、3Dスキャナを見るという癖を付ける機会が無くなります。
メンテナンスが地味にかかる
3Dスキャナはメンテナンスが意外と大変です。お金も手間もかかります。
特にプラントの増改築が多い工場だと、膨大な撮影を毎年のように行わないといけません。これはかなり大変。
今では時間を緩和する新しい機械ができたりするのでしょうが、問題の本質は時間ではなく人のやる気の問題なので、新しい機械を買おうというモチベーションにはなりません。けど、担当者が使わない理由に、メンテナンスを上げます。体のいい理由だからですね。
残業で稼ぎたい・早く帰りたい
3Dスキャナを導入してしまうと、残業をする必要が無くなるかも知れません。これに危機感を覚えて、残業したいから3Dスキャナから遠ざかろうとしている人が居ます。もちろんこれは今ではレアなケース。
早く帰りたいけど、3Dスキャナを使って業務効率化をするのではなく、質を落として定時に帰るという人ばかり。
3Dスキャナなんて高度なことは良く分からないが、上から定時で帰れと言われるので仕事を適当にして帰れば良いのだ、と思っているようです。
仕事を変えるという経験がない
機電系エンジニアは自分の仕事を振り返ったり、効率化しようという意識が働きにくいです。
- 仕事は決まりきっている
- 仕事があるかどうかは製造課の状態で決まり、自分でコントロールできない
- 周りのシステムに左右されて、自分たちでは仕事内容を変えることができない
四方八方を囲まれてしまって、手も足も出ない状態になり、言われたことを愚直にこなすだけで認められる職場。この状態が続けば、仕事を変えようという意識が働かなくなるのも当然かもしれません。
周りが手助けして新たな仕組みを導入しようものなら、現場を知らないからかズレた仕組みになって、結果さらに使いにくくなってしまいます。これに意見しようものなら、最初から言って欲しいと反論。導入前に運用をイメージすることができないので、出来上がったものを無理矢理使うしかないという経験を何度もします。そうなると、導入前に意見すること自体が嫌になりますよね。
仕掛けつくりをしない
3Dスキャナを使うには、既存の仕組みを変えて無理矢理3Dスキャナを使う仕掛けを作るくらいでないと変わりません。
例えば、定例会議を設定するなら、現場に行かずに事務所を集合場所にするなど。
これを誰かが言わない限り、今まで現場に集まっていたから、これからも現場で・・・となってしまいます。
使ってメリットが出たら報奨がでる、評価にプラスになる、などの方法も有効ですね。
この辺は推進する人やそれを取りまとめる管理者の仕事です。よく管理者が悪いと言われる部分です。
存在そのものを忘れる
そうして「しなくて良い理由」をいっぱい探した結果、機電系エンジニアは3Dスキャナの存在そのものを忘れていきます。
3Dスキャナだけがこういう結末になればまだ良いのですが、他のDXアイテムも同じような感じで導入しても使わない、という結末。
「現場は大変なのだ」「現場の意見を聞かない企画者が悪いのだ」とだけを言っていられる立場ではないはずですが。
参考
関連記事
最後に
3Dスキャナは化学プラントのような設備系には業務効率化の夢が広がる話です。
私の職場でも導入されましたが、1~2年で誰も使わなくなりました。理由をいろいろ考察しましたが、「使う人がやる気がない」という結論に落ち着いています。
3Dスキャナーは強力なツールですが、使いこなすには経験と時間が必要です。私の部署の経験が、これから導入を考えている現場の参考になれば幸いです。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
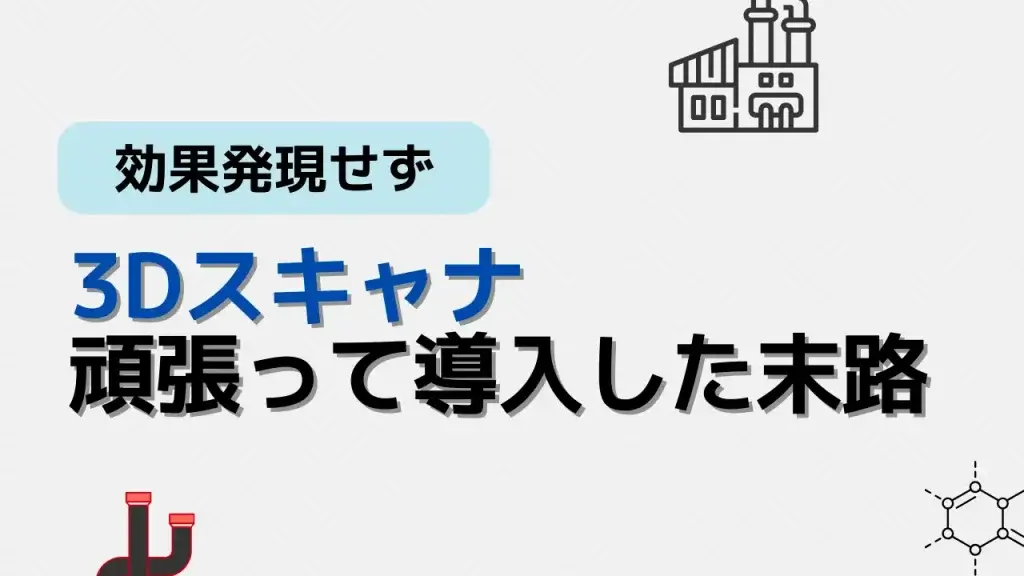

コメント