バッチプラントの性質や運用方法は、使われる特殊装置の特性によって大きく左右されます。
同じ「バッチ生産」でも、装置の種類や構造によって作業の手順や管理方法が変わるためです。
この記事では、特殊装置がバッチプラントの性質を決める理由と、そのポイントを初心者向けにわかりやすく解説します。
この記事は、プラント設計(長期)シリーズの一部です。
将来用途を含めないプラントを建てた後の悲劇
「足し算思考」の限界:化学工場が抱える改善不能の構造的問題とは?
プラント設計の最適化|プロセス面と設備面のバランスを考える
化学プラント建設は“立ち上げ”で終わらない!バッチ運転を見据えた設計の心得
スクラップビルドが化学工場の長期計画で大事な理由
オーナーエンジニアが知っておくべき“標準ユニット”の思想と実践
プラント設備をこんな風に標準化してはいけない
バッチプラントと特殊設備
化学工場などで採用されるバッチプラントは、自ずと考え方が似るものです。ところが、完全に同じプラントというのはあまり存在せず、そのプラント独自の設備があることも事実です。
バッチプラントは同じような設備が並んでいて、複数の生産品目を切り替えて使うため、どのプラントでもどの生産品目でも製造できるようにしておくことが、理想形です。
特殊設備はこの理想形を妨げる方向にいってしまいます。プラント建設などでは新技術をとにかく取り入れて競争力のあるプラントにしようと一時期は言われていましたが、長期的な目線では実は非常に困った発想です。作る側にとってはチャレンジングかもしれませんが、何十年と使っていき廃棄やその後も考えると悪影響の方が強いです。作るときの情熱の方が強くて、見過ごされやすいお話です。
バッチプラントでどういう設備がそのプラントの特殊性を高めているのか、いくつか紹介しましょう。皆さんのプラントでもバッチプラントが複数ある場合は、設備構成を簡単にリストアップして比較してみると面白いと思います。
粉体設備
化学プラントの場合、液体系と粉体系の2つに大きく分かれると言っても良いでしょう。製品が液体であるか粉体であるかで設備構成が変わります。
粉体系の場合は、液体系の設備(撹拌槽、ポンプ、熱交換器など)に加えて、粉体設備が必要になります。濾過・乾燥・破砕・輸送などの工程が加わり、専用の設備が必要となります。
液体系の製品しか使わない前提でプラントを建ててしまって後で粉体設備が必要となって増設したり、粉体設備を使う前提でプラントを建てたのに液体系の製品しか作らなくなって粉体設備が無駄になったり、サイクルの短い製品を使っている工場ほどリスクが高くなります。
粉体設備はあまりにも特殊なので、設備本体費用が高いだけでなくメンテナンス費も高いです。一度設置すると交換は難しいので、できるだけ同じ型式の粉体設備で合わせることが建設時に大事な考えとなるでしょう。メーカーの言う「こっちの方が良いです」という甘い声に乗らないよう・・・。
高圧設備
高圧設備もバッチプラントでは特殊な扱いです。反応器そのものだけでなく付帯設備も高圧が求められて、特殊な扱いになります。
そもそも1MPaを越える運転がバッチプラントでは、ほぼあり得ないレベルです。JIS10kフランジの設備が圧倒的で、JIS20kフランジの設備がある瞬間に特殊扱いです。
特定の生産向けにカスタマイズされた設備となり、別の製品に対して流用しにくいです。難しい設備で導入検討する時には研究としてはやりがいがあっても、後々の設計や保全としては検討対象にすら入らなくなります。
高耐食性材質
高耐食性設備はもちろん特殊な扱いです。SUS304やSUS316Lだけでなく、グラスライニングやフッ素樹脂ライニングもカーボンもセラミックも標準的なカテゴリ。
ハステロイとかさらに高耐食性の設備が特殊という位置づけになります。これらの設備は当然ながら高価でメンテナンスも追加金額が発生しうるものです。購入するにしても製作可能なメーカーは少なく、検討も慎重にせざるを得ません。
腐食は化学プラントの大敵なのでどうしてもこの材質が必要だと諦めがちです。高耐食性の設備がないプラントだから、新製品導入を諦められる場合もあります。実は使い方次第で低スペックな材質でも、使いこなせる場合があったとしても、です。
かといって、初めから必要がないのに高耐食性設備を導入するわけにもいかず、プラントのライフサイクルを考える上で粉体設備と同じく厄介な問題になります。
設備に限らず配管も特殊という扱いは可能です。こちらは例えば、SUS304とグラスライニングで構成されるプラントと、全てがグラスライニングで統一しているプラントというような、極端なケースが考えられます。
連続設備
連続設備は、バッチプラントでは特殊です。除害設備や用役設備などプロセスに直結しない連続設備は対象外。プロセス中に設置する連続設備で、その前後はバッチ運転をしていてもここだけ連続設備に切り替えるという特殊扱いとなります。
バッチプラントである以上は連続設備はそもそも少ないもしくはゼロであるべきです。連続設備がある分だけバッチ運転の設備を設置できる場所がなくなり、他のバッチプラントに対して製品を導入できる可能性が少なくなります。
共通的に使用できる設備数が少ないため長い工程の設備は導入しにくく、別のプラントから移す場合にはその一部の工程だけを移して残りの工程は他のプラントに移すという判断になります。このケースは一般にコストダウンにはならず、採用される確率が下がります。
結果、特殊なプラントとして競争力が少なくなっていく運命になりやすいですね。
特殊な撹拌翼
撹拌翼が特殊ということは、バッチプラントでは確実に特殊です。撹拌槽に代表される撹拌機付き容器は、バッチプラントではごく一般的に使用されます。
ここで例えばプロペラ翼、パドル翼、3枚後退翼のような一般的な構造であれば良いのですが、少し変わった構造にしただけでも、汎用性が失われます。
例えば高粘度用にアンカー翼を採用した場合、高粘度向けには使えるのですが他の用途には極端に使いにくくなります。その工場全体で高粘度液が確実にあるのなら良いのですが、そうでなければ特殊設備という扱いになって新製品導入の競争力を低下させることになります。
汎用的な撹拌翼ばっかり設計していて面白くないと思うか、汎用性が高くて生産調整がしやすいと思うかは、立場に寄ります。経営的には後者が助かりますね。
参考
関連記事
最後に
バッチプラントの性質は、使う特殊装置の性質に強く影響されます。
このため、装置の特長を踏まえた設計と管理が、効率的で安全なバッチ生産の鍵となります。
特殊装置の理解を深めて、バッチプラントの適切な運用を目指しましょう。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
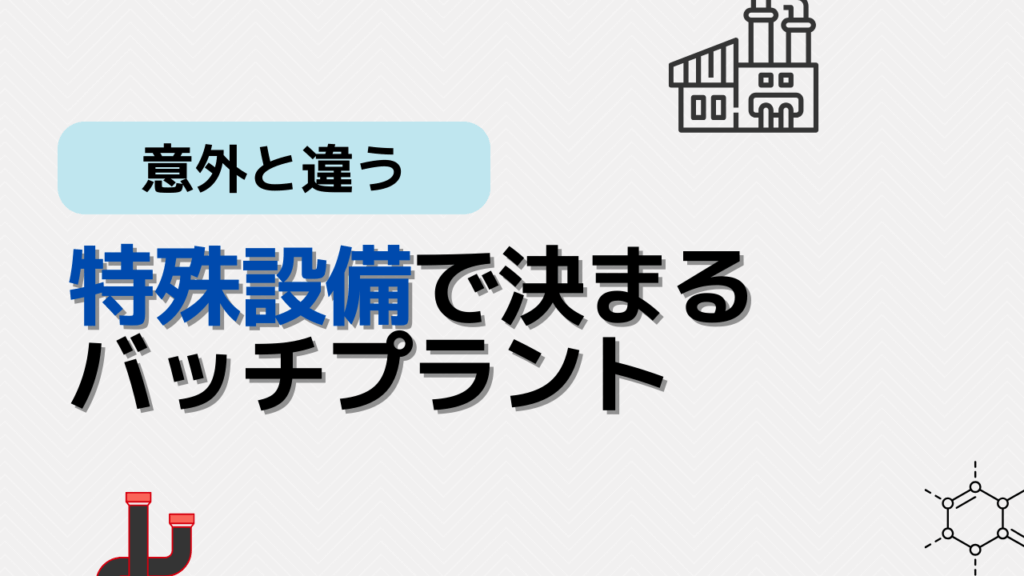

コメント