プラントエンジニアリングの現場では、「考えること」よりも「経験」が大切だと言われることがあります。私自身、これはある程度正しいと感じています。
たとえば、配管設計の仕事では、設計段階では見えなかった問題が、運転開始後にトラブルとして発生することがあります。ですが、そのトラブルも後から振り返ると起きて当然だと納得できることが少なくありません。
こうした失敗の経験を集め、知識として次に活かす仕組みを作ることは、安全安定な操業にとって非常に重要です。しかし、実際にこの「知識を蓄積する仕組み」を作るのは思った以上に難しいのです。以下では、私の実体験をもとに、その難しさと課題を紹介します。
報告書のハードルが高すぎる
多くの企業では、トラブルが発生した際に報告書を作成します。しかし、報告書作成には時間がかかるため、現場では敬遠されがちです。
私のいた組織では、報告書の承認者が部長クラスであり、内容は社内の広範囲に公開されていました。これは一見良さそうに思えますが、実際には現場の担当者にとって大きな負担になります。
工場で起こったトラブルは財産で、いろいろな人に知ってもらわないといけない。仕組みを作る上位者はこう思っていたとしても、担当者レベルでそうは思いません。
変なことを書いてしまうと色々な人から質問が来るかもしれない。公式の資料として扱われるから慎重に書かないといけない。部長の承認をもらうまでに何回も書き直しが発生する。こんな風に即仕上げるべき報告書が、体裁を整えようとするあまり時間が掛かっていってしまいます。結果的に、すぐに記録すべき内容が宙に浮いてしまうのです。
工場で起こったトラブルは公開すべき財産ではなく、一定の範囲内で止めておくべきものだと思います。他部署に公開するのは、1年に1回など緩いタイミングで過去にこんなことがあったという事後情報を共有する程度で十分だと思います。
原因追及に時間がかかりすぎる
報告書では、原因を明確にすることが求められます。しかし、プラントのトラブルの原因は一筋縄ではいきません。
設備に詳しいメーカーや、材料の専門家への確認が必要なケースも多く、調査には1年近くかかることもあります。製造部門からは「原因を突き止めて再発防止を」と求められますが、調査が長期化して途中で断念され、結果的に同じトラブルが繰り返されることがあります。
問題が起きたのは何かしら原因があって、同じことを起こさないために原因を考えること
これはプラントを預かる製造課からよく言われます。でも、原因を解決するために長い時間が掛かり、そのために原因究明を辞めてしまって、どこかのタイミングでまた同じ問題を起こすという展開になります。この時には製造課の担当者は入れ替わってしまっていて、過去に同じ問題が起きたことは忘れ去られます。
原因を求めた結果、知識の蓄積に繋がらずに、どちらにしても同じ問題が起きるなら、報告書なんて仕上げなくても良いですよね。
本当に大事なのは再発防止対策で、暫定的でも良いので対策を取った記録を残すだけでも、知識の蓄積になるはずです。それができないのは、エンジニアは原因を究明するという責務を課せられているからでしょうか。
数値目標にすると質が下がる
報告書は数値目標にしやすいので、成績目標に取り上げる場合があります。
これで報告書作成の数が増えるかも知れませんが、質は上がりません。共有するほどでもないトラブルが共有されます。情報が多くなってしまい、調べるのに時間が掛かってしまいます。
報告書を作らなくて普通、作ったらプラス評価であれば良いのですが、作らないことがマイナス評価に使われる可能性もあり数値目標が成功するというわけでもなさそうです。
定期報告会の落とし穴
報告書を作らない代わりに、製造課と進捗を定期的に確認する場を設ける仕組みが考えられます。1カ月に1回の月報のようなもの。
これをしてしまうと、できていない人を多くの人の場で晒してしまう可能性があります。原因を究明するために膨大な時間が掛かり、それを製造から問い詰められるのが典型例です。
製造も本当は原因はどうでも良いと思っていたとしても、その結果を工場内に報告する時には原因を求められてしまうので、仕方ないかもしれません。
設備のトラブルの大半は機械関係で起こり、機械関係者以外は聞かなくても良い報告会。報告会では資料を作るわけでなく口頭で情報がやり取りされたり、月報に1行書かれる程度でしょう。これなら、データベースとしては残りません。
参考
関連記事
最後に
プラント現場での知識蓄積には、多くの落とし穴があります。ポイントは次の通りです。
- 報告書作成のハードルを下げる
- 完璧な原因究明にこだわりすぎない
- 数値目標化で質を落とさない
- 定期報告のプレッシャーを軽減する
これらの工夫により、現場経験を次に活かす実務的な知識蓄積の仕組みが生まれます。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
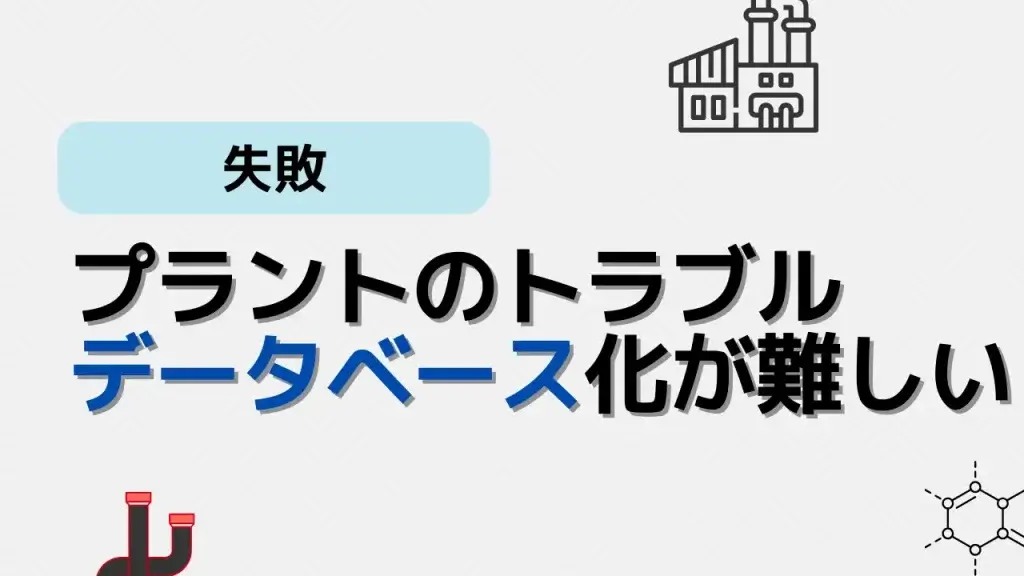

コメント