化学工場で用役(ユーティリティ)というと、水・蒸気・空気・窒素・電気の5つが基本です。化学反応で化学物質を変化させて目的の物質を作り上げていく中で、これらの用役の存在は必要不可欠です。
エンジニアリングの実務面では、軽視されがちです。基本内容物であって、必要な配管スペックが決まっているから、今さら考えることはないという感じでしょう。
ところが、実際に運転したり新設備の導入検討をしたりする際の、そのプラントの実力を測ろうとしたときには、用役の使用量がどれくらいであるかすら分からなかったりします。流量計を付けずに「何となく」でしか把握してないことも。化学物質側は精緻に管理しても、用役側は緩かったりします。
本記事では、流量計を付ければ解決するものの投資ができなかったり、流量計の精度は必要でないけど大きく外れない管理値を持っておきたいなど、用役使用量を実務面で管理する時のコツのようなものを紹介します。
何も根拠が無いよりは、まだ良いという程度の話です。
水
水は工業用水や冷却水のように、仕込に使用しない水をここでは扱います。道中に流量計がなく、専用タンクがなく液面計も無いような場合です。
除害水
除害水として工業用水を入れ苛性ソーダなどと混ぜて使用する場合、一定頻度で入れ替えを行います。例えばバッチ運転なら、除害設備のタンクを1日に1回入れ替えるとします。この場合は、
タンク液量(m3/回)×入替回数(回/日)=使用量(m3/日)
で計算します。連続的に水を入れ替える場合は、
流入水流量(m3/h)×24(h/日)=使用量(m3/日)
で計算します。この場合は、流入水の流量は滞留時間や苛性ソーダの流量と直結するので、それなりの値で管理されていないといけません。自ずと流量計相当の物が必要になってしまいます。
新プラントや新製品の検討段階で良く分からない場合には、私はバッチの計算を使っています。
ジャケット水
反応槽や熱交換器などのジャケット部に水を使用する場合は、水の入れ替えをするかどうかがポイントです。バッチ運転の反応槽の場合、加熱に温水・冷却に冷水を1つの装置で使うことがあります。この場合は、温水と冷水の入れ替え時に排水をします。計算はシンプルに
ジャケットの容量(m3/回)×入替回数(回/日)=使用量(m3/日)
です。ジャケットの容量計算は図面を見ればわかる場合もありますが、面倒なら容量×1/10くらいで計算しています。
連続運転の場合、水の入れ替え自体が起こらないはずなので、この項目の計算自体がありません。
冷却塔
冷却塔では冷却水の蒸発が起こるので、常時補充が必要です。冷却塔の蒸発量と補充量は一般に定められている計算式を使います。
私はすごく簡単に、5℃×循環水流量/500×2くらいを使っています。
循環水流量の計算が面倒かもしれませんが、プラント入口の循環水口径から計算できます。例えば200Aであれば、50A200L/minくらいの標準流量としてその16倍(200/50の2乗)で3200L/minですので、4600m3/日くらいですね。ここから冷却水の補充量は、
5×4600/500×2=9.2m3/日
となります。
シール水
使用量が意外と多いのがシール水です。メカニカルシールなど常時流している場合には、それなりの使用量になります。例えば、私は
2(L/min)×60×24/1000=2.8(m3/日)
くらいで計算します。2L/minはメカニカルシールへの注水量です。メカニカルシールの台数分で効いてくるので、かなりの量になります。
蒸気
蒸気の使用量は、流量計で管理していると思います。高価なので管理してないというのは問題です。少なくとも現地式流量計があれば、使用量はそれなりに分かるでしょう。
加熱量
加熱に蒸気を使う場合は、プロセス上で熱計算をしているはずです。
比熱×容量×温度差
蒸発潜熱×蒸発量
反応槽の容量が分かれば概算の計算もできますが、上記の計算をした方が安心感があります。比熱や蒸発潜熱は水や一般的な有機溶媒で代表させて良いでしょう。
温水に蒸気を使う場合も、温水の使用量と温度が分かれば計算できます。温水の使用量は蒸気の使用量より低くなるはずなので、計算が面倒であれば蒸気として計算しても、プラント全体としては大きな問題にはならないでしょう。
スチームトラップ
スチームトラップを使用していると、蒸気の漏れが考えられます。概算計算としては
1台当たり5kg/h
というくらいの数字を使っています。例えば、50m4階建てのプラントの場合、
メイン配管で15個
反応槽1基あたり1個で10個
その他サブ装置で5個
合計30個
5kg/h×30=150kg/h
というような計算をします。
5kg/hという数字が不安なら10kg/hでも良いと思っています。トラップの1つや2つは漏れがあるものですし、配管放熱量をドレンとして考えるなら多少の余裕を持っても良いという考え方です。
空気
空気の計算量は、実は相当難しいです。単独プラントなどコンプレッサーとプラントが1:1で関連つけられている場合は、コンプレッサーの能力で代用しても良いでしょう。コンプレッサーを複数のプラントで共用している場合は、計算が辛いです。
空気は計装設備の駆動に使い、エアーシリンダの容量で決まります。少しまじめな計算としては、以下のような感じでしょう。
エアー圧力0.5MPa
シリンダ容量1L
自動弁の個数50個(概算)
開閉回数2回/日
(5+1)/1×1L×50×2=600L/日
このオーダーだと、コンプレッサーや配管からの漏れの方が多い気もします。かといって、流量計やタンクを設けるほどでもないので、管理が難しいです。
ざっくり計算上は、コンプレッサーの能力をプラントの数で単純に割るくらいでもいいと思っています。
窒素
窒素も空気と同じように難しい側面があります。
常時流入
危険物タンクへの窒素シールなどの目的だと、例えば以下のような値で代用します。
1基辺り20NL/min
1日に換算すると28.8m3/日ですので、それなりの量です。タンク10基で288m3/日となります。
窒素ブロー
ライン送液用の窒素ブローは、以下の計算をします。
窒素圧力×配管容量
配管50Aが50mの場合、配管1m当たり2L程度なので、50mで100L程度の容量です。窒素圧力0.2Paとすると、
(0.2+0.1)/0.1×100=300NL/日
という計算になります。ラインブローを20個行っても、6m3/日というオーダーです。
窒素置換
毎バッチ窒素置換が必要な工程だと、置換量は計算に入れましょう。
タンク容量(m3)×置換回数
3m3のタンクを1日に5回置換するなら、それだけで15m3/日です。ラインブローより多くなりそうですね。
電気
電気は使用箇所が多いので、計算が複雑にならないようにするために、選別が大事です。
モーター容量が大きい
使用時間が長い
この2つで絞り込みが大事です。例えば、
撹拌槽15kWを10台、24時間運転 → 150*24=3,600kWh/日
ジャケットポンプ5kWを6台、24時間運転 → 5*6*24=7,200kWh/日
冷凍機30kW2台、ポンプ30kW4台、24時間運転 → 30*6*24=4,320kWh/日
エアコン30kWを4台、24時間運転 → 30*4*24=2,880kWh/日
照明 → 100kWh/日
合計 18,100kWh/日
という試算をします。バッチの場合だと短時間だけ動かすポンプ類は誤差範囲になります。
電気量は測定が容易なので、実際のデータを見比べると良いでしょう。この計算よりは高い値が出るはずです。簡易計算と実測値の差を係数として整理しておけば、新プラントや新製品の導入のときの計算に使いやすくなります。
参考
関連記事
最後に
ユーティリティ使用量の把握は、化学プラントの性能評価やコスト管理に直結します。高精度計測が困難な場合でも、簡易計算式を活用すれば、根拠ある使用量を把握できます。日常管理に取り入れることで、設備の健全運転と効率化が実現できます。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)X(旧Twitter)のDMでも可能です。
- 設備設計で悩んでいる
- トラブル原因の考え方が分からない
- 若手の教育方法に困っている
など、幅広くお受けしています。
*いただいたコメント全て拝見し、数日中に真剣に回答させていただきます。
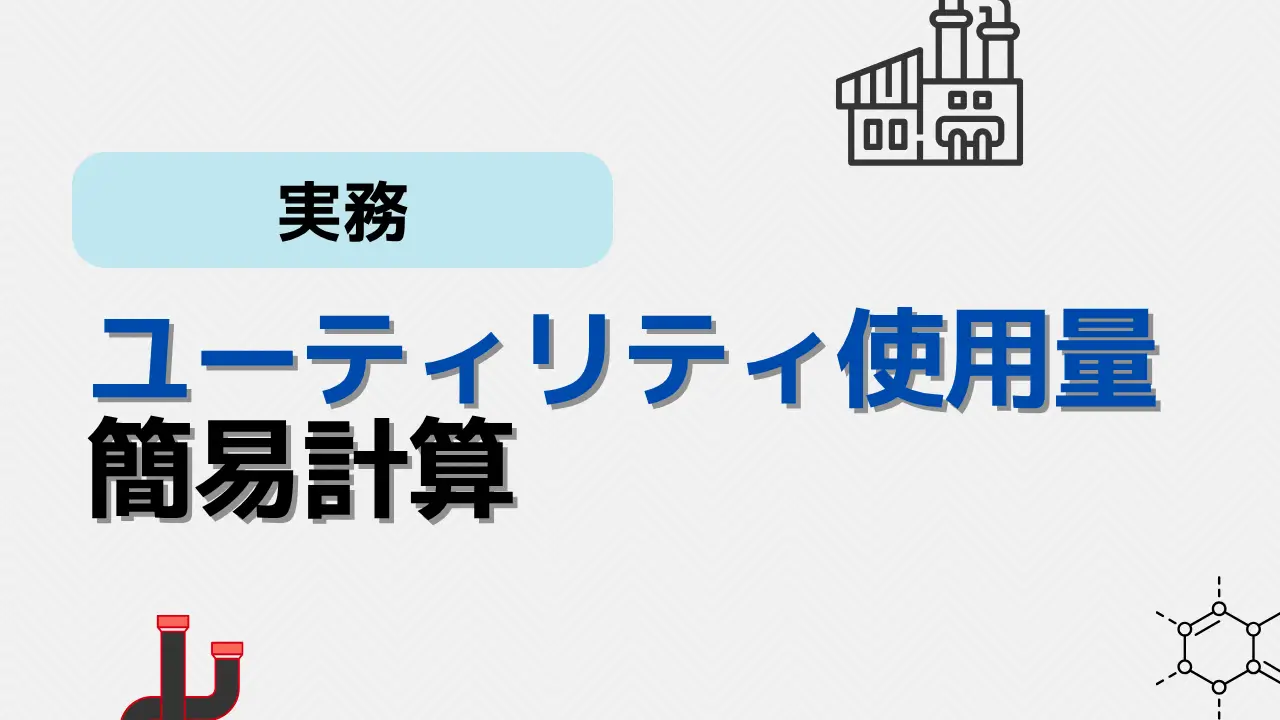

コメント