化学工学は、化学プラントの設計・運転に欠かせない理論的基盤です。このカテゴリでは、物質移動(拡散・移動速度論)、熱交換の基礎、反応工学(反応速度式・反応器設計)、および蒸留・吸収・抽出といった分離操作の理論と応用を丁寧に解説します。特にプラント現場で遭遇する問題に対して、どのように化学工学の知識が活かせるのかを、実践例を交えながら紹介。
また、初心者向けに難解な式や理論も図や比喩を使って噛み砕いて解説し、日常業務での「なぜ?」に答える構成になっています。
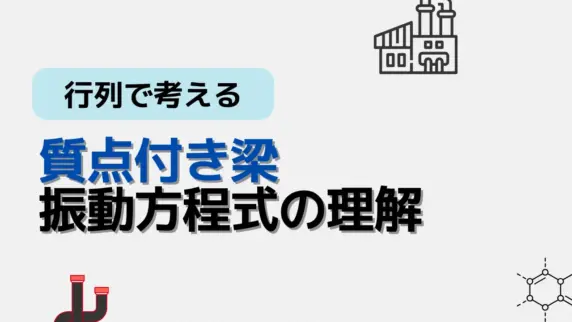 化学工学
化学工学 質点付き梁の運動方程式を解説|振動工学の拡張モデルを理解する
質点付き梁の運動方程式をわかりやすく解説。片持ち梁に質点とばねを加えた場合の運動モデル、m=0・m=∞の考察、固有モードへの影響まで振動工学の基礎から丁寧に説明します。
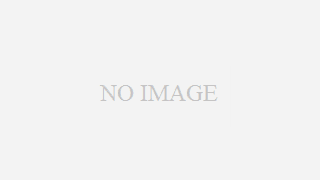 化学工学
化学工学 計算フォーム「蒸発凝縮計算」の解説
計算フォーム「蒸発凝縮計算」の解説です。蒸発凝縮計算の基礎をまとめました。
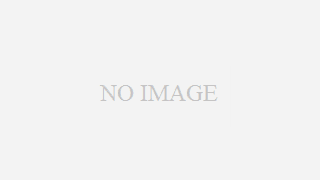 化学工学
化学工学 計算フォーム「熱計算」の解説
計算フォーム「熱計算」の解説です。熱計算の基礎をまとめました。
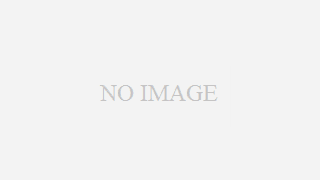 化学工学
化学工学 蒸発凝縮計算
熱計算でも相変化が伴う場合は計算がやや複雑になります。この計算ができるようになれば、能力設計の基礎が確立できたと言って良いと思います。詳しい解説はこちらをご覧ください。記事水封式真空ポンプのプロセス条件の決め方水蒸気蒸留のかんたんな計算イメ...
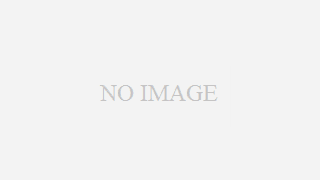 化学工学
化学工学 熱計算
熱交換器を中心に幅広く使います。必要な伝熱面積から設備サイズを決定するほか、既存設備を使った運転でサイクルタイムを計算する場合にも使います。詳しい解説はこちらをご覧ください。記事伝熱計算の例|化学プラント槽型反応器伝熱計算をここまで理解でき...
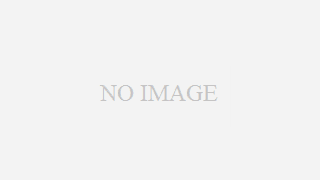 化学工学
化学工学 単位換算
SI単位系ばかりで統一されているわけでなく、旧単位との関りが強いので単位換算は頻繁に行います。それぞれの単位の意味を理解して使いこなせるようになりましょう。1つ前に戻る
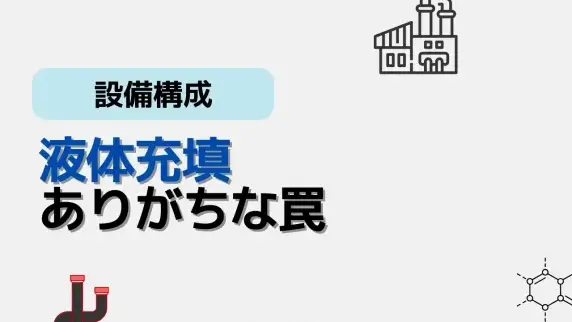 化学工学
化学工学 当たり前じゃない?液体充填設備の基本と落とし穴
液体充填は昔からある古典的な方法ですが、作業環境や設備はアップデートされにくい場合があります。昔からやっているから良いだろうと判断されかねません。現在の安全性や作業性に関する要求を振り返って、できる対策を考えていくことはエンジニアにとっても大事でしょう。監査などで指摘する側も、最高スペックを目指すのではなく基本レベルを満足するように注意したいですね。
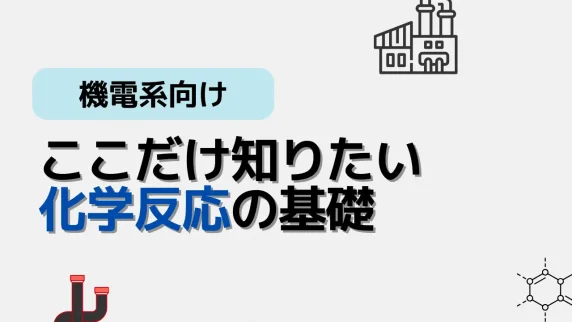 化学工学
化学工学 機電系エンジニアが知るべき化学反応の基礎とその重要性
機電系エンジニアが知っておくべき化学反応の基礎とその重要性を解説。反応式だけではわからない現場の実態や副生成物、製品劣化への影響を理解し、プラント運転の安全性と効率向上に役立てましょう。
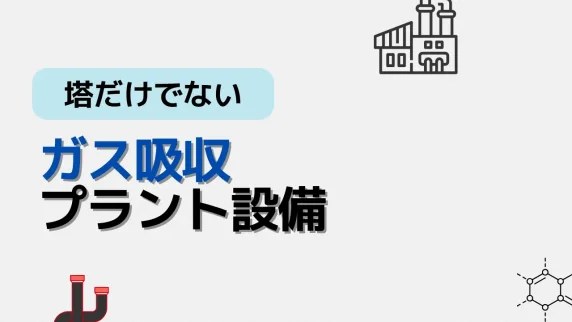 化学工学
化学工学 ガス吸収のために使うプラント設備4選
化学プラントでのガス吸収設備を解説。塔・エゼクター・反応器・真空ポンプの仕組みと特徴、適用範囲や注意点を比較し、安全で効率的なガス処理の考え方を紹介します。
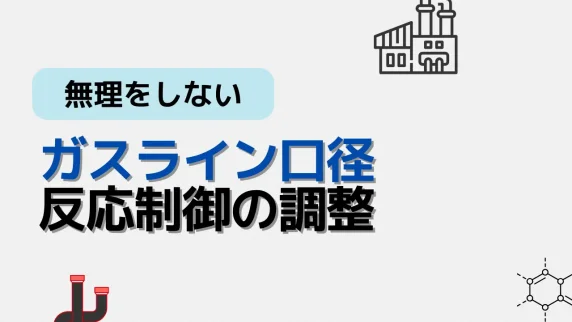 化学工学
化学工学 ガスライン設計の限界と反応調整によるプロセス制御の実際
ガスライン設計の物理的な限界を補うために、反応段階で調整するプロセス制御の実際を解説。設計と運転の連携による安定運転のポイントも紹介します。