化学プラントにおける設備投資を成功させるには、初期段階のFS(フィージビリティスタディ)の進め方が重要なカギを握ります。
しかし、前提条件があいまいなまま進めてしまうと、後の工程で見積額が大幅に変動し、企画そのものが頓挫するリスクも。
本記事では、プラントエンジニアや工場サイドが押さえておくべき「初期FSで確認すべき3つの重要ポイント」について詳しく解説します。
プラント新設レベルではなく、既存プラントに新しい生産品目を導入するケースを考えています。(建設よりも圧倒的に頻度が高いです)
この記事は、FSシリーズの一部です。
FS(フィージビリティスタディ)における余裕率の理解:ラング係数や設計係数が示す現実的なコストバッファ
化学工場のFSとは?基本と進め方をわかりやすく解説
知らないプラントの見積もりで不確実性を減らす方法|初心者向け解説
【化学プラント設計の裏技】0.6乗則で建設コストをざっくり見積もる方法
配管長さを超ざっくり数えるときのコツ|設備投資・設計・比較に役立つ思考法
配管見積の考え方|初心者もわかる現場で役立つポイントと注意点
前提条件を整理する
ステージが浅いFSでは前提条件を特に整理しましょう。
この段階では、製法であるプロセスフローは固まっていません。
メインの反応ですら、いくつかの選択肢が残っています。
しかし設備投資の見積を行うには、製法が決まっていないとできませんよね。
そこで、いろいろな前提条件を置きます。
前提条件が分からなくて、高い側と低い側の設備投資案がある場合、高い側で見積をします。
取扱物質自体の特性や反応後の後処理など、反応以外に必要な設備がどれだけあるかで設備投資の額は大きく変わります。ところが、これこそがステージの浅いFSでは見えていません。同じように高い側で見積をします。
FSのわりに、生産数量が決まっていないということも結構あります。
生産開始するまでに5年~10年の期間があるので、需要が予測できないことも。
研究段階の数字だけしかなく、商業運転の数字が検討されていないということも。数パターン明確にしておきましょう。
これらの条件は明確に記載しておく必要があります。というのも、ステージが深くなっていって、FSの精度を上げるときに、前回のFSから大きく金額が変わったら問題になるからです。特に後のステージで金額が上がった場合、前回何を見ていたのだ?という責められ方をするでしょう。
ステージの浅いFSでもその金額で採算が取れるかどうか、ざっくり計算しています。その前提条件が覆ってしまったら、長い間掛けて開発した新製品が無駄になってしまいかねません。
FSを依頼する側も、当然このリスクを気にしています。経営層に説明する際の材料として、前提条件がクリアになっていると、そのせいにすることが可能です。
ステージの浅い・深いいずれでも前提条件を明確に記載することはとても大事です。特に、リスクの部分は。
目標金額を確認する
ステージの浅いFSでは目標金額を確認しましょう。
社内のFSなので、可能な場合があります。
見積をする工場サイドとしては、そのFSで企画部から気に入ってもらう必要があります。
その金額に載せるように設備投資案を考えることは、工場サイドの必須スキルとも言えます。
コンペでなければ教えてくれるでしょう。コンペでも社内コンペくらいだったら教えてくれると思います。
この金額感が無ければ、FSを機械的に行うことになり、提示した金額が高いから導入されないという悲しい結末になりえます。
私が機電系エンジニアとして設備メーカーや工事会社とやり取りしている時には、こういう話はできませんでした。社内での見積なら、技術者同士で金額についての話ができるので、斬新な気分になります。
期限を確認する
FSと言っても、期限は短いものです。
どれくらいの期間が与えられるかによって、戦略の取り方が変わります。
ステージが浅ければ、期限が短くても済むことが多いです。
精度を設定する
期限を確認したら、精度を設定しましょう。
これは投資規模によって変わります。
ステージが浅い時には50%~100%の差があっても気にならないです。
例えば10億円程度だろうと予想していたら、10億~20億円と範囲を示します。
3億円程度の見積になりそうなら、5億円と丸めることもあります。
何億円単位で丸めるかが、投資規模によって変わるでしょう。
この数字はステージが進むと勝手に独り歩きします。
前に10億円といったのだから、今回も10億円であるべきだ。もっと合理的な案を考えて9億円にしたらなおヨシ。こんなノリは昔は珍しくなかったのですが、今はそうではありませんよね。
FSは数年以上の長い間に、何回も行います。
5年前に10億円という見積をしていても、同じ内容を今行えば20億円。そこにステージが上がって前提条件の精度が上がって見積が増えて、30億円になった。
こんなことも起こりえます。
ステージが浅いころには前提条件が固まっていないこともあり、そこで精度を上げても仕方がないというのが大切な考え方です。時間を掛けても仕方ないです。
この情報は工場サイドとしては自分の隠し種として持っておきます。公開して企画部に渡してしまうと、後で困るのは工場サイドです。
プラントエンジニアだと、設備の細かい金額を積み上げていくことが多く、その情報を正確に持っていてもステージの浅い段階では効果が低いです。高額の設備だけを着目して、一定の余裕率を勝手に決めてしまうくらいでちょうど良いでしょう。
参考
関連記事
最後に
初期FSで差をつけるには、「前提条件の明文化」「目標金額の把握」「見積精度の適正化」という3つの確認事項が鍵となります。
これらを意識することで、無駄な手戻りを防ぎ、関係者の信頼を得ることができます。
初期段階だからこそ、慎重かつ柔軟な思考が求められるのです。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
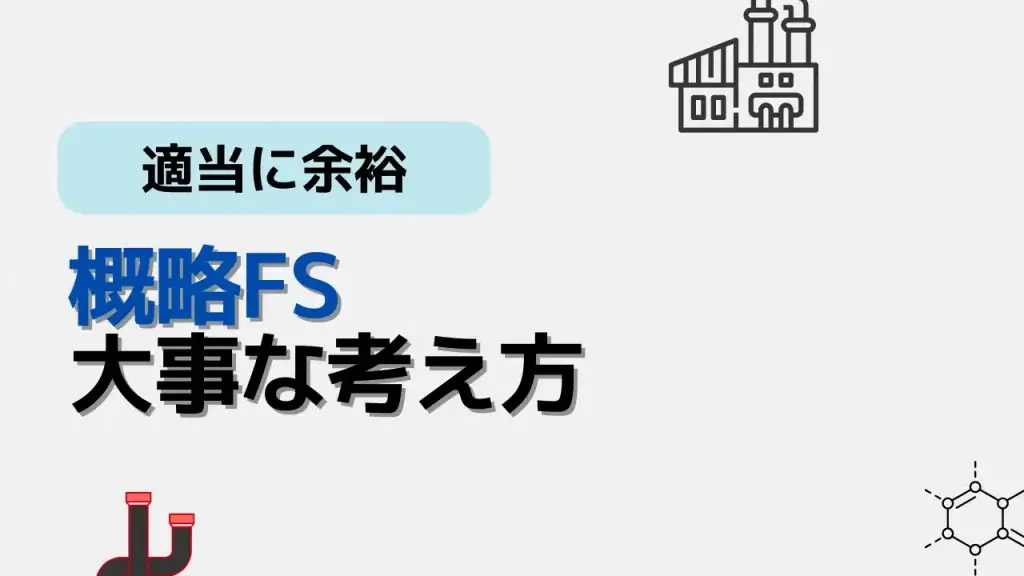

コメント