化学プラントのプロセス設備では、シールの役割は非常に重要です。特に大口径の配管や装置では、漏れを防ぐためのシール設計が難しく、失敗すると重大なトラブルにつながります。
なぜ大口径のシールは漏れやすいのか、そして設計時にどんなポイントに注意すべきかをわかりやすく解説します。これから大口径設備の設計や保全に関わる方は必見の内容です。
この記事は、シールシリーズの一部です。
シールの基礎知識|化学プラントで漏れを防ぐための設計と選定の考え方
化学プラントで使われる迷路シール(ラビリンスシール)とは?仕組み・メリット・注意点をわかりやすく解説
バルブの漏れ対策|グランドパッキンの基本と選び方・メンテナンスポイント
グランドパッキン(グランドシール)とは?仕組み・目的・使い方をわかりやすく解説
初心者向けにわかる!化学プラントのメカニカルシール基礎ガイド
メカニカルシールのフラッシングプラン典型3選|API
ポンプのメカニカルシールが漏れる原因と取れる対策
迷ったらこれ:化学プラントでダブルメカニカルシールを選ぶべき理由
バルブの種類で変わるシール性|ボール・バタフライ・ゲートの違いを解説
Oリングとベローズのシール性能の違い|化学プラント
大口径のシールの特徴
最初に大口径のシールの特徴をまとめます。
大きなサイズはズレる
サイズが大きいと、製作上の誤差・ズレがその分だけ大きくなります。
配管など取付の精度にも影響が出てきます。
シールする部分がズレたり波打ったりして、しっかりシール部品を投入したとしても、シールが上手くいかない可能性が上がります。
大きな設備は強度が弱い
設備が大きくなると、同じ板厚でも耐圧力は下がります。
強度面で弱くなるので、シール圧力は高く取れない設備が多いです。
もちろん大型設備で高圧力で使うという場合は、板厚やフランジ厚みを徹底して上げることになります。
そのようなニーズはバッチプラントではまず考えられないですね。
動く機械は注意
機械のシールを考えるとき、動機器と静機器という2つに分けて考えることがあります。
一般に動機器の方がシール寿命が短いと考えられます。
口径が大きいとシールがしにくくなるので、口径が大きいかつ動く機械というのはリスクが高い設備と考えましょう。
濾過機や乾燥機などの粉体設備が当てはまりやすいです。これらの設備は使用圧力はほぼ大気圧ですが動くという点が怖いです。
ガスケットは限界がある
ガスケットはサイズの限界があります。
原料からくり抜いて製作するという工程のため、原料の大きさに依存します。
メーカーや型式によって差はありますが、最大口径が1m~3mと考えましょう。
バッチプラントでは、配管として1mのサイズとなることはあり得ないレベルですが、装置だと当然発生します。
ガスケットは当たり面が大きく、ボルトで締めたときにシールしやすい特徴があります。
圧力が高い・動きやすい設備・内容物がとても危険、などの厳しい側の条件なら、なるべくガスケットを使うようにしましょう。
イニシャルコストを考えて、ガスケットが高いから採用しない、としてしまうと後で大きな勉強代を払うかも知れませんよ・・・。
ソフトタイプは漏れる
ソフトタイプは、サイズに関する制約がほぼありません。
コードシールという名であまりにも有名ですね。
ほぼ自由に形状を作ることができるでしょう。
しかも安いです。
一方で、漏れのリスクが上がります。
静機器であればある程度耐えるでしょうが、動機器は漏れやすいです。
危険物を扱う化学プラントでは特に注意が必要です。
コードシールは自由度が高いがゆえに、巻き方によって性能が変わります。
溝形フランジにするなど、誰が巻いても同じ結果になるようにフランジ側に工夫が必要になります。
溝形にしたから安心というわけでなく、溝部の角でシールが破れることも十分に考えられます。
Oリングは高い
Oリングはシール材の王道。
いろいろな場所で使い、化学プラントでもよく使います。
大口径という意味では、ガスケットよりもさらに制約が強いです。
大きくても1m~2m程度。
それ以上に問題なのが費用。
耐食性を上げるためには、Oリングだと選択肢が限られます。
しかも費用は以上に高いです。
小口径でも耐食性Oリングは高めの傾向なので、Oリングはとにかく避けた方が良いというのが、持論です。
マグネットポンプなどでたまに見かけて困ります。
参考
関連記事
最後に
大口径のシール設計は「製作誤差」「強度低下」「動く設備のリスク」「シール材の制約」という複数の課題を抱えています。化学プラントの安全で安定した運用を支えるためには、これらのポイントをしっかり理解し、最適なシール材選定と設計を行うことが不可欠です。
特に危険物を扱う設備では、安易なコストカットが後々の大きなトラブルにつながるため注意しましょう。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
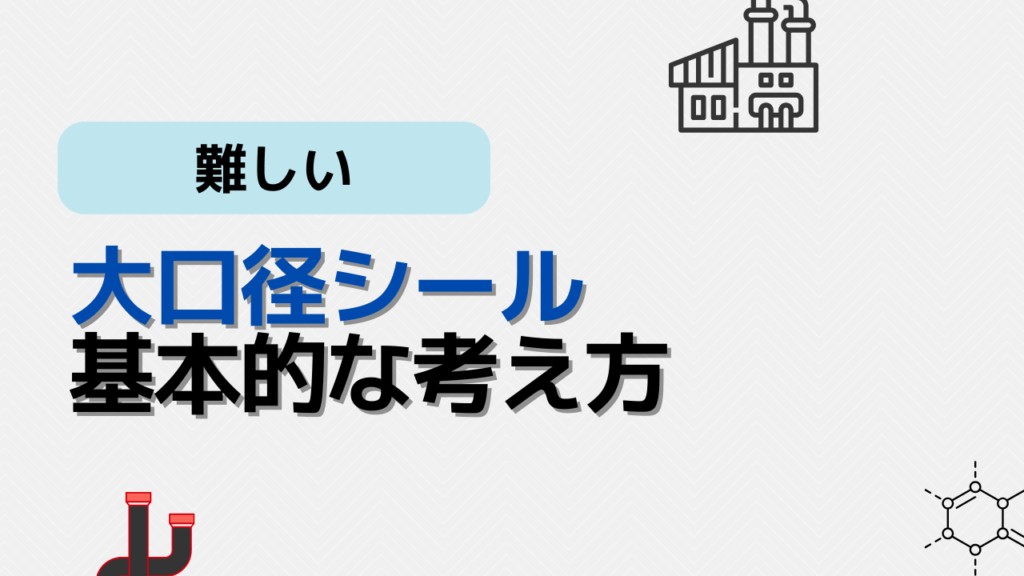

コメント