逆止弁は「一方向にしか流さない」便利な部品ですが、すべてを任せきりにしてしまうのは危険です。化学プラントの現場では、逆止弁の動作不良によってトラブルが発生することもあります。
本記事では、実際の経験をもとに、逆止弁に頼りすぎることのリスクと、それを回避するための設計・運用上の工夫について解説します。
逆止弁は過信しすぎてはいけません。思想は会社によって差がありますが、こう考えてはいかがでしょうかという例を紹介します。
逆止弁のマイナス面の特徴
逆止弁のマイナス面の特徴を整理します。
使ってはいけないという意味ではありませんが、弱点はしっかり理解しましょう。
逆止弁は作動時間差がある
逆止弁は作動するまでに微妙な時間差があります。
例えば液体を流しているラインで、Aという物質を流していたとしましょう。
2次側に高圧のBという物質があって、本来は逆止弁に到達しないはずなのに、何らかの原因で逆止弁に向かって高圧のBが流れようとします。
このとき、Aは正規の向きに流れようとせず、Bに押される形になります。
当然、AとBは混じり合った状態になります。
逆止弁が作動するには、逆向きの圧力差が必要ですが、AとBが混じり出してから圧力勾配が変わるまでに時間差があります。
この間に、逆止弁の正規とは逆向きにAとBが混じり合ったものが流れます。
高圧のBが逆流してはいけないので、逆止弁を付けたとして、これだけでは完全に防止することはできません。
可能なのは、大量の逆流を防止するということ。
少量の混入で大事故に繋がる物質は存在しますし、ちょっと混ざっただけでも異物になったり品質に影響が出たりと問題になりえます。
被害を最大化させないために逆止弁を付ける、という程度の認識が適切だと思います。
自動で開閉する
逆止弁はその構造上、圧力変動で簡単に開閉します。
手動弁や自動弁のようにハンドルで強制的に開閉するわけではありません。
逆流が起きそうなくらい微妙な圧力状態の時、圧力変動によっては逆止弁が開いたり閉じたりという微妙な状態を繰り返します。
逆止弁で完全に遮断すると考える方が無理があるでしょう。
詰まる
逆止弁は詰まることがあります。
スラリーなど固形分が混じった液体では、逆止弁中に引っかかってしまい、逆止弁が閉まらなくなることがあります。
もともと信頼が置けない逆止弁ですが、完全に信頼できなくなる瞬間です。
逆止弁は抵抗となる
逆止弁は抵抗(摩擦抵抗)となります。
スイングでもリフトでも流体の力で弁を押す以上は、抵抗となります。
これで流量が不足するという例はかなりあります。
ポンプの圧力損失計算で忘れやすいので、ラインを正確に追って逆止弁の数を数えましょう。
抜けない
逆止弁がライン中に複数個付いている場合は、要注意です。
2個の逆止弁の間に液体や気体が残ってしまい、抜けなくなります。
こうなると、ポンプで押し出そうにも上手くいかなくて、運転ができなくなります。
気休めでも意図して付けたはずの逆止弁が、意図とは違って邪魔する形です。
逆止弁は壊れる
逆止弁は他のバルブに比べて壊れやすいです。
これは動きが多いからです。
例えばスイング式だとピンがすり減ります。接触する部分ですからね。
リフトでもシール面が傷つきますし、ボール式でスプリングが付いているものはスプリングが壊れます。
完全な逆流を防ぐにはアナログな方法で
逆流を防ぐという目的を達成する場合、アナログな方法を採用しましょう。
- 配管を接続しない
- 遮断板を付ける
という方法が定番です。
自動弁で制御する場合は、測定器をセットにしないと難しいです。それでもチューニングをしっかりしないと信頼が置けないでしょう。
参考
関連記事
最後に
逆止弁は非常に便利な部品ですが、「つけておけばOK」という考え方は現場では通用しません。適切に設計・運用しなければ、逆流によるトラブルやプロセスへの影響が発生します。
設計者や現場担当者は、逆止弁の限界を理解したうえで、必要に応じて補助的な機器や設計配慮を加えるべきです。
逆止弁は気休め程度に考えるのが良いです。完全に逆流を止めるには、測定計器と自動弁を使ったり、ラインを切り離すという古典的な手法にしましょう。
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
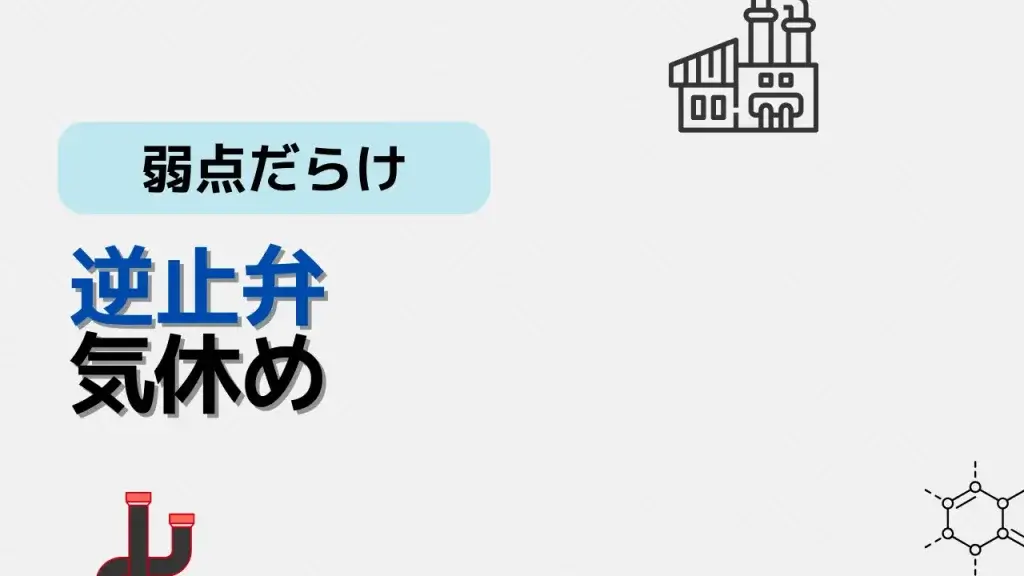

コメント