化学プラントでは、設備トラブルは避けて通れません。
トラブルが発生すれば、まずは生産技術・保全担当が呼ばれて修理に奔走します。そして、落ち着く暇もなく「原因は?報告は?」と求められるのが現実です。
しかし、近年は「原因が分からない」ケースも増えており、必ずしも保全だけで原因を解明するのは現実的ではなくなっています。
この記事では、化学プラントの故障原因解析がなぜ難しくなっているのか、そしてどう向き合うべきかについて解説します。
分解できない
原因解析をしようとしたら、最終的には分解しないと分かりません。
腐食などの問題なら材料を切断して、研究室で解析しないと分かりません。
これを分解せずに判断したり、実物が入った状態で原因解析を求められたりします。
それではどうあがいても分かりません。
トラブル経験が少ない
設備洗浄をして分解したり装置内に入って、目視で確認したとしましょう。
これだけで、原因が何なのかはっきりと答えられるケースは多くはありません。
- 腐食であるのか摩耗であるのかすら、一概に言えるものでない
- 腐食なら隙間腐食なのか応力腐食割れなのか、目視だけで確認できる人は専門家だけ
これは、トラブルの経験が少なくなった現在ならではの問題です。
保全課と言えども世代交代はされ、過去の知見は揃ってはいないか整理されておらず使えない、トラブルは実はあまり多くない。
この状態で育った保全が、トラブル解析をすること自体が難しいです。
メーカーも専門家ばかりではないので、メーカーに依頼しても時間が掛かります。
その間に、上層部からは「早く解析を・・・」と詰められるわけですね。
使用条件が分からない
使用条件が分からないから判定できないというケースは、少なからずあります。
連続プラントで単一使用条件なら、比較的考えやすいでしょう。
バッチプラントでは複数の条件で運転するし、毎バッチ起動停止が発生するので、何が故障原因なのか特定するのが難しいです。
細かく条件を調べるだけでも、実は結構時間が掛かります。
例えば、シールレスポンプの空運転で壊れたとしましょう。
典型的な空運転で起こった故障でも、いつどうやって壊れたか?を特定するのは結構難しいです。
- スラリーが多めにいて詰まったのか
- バルブを絞り過ぎたのか
- 温度が高くてキャビテーションが起きたり、低くて固化したり
- 部品が寿命で壊れたり
- 製品とは違う異物が入ってきて壊れたり
いろいろ考えられます。
答えられなくても良しとする風潮を
保全が原因解析をするというのは、実際にはかなり難しくなっているでしょう。
この事実をしっかりと認識し、保全に責任を押し付け過ぎないような風潮が大事になります。
- 長期運転していたら壊れて当たり前。原因を調べて対策を打つくらいなら予備を持つ
- 使い始めたばかりで壊れたのなら、まずは運転条件を疑う
- 詳細検討をしない限りは全て推定原因であり、できる限り調べたという納得感で妥協する
時間を掛けても、成果に結びつかないならしない方が良いです。(この場合なら、解析して再発防止が期待できるなら、解析の価値があるということですね)
みなさんの職場では、原因解析を細かく聞かれるでしょうか・・・。
参考
関連記事
最後に
化学プラントの故障原因解析は、近年ますます難しくなっています。
分解不能、経験不足、条件不明などの現実を踏まえ、「原因が分からないこと」を前提に対策を取ることも重要な選択肢です。
完璧な解析を目指すのではなく、「納得できる推定と対策の実行」が、現代の保全には求められています。
ここに時間を掛けても、故障頻度削減などの効果が得られないなら、割り切ってTBM的に予備を持って交換していく方が健全です。検討に欠ける時間も立派なコスト。トータルコストを考えましょう、
化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)
*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。
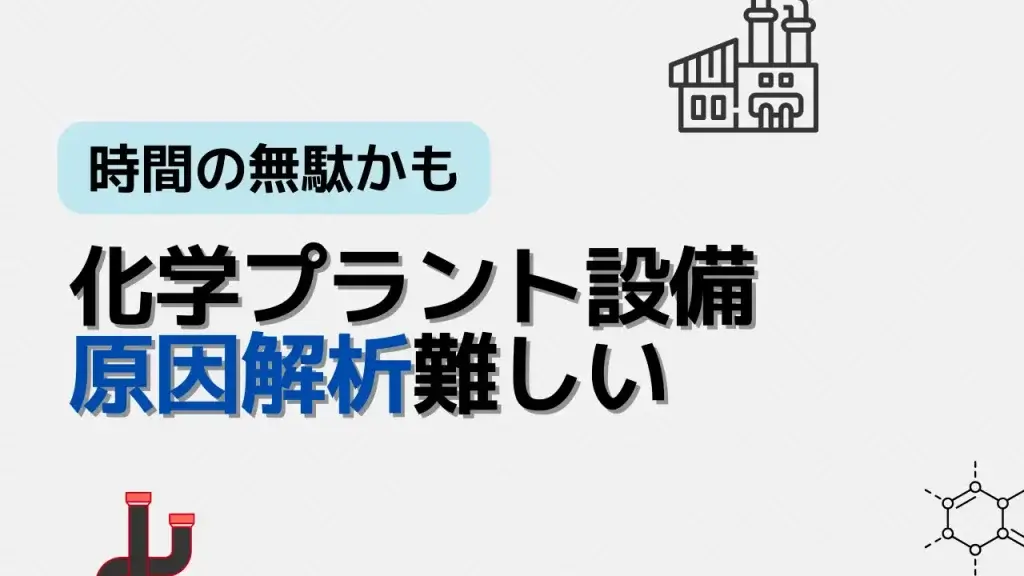

コメント